
「成功者の勉強法をいろいろ試してみたけど……。どれもしっくりこない」
「自分に合う勉強法が見つからない。やっぱり勉強に向いてないのでは……?」
上記のように、勉強法を確立できないという悩みを抱えていませんか? もしかすると、勉強法に関するちょっとした “勘違い” をしている可能性が。
今回は、「どの勉強法も合わない」と嘆く人が勘違いしているかもしれないことを、3つ取り上げます。ぜひ、ご自身の勉強法改善に役立ててくださいね。
勘違い1「ちゃんと勉強すれば、“順調に” 成果が出るはずだ」
効率的だと言われる方法で勉強していけば、成果は順調に出るものだと考えていませんか?
勉強の途中には必ず踊り場(停滞期)がある——こう語るのは、「7回読み」という独自の勉強法を編み出し、東京大学を首席で卒業した山口真由氏。つまり、勉強の成果というのは右肩上がりには伸びないのが当たり前だということです。
山口氏によれば、なかなか成績が伸びない人がやりがちなのが、「この方法で合っているのかな……?」と自分の勉強法を疑ってしまうこと。疑った結果、別の誰かのやり方のほうが効率的に思えたり、全然違うほかの勉強法に手を出してみたり……。このように、やり方で迷いすぎると、勉強にムダが生じてくると言います。伸び悩んだからとすぐ新しい勉強法に変えたところで、成績が上がるとも限りません。

世界記憶力選手権で日本人初のグランドマスターとなった池田義博氏によれば、技術は練習量にともなって直線的に上達していくわけではないのだとか。上達度を表す線は、順調な右肩上がりの線にはならず、階段状になるそう。「上達→停滞→上達……」というように、伸びる時期と伸びない期が繰り返されるのです。
この途中におとずれる停滞期のことを、プラトー(学習高原)と呼びます。池田氏いわく、プラトーの時期は、脳が情報を整理して使える知識へと変える作業を行なう、「知識の習熟期間」。言い換えれば、停滞期を通ることで、物事への理解が深まり、次の段階へ成長できるということ。
ですから、「いま取り組んでいるやり方で成果が出ない」と感じたからといって、勉強法をまるっきり変えなくてもいいのです。
とはいえ、プラトー期を抜け出す取り組みはしたいもの。そこで参考になるのが、公認心理師の大美賀直子氏がすすめる “小さな工夫” です。
たとえば、勉強方法にちょっとした新鮮さを加えると、思いがけない発見があり、勉強がはかどる可能性があるとのこと。参考書を頭から順に読むのをやめ、好きな章から順に読んでみるのは、その一手だそうです。いままでのやり方に、小さな変化を加えることがポイントですよ。

勘違い2「予定していた勉強量が終われば、とりあえずOK!」
「今日やるべき勉強量は達成できた」というだけで、十分だと考えてしまっていませんか?
ちゃんとやれたぞという達成感にひたるのはいいですが、“勉強してそのまま” の状態でいると、いつまでも自分に合う勉強法は見つけられないかもしれません。
教育アドバイザーの伊藤敏雄氏は、勉強しても成績が上がらない原因のひとつとして、「振り返りを丁寧に行なっていない」ことを挙げています。
伊藤氏いわく、そもそも勉強とは「わからない」箇所を「わかる」ようにすること。答え合わせを丁寧にやらない、間違えた箇所の解き直しをしない、なぜ間違えたのかを考えない……というように、勉強をやりっぱなしにすると、自分の現状も弱点もわからないまま。丁寧な振り返りは、「わからない」ことが「わかる」ようになるために欠かせないと伊藤氏は説きます。
さらに、非効率な勉強法の見直しに役立つという点でも、振り返りは重要です。
現役東大生で勉強法に関する著作を多くもつ西岡壱誠氏は、勉強には「PDCAサイクルを回す」という思考が必要になると言います。Plan(計画)、Do(実行)、Check(確認)、Action(改善)のうち、特に大切なのはCheck(確認)の工程だそう。
勉強を実行したあと、いまの勉強にムダや非効率なものはないかチェックし、不要なところをどんどん削っていく——こうしてつど自分の勉強法をアップデートしていくことが、成績を上げるためには重要なのです。
「予定していたページ数や問題数はちゃんとこなしたぞ」というだけで満足していてはいけません。PDCAサイクルを怠らずに回し、”いまの自分に本当に合ったやり方” を見つけてくださいね。
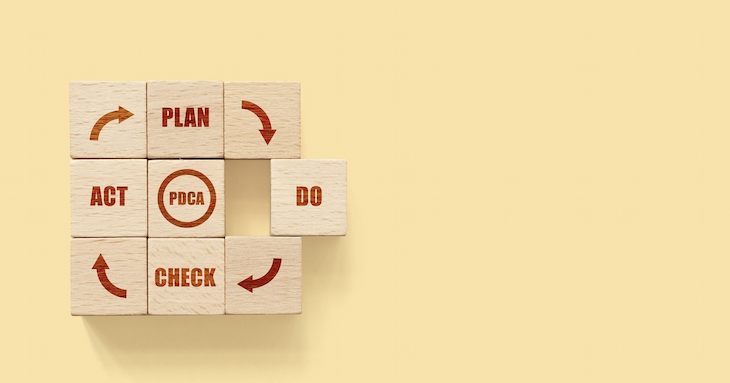
勘違い3「成功者の勉強法のとおりにすれば、きっとうまくいくだろう」
ハーバード大卒、東大卒。勉強で成功した人物が実践していたとおりにやれば、きっと自分も成果が出るはずだ――と、“成功者の勉強法” にとらわれすぎるのにも注意が必要です。
行政書士など9つの資格に独学で合格した棚田健大郎氏は、最初に受けた宅地建物取引士の試験に失敗したことで、自己流の勉強法を編み出し始めたと語ります。というのも、当時棚田氏がやっていたのは、有名大学出身者が提唱した勉強法ばかりだったのだとか。
そもそも、「絶対的に正しい勉強法」は存在しないと棚田氏。有名大学出身者のやり方は棚田氏には合わなかったようですが、そのやり方で成果が出る人もいるでしょう。成功者がやってきた勉強法をいろいろ試したけれど、どれも合わない……と感じているなら、自分に合うやり方にアレンジすることが必要なのです。
前出の西岡氏によると、東大生の多くは、勉強のやり方について “納得感” を重視しているのだそう。独自の勉強法を編み出す場合でも、誰かの勉強法にならうときでも、自分が納得できるように工夫するのだと言います。
もちろん、人から教えてもらったやり方を実践していた、という東大生もいます。でも彼ら彼女らも、よく聞いてみると、理由もわからずそのまま真似していたというよりも、そのやり方を自分なりに解釈して、自分用に改造して、実践しているということが多いのです。「自分が納得できるやり方」を試しているのが東大生の特徴なのです。
(引用元:東洋経済オンライン|ドラゴン桜で理解「東大生が勉強好きになる秘密」)
成功例はあくまで参考。「絶対にその通りにしなくてはいけない」と考える必要はありません。
それよりも優先すべきは、勉強法の効果を理解し、さらに納得いくやり方にアレンジしながら実践してみること。西岡氏によれば、納得感が生まれてくると、勉強の楽しさも感じることができるそうですよ。
***
個人に合うやり方は千差万別。試行錯誤を重ねながら、勉強の楽しさを感じられるベストな方法を見つけ出してくださいね。
(参考)
STUDY HACKER|勉強が「できる」とは「楽に、楽しめる」こと。シンプルに、学ぶことを “好き” になればいい
ダイヤモンド・オンライン|天才にもおとずれるプラトーの正体とは?
All About|プラトー期からの脱出法…ダイエットや勉強の停滞期に
All About|勉強しても成績が上がらない!その原因は?
東洋経済オンライン|東大生直伝「成績上がる子」見抜くただ1つの質問
ダイヤモンド・オンライン|「がんばっているのに報われない人」に共通するNG行動
東洋経済オンライン|ドラゴン桜で理解「東大生が勉強好きになる秘密」
【ライタープロフィール】
青野透子
大学では経営学を専攻。科学的に効果のあるメンタル管理方法への理解が深く、マインドセット・対人関係についての執筆が得意。科学(脳科学・心理学)に基づいた勉強法への関心も強く、執筆を通して得たノウハウをもとに、勉強の習慣化に成功している。

