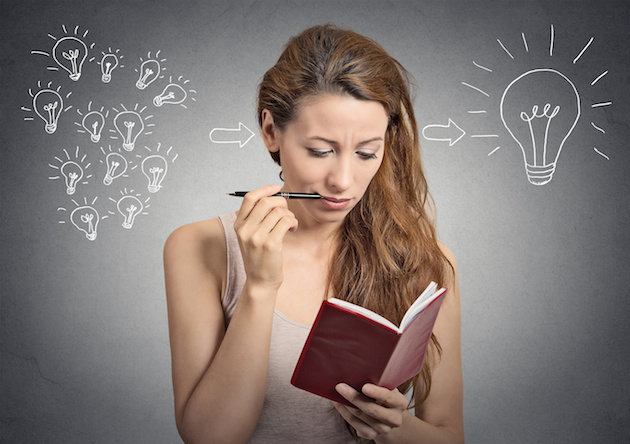選択式のマークテスト。絞りに絞った末に残った選択肢は二つ。そういえばさっき2番だったから今度は3かな?いやでもちょっとこれ怪しいよな……。よし、思い切って!
学生時代、こんな葛藤に苛まれた経験はないでしょうか。もちろん実力で正答を導き出せればいいですが、そうはいかないのが試験というもの。最後の最後で直観に頼ることは、かなりあるはず。
社会に出てからもそれは同じ。プロジェクトの重要な決定から、今晩の献立にいたるまで。日常生活で直観が活躍する場面は相当あるでしょう。そんなとき、プロの棋士やスポーツ選手のように、直観力があればどれだけいいことか。
最近の研究では、特別な才能がなくても、直観は鍛えられるのだということがわかってきています。重要な決定を素早く決める力。あなたもきっと欲しいはず。
今回はそんな「直観力」を鍛えるお話。
 霊感でもなんでもない!直観は脳のはたらきにすぎなかった。
霊感でもなんでもない!直観は脳のはたらきにすぎなかった。
ひらめき、直観、インスピレーション。こんな言葉を聞くと、これらは何か第六感的なものによって起こされると思いがち。しかし理化学研究所によれば、人間の直観的戦略決定は脳の一部分である「帯状皮質」で起こるんだとか。
これは将棋でアマチュア三段、四段の実力者に協力してもらった実験。将棋の盤面を5秒間だけ画面に表示し、どんな手を打つか瞬時に答えるというもの。「戦略決定」というと大げさな気がしますが、晩ごはんの献立を決めるのだって広い意味では立派な戦略のひとつ。直観で物事をきめる、という点は同じでしょう。
ここから分かるとおり、直観は脳のれっきとした機能のひとつ。素人にだって、鍛えられないはずがないのです。
 才能なんかじゃない。直観は経験によって養われる!
才能なんかじゃない。直観は経験によって養われる!
勝敗やルールが明確なチェスや将棋は、昔から認知科学・脳科学の分野で様々な研究に利用されてきました。
そんな中、トップレベルのプレーヤーがもつ特徴は「短時間で最善手を直観的に導き出す能力」にあると結論づけられたんだとか。
勝負の世界には、瞬間的に有利不利を判断して正しく対処できる優れた能力を持つ人がいます。このレベルに達するには、その分野での集中した訓練を長期にわたって行うことが必要であるといわれています。運動技能の訓練の場合と同じく、訓練の初めには意識的に時間をかけて解決策を考え出します。しかし、経験が蓄積するにつれて思考過程は自動的に、そして素早くなっていきます。 (引用元:理化学研究所「素人でも訓練によりプロ棋士と同じ直観的思考回路を持てる -直観的思考は継続的な練習の積み重ねで養われる-」 )
実力あるプレーヤーほど「直観力」が優れていて、それは訓練によって身につくものなのだということ。
そこで理化学研究所ではさらに、将棋をほとんどやったことのない素人をトレーニングする、という実験を行いました。
具体的には、20代の男性20人を対象に、簡単な将棋のゲームを4ヶ月間毎日行わせ、脳の働きを計測するというもの。初めはなかなかうまくいかなかったものの、訓練を続けた結果、直観を司る例の「帯状皮質」が活性化したそうです!
ここで注意してほしいのは、彼らは決してトレーニングによってパターンを暗記したり、定石を覚えたりしたわけではないこと。経験を積むことによって、毎回毎回新たな状況に瞬時に対応する力、直観力が養われたということです。単に暗記したわけではない、ということは脳の働きをみればわかります。
それも、4ヶ月のトレーニングによって。しかも驚くべきことに、1日に訓練に要した時間はたったの40分だそうです。
自分の直観を信じるのが怖い…というあなた。大切なプロジェクトにしろ、センター試験にしろ、1日40分くらいの努力は誰もが積み重ねてきたはず。だったら、恐れる必要はありません。思い切って選んだ選択肢は、おそらくかなりの高確率で正しいはずなのです。
 自分を信じろ!プロの直観はあなたの中にもある。
自分を信じろ!プロの直観はあなたの中にもある。
理化学研究所の発表から見えてきたのは、「直観は努力によって培われる」ということでした。ひらめきやインスピレーションは、日々の泥臭い積み重ねによってしか生み出されないのです。
だとすれば、ここ一番の勝負のとき。最後の最後で「キメ」なければいけないとき。努力を重ねてきたならば、直観は自然とあなたを正解へと導くはずです。
そう思えば、これから自分の直観に少しは自信が持てそうじゃありませんか?
「天才は99%の努力と1%のひらめきからなる」といエジソンの言葉。 その1%のひらめきさえも、残りの99%によって生み出されるのかもしれません。
参考 理化学研究所「直観的な戦略決定を行う脳のメカニズムを解明 ―棋士の戦略決定は帯状皮質ネットワークで行われる―」
理化学研究所「素人でも訓練によりプロ棋士と同じ直観的思考回路を持てる-直観的思考は継続的な練習の積み重ねで養われる-」