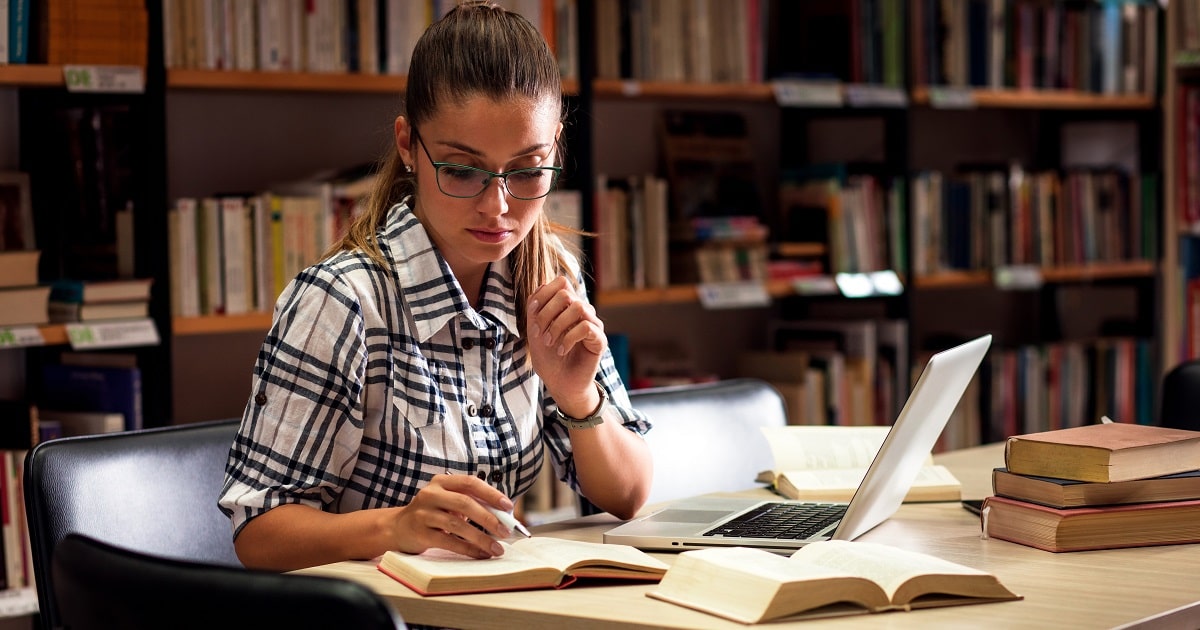
みなさん、復習のタイミングはつかめているでしょうか。「勉強では復習が大事」という話はよく聞くけれど、具体的にいつどうやればいいかわからない。そんなことはありませんか?
実は、脳科学を利用した最適な復習方法があるのです。効率的かつ効果的な記憶術をお伝えしましょう。
復習を繰り返すと、覚え直すのにかかる時間は短くなる
ドイツの心理学者ヘルマン・エビングハウスが発見した、人の記憶力に関する曲線「エビングハウスの忘却曲線」を知っていますか?
エビングハウスは、自ら無意味な3文字の羅列(子音・母音・子音から成る無意味な文字列。rit, pek, tas……など)を覚え、それを思い出せるかどうかを調べる実験を行いました。そして、2回目以降に覚え直す際、最初に覚えた時と比べて、完全に覚えるのにかかる時間をどれだけ節約することができたかを示す割合である「節約率」というものを導き出しました。それが以下の通りです。
1時間後:44%
約9時間後:35%
1日後:34%
2日後:27%
6日後:25%
1ヶ月後:21%
例えば、「1日後は節約率が34%」とありますが、これは「最初に覚えるのにかかった時間の66%の時間で覚え直せる」という意味です。最初に10分で覚えたならば、「翌日には3~4分節約でき、6~7分で覚え直せる」ということになります。(1日経つと66%の内容を忘れてしまう、ということではありません。)そして、1日後に復習すれば節約率は34%なのに対し、1ヶ月後にようやく復習する場合の節約率は21%。復習するタイミングが後になるほど、覚え直すのに多くの時間がかかってしまうことも明らかにされました。
この節約率は、無意味な文字の羅列を記憶する実験によって得られたデータです。実際の勉強では意味のある内容を覚えるでしょうから、節約率はさらに高くなります。
ここまで説明してきたことを踏まえて復習を行えば、最低限の復習時間できちんと記憶の穴を埋めることができます。復習といえば、勉強した翌日あるいは1週間後などに1回だけするという人は少なくないと思いますが、重要なのは「ベストタイミングで復習を繰り返すこと」なのです。

海馬を騙す反復学習
復習を繰り返すことは、脳の記憶の仕組みから見ても有効です。
脳では、海馬という部位が何を記憶するか選別する機能を司っています。入ってきた情報を海馬が「記憶すべき」と選別すれば、私たちはその情報を記憶することができます。その選別基準は「生命の存続に必要かどうか」。海馬が、「これは生きていくために不可欠だ」と判断した情報は記憶され、「必要ない情報だ」と判断されたものは捨てられていきます。
人間も動物ですから、食べ物や危険に関する生死に密接な情報は優先的に記憶されます。しかし勉強で覚える情報は、たいていの場合生命の存続に直結するものではありません。ですから、海馬の取捨選択によってすぐに忘れてしまいます。では、どうすれば、勉強の内容を必要な情報だと海馬に判断させられるのでしょうか。
脳研究者で東京大学薬学部教授の池谷裕二氏は、この問いにこう答えています。
生き死ににかかわらない情報でも、何度も繰り返し脳に送り続けると、海馬は「これは生きるのに必要な情報に違いない」と勘違いしてくれます。そう、海馬をダマすわけです。繰り返すことで海馬に重要な情報と思わせる。これがポイントです。
(引用元:WAOサイエンスパーク|こうすれば記憶力は高まる!~脳の仕組みから考える学習法)太字は筆者にて施した
つまり、復習の反復が重要だということ。何度も何度も復習すれば、海馬が情報を受け入れ、確実に記憶することができるのです。

インプットだけでなくアウトプットを重視した復習を
また池谷氏は、情報を記憶するには暗記という情報の「入力」だけでなく、情報の「出力」が大事だと言います。なぜなら、海馬は、目からしか入ってこない情報よりも、実際に使った情報を圧倒的に優先するから。脳は、出力する(使用する)回数の多い情報を重要な情報だとみなすのです。
そのため、教科書や参考書などを何度も読み直すインプット重視の復習法よりも、書く・声に出す・問題を解くといったアウトプット重視の復習法のほうが効果的です。内容がより強く記憶に定着するでしょう。
さらに、興味のある情報や、感情を交えた情報も記憶に残りやすいそうです。例えば、全く知らない人の誕生日を覚えるより、仲のいい友人の誕生日を覚えるほうがずっと楽ですよね。このように、勉強でも覚えたい内容に興味を持つと効果的です。外国語を勉強したいなら、本や映画などを通じてその言語が使われている国について知り、愛着を持って勉強するといいかもしれませんね。
また、勉強に感情を交える方法としては、以下のようなものが挙げられます。ぜひ試してみてください。
- 歴史の知識を覚える際、歴史上の人物の気持ちを想像し「悔しかっただろうな」「大変だっただろうな」などとイメージする。
- 仕事で必要な知識を覚える際、「この知識があれば〇〇社との取引がうまく進みそうだな」「〇〇なシーンですごく役に立ちそう!」などとイメージする。
***
復習の効果は、やり方次第で大幅にアップさせることができます。記憶の仕組みを理解して、脳を操るように効率的な暗記を心がけましょう。今回ご説明した復習方法を実践すれば、覚えたい内容がスムーズに、そして確実に頭に入ってくるはずです。
(参考)
Security Awareness App|The forgetting curve of Herman Ebbinghaus
Wikipedia|忘却曲線
WAOサイエンスパーク|こうすれば記憶力は高まる!~脳の仕組みから考える学習法
プレジデントオンライン|「復習4回」で脳をダマすことができる

