
知識が豊富でいつもユニークな提案をする同僚がいる一方で、自分の意見はパッとしないものばかり。「ビジネスでは多様な視点を持つことが大切だ」「物事はいろいろな角度の切り口から考えるべきだ」とは言うけれど、新しい視点なんてどうすれば得られるのだろう……とお悩みではありませんか?
実は、多様な視点を持っている人は、普段から「学びに敏感」なのです。そこで今回は、知識を増やして視野を広げ、多様な考えを持つことができるようになるための「学びのアンテナ」の広げ方をご紹介します。
「視野を広げる」ために必要なこととは?
「自分の視野を広げたい!」とは思っても、そもそも「広い視野を持つ」とはどういうことなのだろう。そんな疑問をお持ちの方もいることでしょう。
投資銀行やコンサルティングファームなどでグローバルに活躍した経歴を持ち、ベストセラー『最強の働き方』の著者でもあるムーギー・キム氏は、視野が広い人のことを次のように述べています。
視野を広げるとはどういうことか? これはつまるところ、他の人よりも違った視点で考えることができ、問題や事象の全体像を多角的にとらえることができることを意味する。 異なった考え方ができる人とは、単に変な人のことを指しているわけではない。周りの同じようなことばかり考えている賢い人たちに対し、自分のユニークなバックグラウンドやスキル、視点から付加価値を提供できる人のことである。
(引用元:DIAMOND online|一流が実践する「視野を広げる習慣」の中身)太字は筆者にて施した
これをもとに考えると、視野の広い人になるためにすべきことは、他の人とは違った知見・経験を持ち、他の人とは違う考え方をして、自分に付加価値をつけていくこと。つまり、視野を広げるには、さまざまな分野に関心を持ち、積極的に学ぶ必要があるのです。これが、この記事で言う「学びのアンテナを広げる」ということ。逆に言えば、学びのアンテナを広げない限り、視野は決して広がらないのです。
世界の一流ビジネスパーソンたちと共に働いてきたキム氏によれば、一流は皆視野が広く、また広い視野を持つために日頃から多様な分野を積極的に学んでいるのだそう。
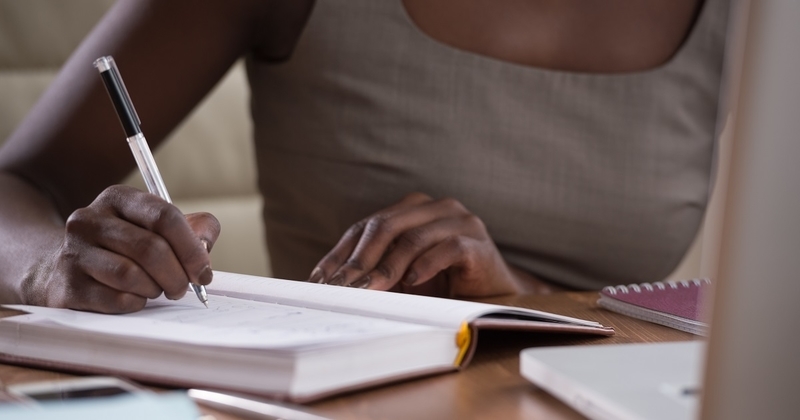
また、学びのアンテナを広げることには他にも次のようなメリットがあります。
・仕事力がアップする
東北大学加齢医学研究所教授で脳医学者の瀧靖之氏によれば、脳は知的好奇心がかきたてられると神経伝達物質であるドーパミンを分泌するそう。ドーパミンには思考力や判断力、記憶力を高めるなど高次認知機能を活性化させる働きがあります。つまり、学ぶことに意欲を持ち、学ぶ楽しさを感じれば、仕事力アップが期待できるのです。また、学ぶこと自体を心から楽しめば、リラックスでき、仕事や人間関係におけるストレスの解消にも役立つそうですよ。
・収入がアップする
社会人の学習習慣と収入の関係について、次のような分析があります。
教育と労働の問題に詳しい矢野真和東京工業大学名誉教授は、2009年の「教育と労働と社会」という論文で、学ぶ姿勢と所得の関係について、大学時代に獲得した学習習慣が社会人になってからの学習習慣に影響し、学習習慣の有無が所得の差を生じさせていると分析しました。学生時代に学習の習慣をつけ、職場でも継続的に学んでいる人の方が所得が高かったというのです。
(引用元:NIKKEI STYLE|学び上手の決め手は「後輩力」 失敗や変化を恐れるな)太字・下線は筆者にて施した
学生の頃はいろいろなことに関心があったけれど、社会人になってからは仕事で忙しく、なかなか学ぶ意欲が湧かないという方もいらっしゃるかもしれません。ですが、学生時代に身につけた学びの習慣をそこで手放してしまうのは、とてももったいないことなのです。
学びのアンテナを広げることには、さまざまなメリットがあることがお分かりいただけたと思います。以下では、どのようにすれば学びのアンテナを広げることができるのか、そのやり方をご紹介しましょう。

「学びのアンテナ」を広げる方法1:読書
先ほどのムーギー・キム氏が視野を広げる良い方法として紹介しているのが、読書です。キム氏によれば、世界の一流は皆読書家であり、いくら忙しくても仕事の合間を縫って読書時間を確保しているのだそう。学び続け、成長を志向する姿勢があるかどうかは、読書習慣と密接に関係しているのだと言います。
読書によって学びのアンテナを広げたいなら、自分の意見や価値観とは違うことを主張している本も読むようにしましょう。自分の考え方に沿った内容の本は、確かに読んでいて心地良いものですが、そういう本ばかりを読んでいても視野は狭まる一方で広がりません。キム氏によれば、二流の人ほど“自分の偏見を助長してくれる著者の本ばかり読みたがる”そうですよ。
また、何か新たなテーマの本を読んでみようという場合にも、複数冊読むようにしましょう。人材育成コンサルタントの清水久三子氏は、本は情報源として信頼できるうえ、良書に当たれば費用対効果がかなり高いとしたうえで、次のように述べています。
たまたま見つけた本を1冊だけ読むというやり方では書籍の良さを生かしきれません。関連テーマで少なくとも5冊、時間に余裕があれば10冊は目を通したいところです。 (中略) パッと飛びついた1冊を鵜呑みにするのは危険です。多くの書籍を読むことによって、共通見解と相違見解が見えてきますので、複数冊読むことをお勧めします。
(引用元:東洋経済ONLINE|仕事のスピードが速い人の「情報収集」のコツ)太字は筆者にて施した
広い視野を持つためには、本を幅広く読むことが大事なのですね。

「学びのアンテナ」を広げる方法2:一次情報にも触れる
本によって得られる情報は「二次情報」と言い、自分で直接得た情報ではありません。新聞や雑誌、インターネットにしても同じ。こうした二次情報だけでなく、一次情報も得てみましょう。ある場所に行ってみたり人に会って話を聞いたりして、自分で直接経験して情報を手に入れるのです。清水氏は、自分が実際に経験して手に入れた一次情報からは、二次情報からは得られない、より価値のある情報や洞察が得られると伝えています。
例えば、あなたが仕事で、新しく子育て世代向けの商品を企画しているとしましょう。本や新聞・雑誌などで、子育て世代とはどういう世代であり、どんなニーズを持っていそうか調べるだけでは、誰でも考え付くようなアイデアしか浮かばないかもしれません。ですが、実際に子育てしている父親・母親たちを集めて話を聞いてみたり、子育て中の人たちと接する機会の多い保育関係の人に会ってみたりしたら、本では得られなかったような新たな視点を得られる可能性がありますよね。まさに、「目からウロコ」の情報に出合えるかもしれないのです。
またホリエモンの愛称でおなじみの堀江貴文氏も、一次情報の価値はどんどん高まってきていると伝えています。自分で足を運ぶというのは一見効率が悪そうに思えるものの、誰でも同じような情報を得られるようになった現代だからこそ、一次情報の価値が相対的に上がっていると言えるのです。

「学びのアンテナ」を広げる方法3:マインドセット
社会人の方の中には、「何でも覚えられた学生の頃とは違って、今は学びたくてもなかなか覚えられない」「忙しくて学ぶ意欲なんて湧かない」と言ったように、学びに消極的になっている人もいるのではないでしょうか?
スタンフォード大学のキャロル・ドゥエック教授によれば、学びにおいては「やればできる!」と考えることが大事なのだそう。「知性や能力は努力次第で伸ばせる」と考える人のほうが、「知性や能力は、努力したって変わらない」と考えている人よりも、成長意欲・学習意欲が高いのだとか。ドゥエック教授は、こういう考え方のことを「Growth Mindset:しなやかマインドセット」と呼びます。
例えば、「英語ができるようになれば、読める資料が増えて仕事の幅が広がりそうだ」と考えた場合。「自分は英語が苦手だから日本語で読める資料だけにしておこう」とするか「英語の勉強にチャレンジしよう」と考えるかによって、その後の視野の広がりははっきりと変わってきますよね。
また、「忙しくて、学ぶ意欲が湧かない」という場合。「仕事が忙しいのは変わらないから、当分の間勉強は無理だな」と考えるか、「スキマ時間をつなげれば1日1時間は確保できそうだな」と考えるか。どちらのタイプの人が成長していけるかは明らかです。
努力しても意味がないと考えていると、「アンテナを広げたくても広がらない」状態に陥ってしまいます。もちろん、努力さえすればいい、「やればできる」と信じさえすればいい、とは言いません。しかし、学びのアンテナを広げる可能性を少しでも高めるためにも、「しなやかマインドセット」を持つようにしてみてはいかがでしょうか。
***
視野を広げ、いままでとはちょっと違った意見を言える人になるためにすべきことは、いつまでも学び続けること。ぜひみなさんも、お伝えした方法を実践してみてください。きっと、ユニークな考え方ができるようになるはずですよ。
なお、「社会人の勉強におすすめなのはコレだ! 勉強方法&勉強場所まとめ」では、社会人がどう勉強すればよいのか具体的な情報をまとめています。こちらもご参照ください。
(参考)
ソニー生命保険株式会社|子ども脳も大人脳も「好奇心」で成長する 脳に効く習い事
NIKKEI STYLE|学び上手の決め手は「後輩力」 失敗や変化を恐れるな
DIAMOND online|一流が実践する「視野を広げる習慣」の中身
東洋経済ONLINE|読む本でバレる「一生、成長しない人」の3欠点
東洋経済ONLINE|仕事のスピードが速い人の「情報収集」のコツ
U-NOTE|とにかくアンテナが広いホリエモンの情報収集法とは?「最近は一次情報の価値が高まっているよね」

