
勉強前に「面倒くさい」と思ったことがない人はいない……と言っても、きっと過言ではないでしょう。
脳内科医の加藤俊徳氏によれば、「面倒くさい」と感じてしまうのは性格・やる気の問題ではなく、「脳との付き合い方を知らないだけ」だそう。そこでこの記事では、脳が「面倒くさい」と思う原因をふまえて、勉強前の「面倒くさい」をなくすための “10のしないこと” をご紹介します。
脳科学で見る、「面倒くさい」の3つの原因
1. 脳が覚醒していない
加藤氏によると、脳が一番面倒くさいと感じるのは「寝不足」のときなのだそう。とりわけ、朝は脳に酸素が十分に届いておらず、起きているだけで精いっぱいなため、きちんと覚醒していない状態なのだと言います。
寝不足の自覚がある、朝は勉強がはかどらないという人は、脳が覚醒していないことが原因で勉強が面倒になっているのかもしれません。
2. 脳に負担がかかりすぎている
脳に過剰な負担がかかってヘトヘトな状態になると、やる気が損なわれ、面倒くさいと感じてしまいます。
加藤氏いわく、脳が特に負担を感じるのは、不得意なことや新しいことに取り組むときだそう。たとえば、苦手分野の学習や資格試験の挑戦がこれらに当てはまるでしょう。いかに自分を追い込まずこうした勉強に取り組むかが、「面倒くさい」をなくすカギとなりそうです。
3. 脳に余裕がある
一方、脳に余裕があるときも「面倒くさい」と感じてしまうと加藤氏は説きます。余裕があるために、本来考えなくてはいけないこととは別に「面倒くさい」と考えてしまうのです。
静かな環境や試験まで時間がある場合など、脳に余裕を与える理由はさまざま。あなたの勉強法も、意外と脳に余裕をもたせすぎているのかもしれませんよ。
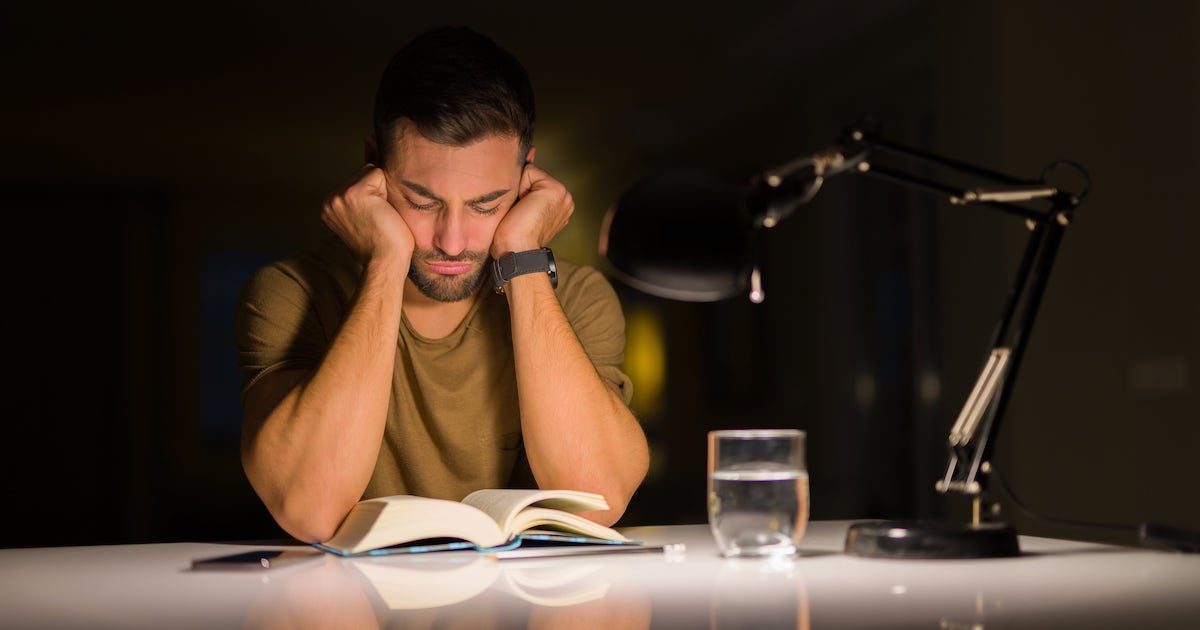
勉強前の「面倒くさい」をなくす “10のしないこと”
脳科学をふまえた、勉強前の「面倒くさい」をなくすための “10のしないこと” は次のとおり。

1. 寝る前にスマホやパソコンを見ない
寝不足が「面倒くさい」の原因なら、睡眠時間を確保して脳を覚醒させればいいと考えがちですが、それだけでは不十分。脳神経外科医の菅原道仁氏は、睡眠時間を削っていない人も、慢性的な睡眠不足に陥っている可能性があると言います。その原因は、スマートフォンやパソコンの画面から発せられる「ブルーライト」です。
ブルーライトによって脳が夜を朝だと錯覚してしまうと、メラトニンの分泌量が減り、体内時計のリズムが乱れ、不眠状態に陥ることがあるのだそう。そのため、就寝の1~2時間前にはスマートフォンやパソコンを見ないようにしましょう。
2. 勉強前にソファやベッドでゴロゴロしない
「ソファやベッドでゴロゴロしていたら、気づけば数時間も経っていた」という経験のある人は、ぜひ体を動かしてみましょう。
加藤氏によると、運動には身体を大きく動かす「粗大運動」と手先の力を調整する「巧緻(こうち)動作」があり、脳を徐々に覚醒させるには「粗大運動」が適しているのだそうです。朝の目覚めが悪いなら、起床後のウォーキングや、室内でのラジオ体操がおすすめですよ。
3. 遅れたぶんを一気に取り戻そうとしない
「勉強が遅れ気味だけど、週末にまとめて勉強すればいいや」と考えたことはありませんか? じつはこれ、菅原氏によれば自分を面倒くさい状況に追い込んでいる原因なのだそう。
菅原氏いわく、1日当たりのタスクを定量化したほうが脳への負担が少なく、「面倒くさい」がなくせるのだとか。「1日20ページずつテキストを読む」といったように、無理なく続けられる範囲で1日当たりの勉強量をあらかじめ決めておきましょう。そうすれば、遅れることも、遅れたぶんを取り戻そうと焦ることもなくなるはずです。
4. 目標達成までのプロセスを曖昧にしない
読むべきテキストや問題集の分量が多いと、「面倒くさい」と感じがちですよね。新しいことへの取り組みは、脳への負担が大きいので無理もありません。
「面倒くさい」をなくすには、どのような手順を何段階踏んでいけば物事の達成に至るのかを最初に把握しておくとよいと加藤氏は述べます。勉強のスケジュールが曖昧な人は、一度手を休めて具体的な進行や段取りを考えてみましょう。
5. ひとりで頑張らない
京都大学名誉教授の東郷雄二氏は、勉強仲間をつくったほうが途中で挫折する可能性が低くなると説きます。不得意な分野や新しい単元への挑戦といった脳へ負担がかかりがちなことでも、勉強仲間がいればやりやすくなるはず。
「苦手分野が克服できない」「試験前で不安」といった悩みを相談できる仲間ができれば、面倒くさいという気持ちもなくなるかもしれませんよ。

6. 5分頑張ってもダメなら無理して勉強しない
どれだけ環境を整えても「面倒くさい」と感じることがあるかもしれません。そんなときは思いきって休むのもひとつの手だと、心療内科医師の吉田たかよし氏は言います。
吉田氏いわく、休むかどうかを見極める目安は5分間。5分勉強するあいだに脳内で「作業興奮」が起これば、やる気が高まり、そのまま勉強を続けることができます。一方で、5分経ってもやる気が出ないときは、きっぱりと勉強を打ちきりましょう。
7. 静かな自室で勉強をしない
静かすぎる環境は脳に余裕をもたらし、かえって集中できないことがあると加藤氏は述べます。静かな自室だとなかなかやる気に火がつかない人は、適度にしゃべり声が聞こえるカフェなどで勉強するのがおすすめです。静かな場所から勉強場所を変えれば、面倒くさい気持ちがなくなるかもしれませんよ。
8. 「とりあえず」で机の前に座らない
精神科医の西多昌規氏によると、適度なプレッシャーには、やる気を高めるドーパミンの働きを強化する効果があるのだそう。
たとえば、机の前に座ったはいいもののスマートフォンでSNSをダラダラ見るなどしてしまう脳に余裕がある人は、「15分以内に章末問題を解く」といったようにタイムリミットを決めてから勉強に取り組む「タイム・プレッシャー」がおすすめですよ。
9. 受験の申し込みを先延ばしにしない
資格試験を受けようかと悩んでいる人は、思いきって申し込んでしまいましょう。これも、自分に適度なプレッシャーをかける方法のひとつだと西多氏は言います。受験費を支払う(=身銭を切る)ことには、脳の側坐核や腹側被蓋野を刺激してドーパミンの分泌を促進する働きがあるのだそう。また、「合格するぞ」という自分に対する決意表明にもなりますよ。
10. 「勉強しなくていいや」が口癖の人と付き合わない
脳にはものまね細胞と呼ばれるミラーニューロンがあり、やる気や行動力がある人のそばにいれば自然とそれに影響されますが、その逆もあると菅原氏は述べます。
たとえば、試験が間近に控えているのに「やる気が出ない」「勉強しなくていいや」と口にするような、自分に対してまったくプレッシャーをかけていない人(=脳に余裕がある人)のそばにいると、あなたも「面倒くさい」と思うようになってしまうかもしれません。自分のまわりにどんな人がいるかを、あらためて振り返ってみてください。
***
勉強前の「面倒くさい」をなくすには、睡眠や勉強の環境を整えるほか、スケジューリングがカギとなります。余裕がありすぎることが問題と考える人は、適度なプレッシャーでやる気を奮い立たせてみましょう。
(参考)
加藤俊徳 (2017),『「めんどくさい」がなくなる脳』, SBクリエイティブ.
Lidea|「めんどくさい」の正体を脳科学者に聞く
@DIME|脳科学者が指南する「めんどくさい」気分を克服する方法
ダイヤモンド・オンライン|「めんどくさい」は脳のクセだった!タイプ別“先送りグセ”を直す方法
菅原道仁 (2017),『「めんどくさい」がなくなる100の科学的な方法』, 大和書房.
東郷雄二 (2002),『独学の技術』, 筑摩書房.
西多昌規 (2016),『めんどくさくて、「なんだかやる気が出ない」がなくなる本』, SBクリエイティブ.
【ライタープロフィール】
かのえ かな
大学では西洋史を専攻。社会人の資格勉強に関心があり、自身も一般用医薬品に関わる登録販売者試験に合格した。教養を高めるための学び直しにも意欲があり、ビジネス書、歴史書など毎月20冊以上読む。豊富な執筆経験を通じて得た読書法の知識を原動力に、多読習慣を続けている。

