
得手不得手があって当然ですが、仕事においては「とにかくプレゼンが苦手……」という人も多いはずです。では、そのプレゼンの成功確率を高めるにはどうすればいいのでしょうか。
心強いアドバイスをしてくれたのは、その名もずばりの「プレゼンテーションクリエイター」である前田鎌利(まえだ・かまり)さん。大手通信会社で「プレゼンのプロ」として活躍したのちに独立し、現在は年間200社を超える企業を相手にプレゼンの研修や講演を行なっています。
構成/岩川悟 取材・文/清家茂樹 写真/石塚雅人
若き日に犯してしまった大きな失敗
いまでこそプレゼンのスペシャリストなどと呼ばれますが、僕もたくさんの失敗をしてきました。
まだ若かった頃の僕がはじめてプレゼン資料を作成することになったときのことです。「PowerPoint」っていろいろな効果を使えるので、見よう見まねでつくっているうちに楽しくなっちゃって、花火が打ち上がる音やミサイルの発射音をいっぱい詰め込んだのです。
その資料を使ってプレゼンをしたのは、当時所属していた会社の執行役員。もちろん、事前に資料のチェックはされていたとは思うのですが、その人は文句ひとついわずに僕がつくった資料を使ってプレゼンをしてくれました。そのプレゼンの聴衆は2,000人ほどでした。そして、彼らの前で花火やミサイルの効果音が鳴り響く……。それを客観的に見たとき、「なんて申し訳ないことをしてしまったんだ」と思わざるを得ませんでした。
なにが失敗だったかというと、そのときの僕は「ゴールイメージ」をまったく持っていなかったということです。ただ自分が「いいな」と思うものではなく、対象である誰かに伝えるべきことを的確に伝えられるものでなければならない――。その重要性を目の当たりにしたわけです。そのことに気づかせてくれたその執行役員だった人には、いまでも頭が上がりませんね(苦笑)。

手っ取り早い上達法は「うまい人から学ぶ」こと
その後、僕はさまざまなかたちでプレゼンの腕を磨くことになるのですが、なかでもいちばん手っ取り早い方法は「うまい人から学ぶ」ということでした。社内でのプレゼンでいえば、あたりまえのことですが、決裁を取れるプレゼンと取れないプレゼンがあります。だとしたら、決裁を取れるものに寄せていけばいい。
それらのプレゼンにどういう共通点があるかというと、ひとつは「決裁者からの質問がない、あるいは少ない」ことです。プレゼン後になんの質疑もなく「これ、いいね」といわれるケースですね。
決裁者の立場にある人は、多くは多忙で決裁にたくさんの時間をかけたくないものです。そこで質問することもなく決裁ができるということは、決裁者が意思決定をするために必要な情報がきちんと網羅されているということなのです。
かといって、たくさんの情報を詰め込めばいいというものでもありません。決裁者にとって無駄が多いボリュームの情報であれば、確認のために時間を取られてしまうからです。
そのためには、プレゼンの対象である人物のタイプを分析することも大切です。1枚の資料でシンプルに表現して概要を説明すれば理解してくれる人、あるいは資料が多いほど内容の信頼度が高いと感じる人。同じ資料でプレゼンをしても、相手が違えば、決裁が取れる場合とそうでない場合があります。
プレゼンの成功確率を高めるために、自分がプレゼンをするときはもちろん、第三者がその人に対してプレゼンをするとき、あるいは会議中でも質問をするなどして相手の受け答えのサンプルを集める。そうしてプレゼンのシミュレーションを重ねながら、決裁者の「癖」を見抜くことが大切です。

また、質疑応答での自身の回答の仕方も大きなポイントです。
質問されたことに対するデータやエビデンスがないというとき、なんとかごまかそうとする人も多いものです。決裁者の質問に対して、「いや、それも大事なのですが、じつは……」と別の話題に変えてはぐらかそうとするようなパターンです。自分が決裁者であれば、そんな人間の提案を信頼できるはずもないでしょう。
信頼を勝ち取るために必要なのは、「ないものはない」といえる勇気です。「いまは手元にないので、のちほどお持ちします」と答える。はぐらかすよりよほど誠実な対応といえます。
そういうふうにデータなどが足りなくてその場では決裁できないというケースでも、ただ撤退するのではなく、やれることがあります。「足りないデータはのちほどお持ちしますが、全体としては進める方向でいいですか?」というひとことを伝えることです。そういうふうに合意を勝ち取ろうとするアクションがあるかどうかが大切で、それだけでもプレゼンの対象者が受ける印象は大きく変わってくるはずです。
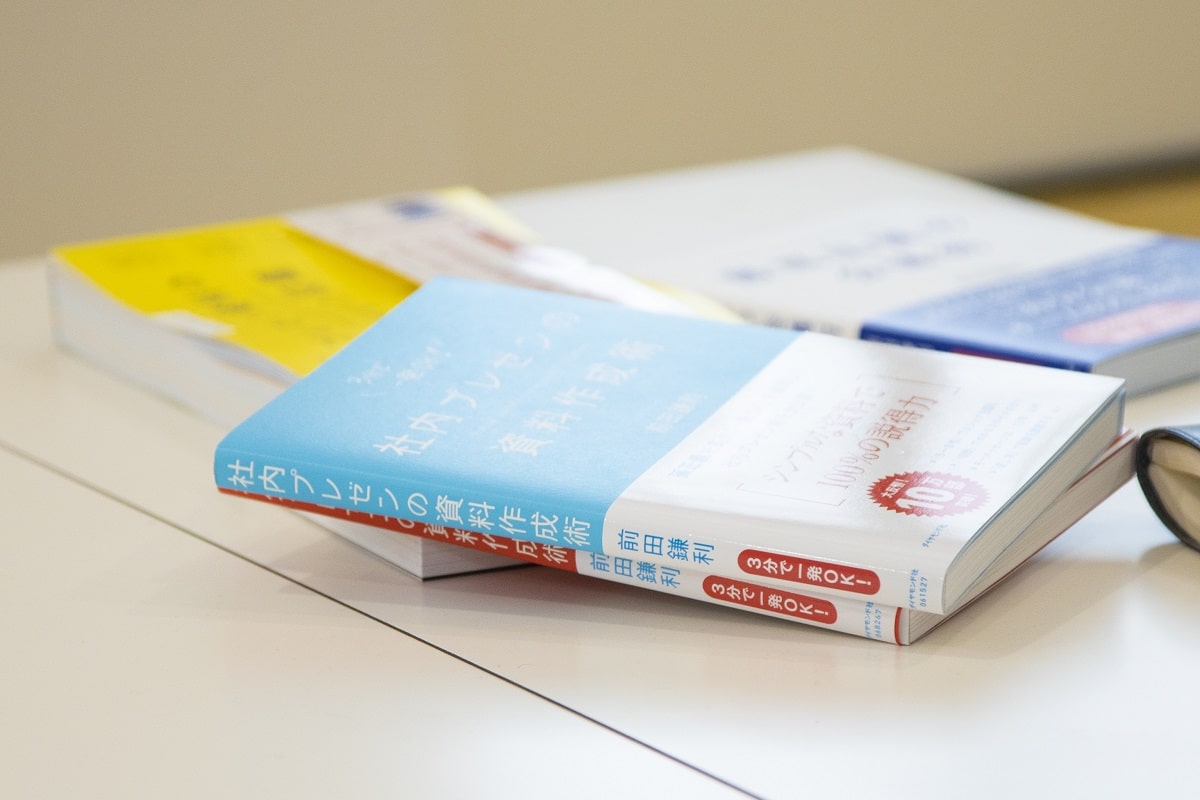
ありがちなNGプレゼンの3タイプ
そういうふうに、「うまい人から学ぶ」ことを続けているうち、悪いプレゼンの特徴も見えてきました。
よく見られるケースとしては、「文字が多い」というもの。もちろん、企業文化もさまざまですから、多くの情報を詰め込んだほうがいいとされる会社もあります。でも、とくに日本人の決裁者は「だから結論はなんだ?」とすぐにゴールを求めがちですから、そういわせないくらいシンプルな資料にして短い時間で伝えることを基本的には心がけるべきです。
また、「文字が多い」ことに近いことですが、「脱線しやすい」プレゼン資料もNGといえます。これは、1枚のスライドのなかにたくさんのグラフを埋め込んでいるといったものです。
プレゼンというものは、5分や10分など限られた時間内で行なうものですよね。5分なら5分で話すシナリオを考え、話し切れなければなりません。でも、グラフなど脱線の材料が多いと、それに引っかかった聴衆から質問が始まってしまいます。その回答に追われるうち、本当に伝えたいことを伝えられないまま時間切れ……ということになるのです。
そして、3つ目は「『最後まで自分がやり切る』という熱意がこもっていない」ものです。会社に帰属しているビジネスパーソンが、やりたい仕事をやらせてもらっているというケースは本当に少ないはずです。でも、そういう「やりたくはないけどやらなければいけない」仕事に対しても、本人が「それをやり切ることが会社を通じて世の中を変えていくなにかのきっかけになる」というふうに考え「やるべきだ」と腹落ちできているかが重要なのです。
それができていない人間のプレゼンには、どこかに「やらされ感」が出てしまう。そういったものは、プレゼンを見ている聴衆に伝わってくるものです。もちろん、そんなプレゼンの結果はいいものにはならないでしょう。そういう意味では、プレゼンの成功確率を高めていくためには、最終的には「仕事への向き合い方」こそが重要になってくるのかもしれませんね。

【前田鎌利さん ほかのインタビュー記事はこちら】
なぜか聴き続けたくなるプレゼンには「数字」と「○○」が入っている。
最高のリーダーが “たった2分” で決断できるカラクリ。「自分の軸」がないと何も決まらない。
【プロフィール】
前田鎌利(まえだ・かまり)
1973年5月5日生まれ、福井県出身。プレゼンテーションクリエイター、書家。株式会社固-KATAMARI-代表取締役。一般社団法人継未-TUGUMI-代表理事。一般社団法人プレゼンテーション協会代表理事。i専門職大学客員教員予定。サイバー大学客員講師。東京学芸大学卒業後、光通信入社。2000年にジェイフォンに転職して以降も、ボーダフォン、ソフトバンクモバイル(現ソフトバンク)と計17年にわたって通信事業に従事。営業プレゼンはもちろん、代理店向け営業方針説明会、経営戦略部門にて中長期計画の策定、渉外部門にて意見書の作成など幅広く担当。2010年にソフトバンクグループの後継者育成機関であるソフトバンクアカデミア第1期生に選考され、事業プレゼンにて第1位を獲得。孫正義社長に直接プレゼンをして数多くの事業提案を承認された他、孫社長が行うプレゼンの資料作成にも参画した。ソフトバンク社内におけるプレゼンの認定講師として活躍したのち、2013年12月にソフトバンクを退社し独立。ソフトバンク、ヤフーなどIT関連企業の他、年間200社を超える企業においてプレゼン研修や講演、資料作成、コンサルティングなどを行っている。著書に『最高のリーダーは2分で決める』(SBクリエイティブ)、『最高品質の会議術』(ダイヤモンド社)、『社内プレゼンの資料作成術』(ダイヤモンド社)、『社外プレゼンの資料作成術』(ダイヤモンド社)、『プレゼンの資料のデザイン図鑑』(ダイヤモンド社)がある。
【ライタープロフィール】
清家茂樹(せいけ・しげき)
1975年生まれ、愛媛県出身。出版社勤務を経て2012年に独立し、編集プロダクション・株式会社ESSを設立。ジャンルを問わずさまざまな雑誌・書籍の編集に携わる。


