
読解力は、仕事においても必須の能力。大人のみなさんは、ご自身の読解力に自信はありますか? 小学生の頃から国語の授業などで「読解力を身につけましょう」と言われてきたと思いますが、いざ読解力が身についているのかと問われたら、不安になってしまいますよね。
また、読解力を上げたいと思っても、どのような行動をすればいいのかよくわからないという方も多いはずです。読解力を高めるには何をすればよいのでしょうか。
今回は、読解力が必要な理由や、読解力を鍛える方法を考えていきます。
読解力とは
そもそも、読解力とはどのような意味なのでしょうか。OECD(経済協力開発機構)は、15歳児の読解力、数学的リテラシー、科学的リテラシーを調査する 「PISA(Programme for International Student Assessment)」を実施しており、そのなかで読解力を次のように定義しています。
自らの目標を達成し、自らの知識と可能性を発展させ、社会に参加するために、テキストを理解し、利用し、評価し、熟考し、これに取り組むこと。<測定する能力>「①情報を探し出す」「②理解する」「③評価し、熟考する」
(引用元:国立教育政策研究所|OECD生徒の学習到達度調査2022年調査(PISA2022)のポイント※太字は編集部が施した。)
PISAにおいては、テキストから情報を読み取るだけでなく、テキストに基づいて自分の意見を論じる能力が求められます。また、文章読解力のみならず、図・グラフ・表などを読解する力が測られるのも特徴です。
つまり、読解力とは、以下の能力を指しているといえるでしょう。
- テキストを読み、正しく理解できる力
- テキストの意味を熟考できる力
- テキストに基づいて自分の意見を論じられる力

日本人は読解力がない?
昨今、「読解力がない人が増えている」「現代人の語彙力が低下している」と耳にすることが多くありますよね。しかし、読解力は本当に低下しているのでしょうか。
2022年のPISAにおいて、日本の読解力の平均得点はOECD加盟国中2位でした。順位だけ見ればなかなかの成績を収めているように思えます。
しかし結果を細かく見てみると、読解力の5段階のレベルのうち、レベル1(「最小限の複雑な課題をこなすことができる」)以下の生徒が13.8%と、最小限の読解力しか持っていない子どももある程度いることがわかります。(参考元:国立教育政策研究所|OECD生徒の学習到達度調査(PISA)の調査結果、文部科学省|1 PISA調査における読解力の定義,特徴等よりまとめた)
PISAの結果だけをもって日本人の読解力が低下しているとは言い切れませんが、読解力に不安のある子が少なくないというのも事実。そして大人のみなさんのなかでも、小中学生の頃から読解力に自信がないままここまで来てしまったという方もいるでしょう。もしくは、「この人は読解力がないな」と感じる人がまわりにいるかもしれません。読解力の低下はなぜ起こってしまうのでしょうか。
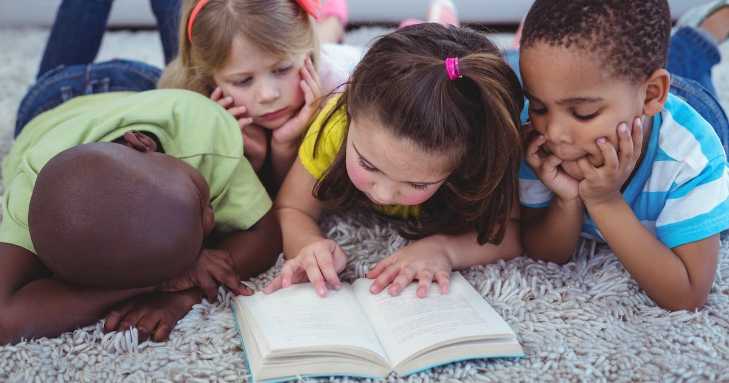
読解力が低くなる原因
ここからは、読解力が低下してしまう原因を考えていきます。
読書量の減少
読解力のトレーニングは、まず文章に触れないことには始まりません。本は文字に触れられる身近なツールですが、「一番最近読書をしたのはいつだったかな……」という方も多いのではないでしょうか。時間があるとついついスマートフォンやゲームで遊んでしまっていませんか?
言語学者で静岡県立大学教授の澤崎宏一氏が大学生を対象に行なった研究では、「子どもの頃から現在までの総読書量が文章理解力と関係していることを明らかにして」います。(カギカッコ内引用元:ダイヤモンドオンライン|「本を読む子は頭がいい」「家にたくさん本がある子は頭がいい」は本当?※太字は編集部が施した)
普段の生活で長い文章を読む機会は少ないもの。意識的に読書をしていないと、読解力以前に、ある程度の量の文章を読むことすらできないという事態に陥ってしまう可能性があります。
SNSの利用
SNSに投稿される文章は短くて読みやすく、さまざまな情報を得るのに非常に便利です。一方で、SNSの文章は短く、文脈がないことも多いので、必ずしも読解力は求められません。
また、発信の手段としてSNSを使う場合でも、自分の意見をひとりごとのようにポンポン投稿することができます。
多摩大学客員教授の樋口裕一氏は、SNSでのコミュニケーションについて、以下のように述べています。
SNS、チャットツールなどの会話はほとんど仲間内です。共通の価値観、共通の体験があり、一言でわかり合える間柄です。こうした仲間内でのコミュニケーションが多いため、仲間以外の人と会話が出来ない、話が通じない人が多くいます
(引用元:FNNプライムオンライン|メールやSNSなど“文字”の会話が増えた今だからこそ必要な「読解力」の鍛え方)
SNSで近しい関係の人としかつながっていない場合、文章の意味を考えたり推敲したりする必要性は下がります。SNSの文章に触れていても、読解力はなかなか上がりません。
読解力をつけるべき理由
「読解力があるに超したことはないけれど、インターネットで調べればなんでもわかるし……」と読解力の必要性に懐疑的な方もいるかもしれません。ChatGPTなども気軽に使えるようになり、わざわざ自分で読んで理解しなくても問題ないと感じるのも無理はないでしょう。しかし、読解力は文章を読む以外の場面でも発揮される能力なのです。
国語教育者の福嶋隆史氏は、読解力を「人との会話においてその意図を推し量る力」だと言います。(カギカッコ内引用元:EL BORDE|【国語力特集:前編】仕事ができる人は読解力も高かった! 仕事力と国語力の関係は?)
ビジネスシーンでは、人と直接会話をする機会が頻繁にあります。読解力があれば、会話の端々に散りばめられている相手の気持ちを読み取ることができるでしょう。「なぜこういう言葉を使ったのかな」「いまの言い回しに隠されている真意はなんだろう」と考えるときにも読解力は役に立ちます。
読解力を味方につければ、ビジネスを有利に進めることができるかもしれません。逆に読解力がなければ、せっかくのチャンスを逃してしまうことにもつながりかねません。
読解力テスト
読解力低下という問題に危機感を覚えてきた方も多いのではないでしょうか。では、みなさんの読解力はどうでしょう? 大人も誤答が多かった読解力クイズをご紹介するので、チャレンジしてみてください。
アミラーゼという酵素はグルコースがつながってできたデンプンを分解するが、同じグルコースからできていても、形が違うセルロースは分解できない。
この文脈において、以下の文中の空欄にあてはまる最も適当なものを選択肢のうちから1つ選びなさい。
セルロースは( )と形が違う。
(1)デンプン (2)アミラーゼ (3)グルコース (4)酵素
(引用元:Yahoo!ニュース|大事なのは「読む」力だ!~4万人の読解力テストで判明した問題を新井紀子・国立情報学研究所教授に聞く)
正解は(1)の「デンプン」です。しかし、国立情報学研究所社会共有知研究センター長の新井紀子氏によると、新聞社の論説委員や経済産業省の官僚でも「グルコース」と答えた人がいたのだそう。
読者のみなさんはいかがでしたか? 間違えてしまった人は、もう一度読み、なぜ(1)が正解になるのか考えてみてください。

読解力を鍛える方法
読解力の低い大人が読解力をつけるには、どうすればいいのでしょうか。読解力をつける方法をご紹介します。
読書
上で、読書量が減ったことが読解力低下の一因である可能性に触れました。裏を返せば、読書をすることで読解力のアップが期待できるということです。
脳科学を研究している東北大学教授の川島隆太氏らは以下の研究を行ないました。
- 5歳から18歳の子どもや若者を対象に、「あなたは、読書(漫画や絵本を除く)の習慣はついているほうだと思いますか」と尋ね、その回答を数値化。同時にMRIで脳の状態も測定する。
- 3年後、彼ら・彼女らの脳の形態の変化を調べた。
研究の結果、読書習慣と、神経繊維の発達や言語性知能の向上とのあいだには大きな関係があることがわかったそうです。(参考元:ダイヤモンドオンライン|「本を読む子は頭がいい」「家にたくさん本がある子は頭がいい」は本当?「よりまとめた)
つまり、読書習慣のある子は脳神経や言語能力が発達していたということ。読書が読解力の向上に寄与してくれることを示唆しています。
いままで読書の習慣がなかった方は、短い小説やエッセーなど読みやすい本から入るのがいいでしょう。最初から新書や専門書のような難しい本を読み始めると、挫折してしまいやすいからです。
「1日1章読もう」「帰りの電車はスマホをいじらず読書をしよう」など継続しやすい目標を立てると、習慣にしやすいですよ。
要約
読解力を向上させるには、要約の練習も有効です。本や長い文章を要約するには、単語の意味や著者の主張を正しく理解し、端的に言い換えることが求められます。そのため、要約の練習を繰り返すことによって、読解力が養われるのです。
大学受験塾やカルチャースクールで国語講師を務める吉田裕子氏いわく、要約の教材としては新聞がおすすめなのだそう。記事の内容を100文字前後で要約するのが効果的なのだとか。新聞記事を要約する際は、次の2点に着目するべきなのだそうです。
- 話題:何について述べているのか
- 結論:結局どのようなことを言いたいのか
新聞記事のなかでも、リード文(記事冒頭の要約)がある記事や、社説がおすすめとのこと。リード文つきの記事は、要約文を作成したあとでリード文を見れば、答え合わせができます。社説の場合、ひとつの記事がひとつの主張で構成されているので、要約に適しているのです。(参考元:東洋経済オンライン|読み書きを鍛えるのに「要約」が最強なワケよりまとめた)
実際に100字でまとめようとすると、内容をかなり凝縮しなければならないことがわかるはずです。どこが最も重要で、どこが削るべき部分なのかを考えながら要約を重ねることで読解力が養われていきます。最初から完璧にまとめる必要はありません。まずは手を動かしてみてください。

音読
音読は、「飛ばし読み」という癖を矯正するのに有効なのだそう。飛ばし読みとは、文を冒頭から丁寧に追っていくのではなく、一部の単語だけを拾いながら読んでいく方法です。
重要なキーワードを適切に拾っていけば効率よく読書できますが、読解力の低い人は、不適切な飛ばし読みをやってしまっています。重要な単語を見落としたり、単語と単語の関係を自分で勝手に作り上げたりしているのです。このような「悪い飛ばし読み」が癖になっていると、文章の意味を正しく理解できません。
なので、読解力が低いと自覚している人は、飛ばし読みの癖を直すため、音読をしてみましょう。音読なら、必然的に一言一句を意識することになります。(参考元:齋藤孝 (2002),『読書力』, 岩波文庫.よりまとめた)
アプリ
「いきなり読書や要約をするのはハードルが高い」と感じる方は、漢字や語彙のトレーニングができるアプリから始めるのも手です。最初は小中学生向けのアプリを使ってもいいでしょう。
心理学博士でMP人間科学研究所代表の榎本博明氏は「読解力があればどんどん語彙を増やすことができ、語彙が豊富なことが読解力のさらなる向上につながるといった好循環がみられる」と言います。(カギカッコ引用元:ダイヤモンドオンライン|言語能力が低い子は成長しても読解力が低いという、これだけの研究結果)
わからない言葉が多いと文章を読むのが苦になってしまうこともありますが、語彙を増やしていくことで文章の意味が理解できるようになっていきます。文章の意味を理解するとさらに語彙が増え、語彙が増えるとさらに読解を楽しめるようになるという正のスパイラルを作り出すことができるでしょう。
***
読解力は、これからの時代に必須の能力。自身の読解力に危機感を抱いているのであれば、今日からトレーニングを始めてみてはいかがでしょうか。
国立教育政策研究所|OECD生徒の学習到達度調査2022年調査(PISA2022)のポイント
国立教育政策研究所|OECD生徒の学習到達度調査(PISA)の調査結果
文部科学省|1 PISA調査における読解力の定義,特徴等
ダイヤモンド・オンライン|「本を読む子は頭がいい」「家にたくさん本がある子は頭がいい」は本当?
FNNプライムオンライン|メールやSNSなど“文字”の会話が増えた今だからこそ必要な「読解力」の鍛え方
EL BORDE|【国語力特集:前編】仕事ができる人は読解力も高かった! 仕事力と国語力の関係は?
Yahoo!ニュース|大事なのは「読む」力だ!~4万人の読解力テストで判明した問題を新井紀子・国立情報学研究所教授に聞く
東洋経済オンライン|読み書きを鍛えるのに「要約」が最強なワケ
齋藤孝 (2002),『読書力』, 岩波文庫.
ダイヤモンド・オンライン|言語能力が低い子は成長しても読解力が低いという、これだけの研究結果
STUDY HACKER 編集部
「STUDY HACKER」は、これからの学びを考える、勉強法のハッキングメディアです。「STUDY SMART」をコンセプトに、2014年のサイトオープン以後、効率的な勉強法 / 記憶に残るノート術 / 脳科学に基づく学習テクニック / 身になる読書術 / 文章術 / 思考法など、勉強・仕事に必要な知識やスキルをより合理的に身につけるためのヒントを、多数紹介しています。運営は、英語パーソナルジム「StudyHacker ENGLISH COMPANY」を手がける株式会社スタディーハッカー。

