
今回のテーマは、勉強ノートのまとめ方。見やすいノートをつくる「10のルール」と、フォーマットの具体例を紹介します。
- ノートの書き方・まとめ方がよくわからない
- 学んだことをうまくノートに整理できない
- ノートを読み返しても理解できないことが多い
当てはまる方は、ぜひ本記事を一読し、勉強ノートの基本的なまとめ方をマスターしてください。
優れた勉強ノートの条件とは
勉強ノートのまとめ方の良し悪しは、知識の再現性に係っています。読み返したときに理解しやすいかどうか、記憶がよみがえるかどうかです。
講座の内容をノートに書き留め、数日~数ヵ月後に見返したとき、学んだことがありありと思い出せるようでなければいけません。きれいな文字で書き、色分けにこだわったとしても、読み返してパッと理解できないのは「ダメなノート」なのです。この「再現性」という重要な条件を念頭に置き、勉強ノートのまとめ方を学んでいきましょう。

勉強ノートをまとめる「10のルール」
勉強ノートのまとめ方としては、これからご紹介する「10のルール」を参考にしてください。
フォーマットを決める
常に一定のフォーマットでノートを書くと、「どこに何を書くべきか」「どう書くべきか」という迷いがなくなり、スピーディーかつきれいにまとめることができます。どの場所に何が書いてあるかひとめで判断できるため、見直しにも好都合です。フォーマットの具体例は、記事の後半で紹介しています。
見出しをつける
内容ごとに見出しをつけると、知識が体系的に整理され、見やすいノートになります。ページの一番上には全体のテーマを示す大見出しをつけ、その中身には小見出しを設けましょう。「IoT」についてまとめるなら、以下のようになります。
- 大見出し:IoT
- 小見出し1:IoTとは
- 小見出し2:IoTで実現できること
- 小見出し3:IoTの4要素
1ページにつき1テーマ
「IoT」をまとめたページには、ほかのテーマについて書いてはいけません。つまり、1ページに大見出しは1個だけです。
「スペースが余ったから『ICT』の話も入れておこう」はNG。まだ書けるスペースがあっても、テーマが変わったなら次のページに移りましょう。
「箇条書き」が基本
ノートは簡潔に、箇条書きしましょう。「~は~である。なぜなら~だからだ」と文章で書くより、要点がハッキリします。以下に挙げたふたつの例を比べてみてください。
IoTとは「Internet of Things」の頭文字で、「モノのインターネット」と直訳される概念である。あらゆるモノをインターネットにつないで便利にする技術を指し、具体例としては「スマート家電」「自動運転車」「スマートスピーカー」などが挙げられる。
- IoTとは「Internet of Things」の頭文字
- 直訳は「モノのインターネット」
- モノをインターネットにつなぎ、便利にする技術
- 具体例は「スマート家電」「自動運転車」「スマートスピーカー」など
箇条書きのほうが読みやすく、要点をつかみやすいですよね。
箇条書きにもコツがあります。ノートのとり方に関する著書をもつ塾講師・小澤淳氏によると、「1文につき1テーマ」を意識することが大事だそう。
- IoTとは「Internet of Things」の頭文字で、「モノのインターネット」と直訳される
これでは長いので、テーマごとに分割しましょう。
- IoTとは「Internet of Things」の頭文字
- 直訳は「モノのインターネット」
このように区切ることで、読みやすい箇条書きになります。
ペンは3色まで
ペンを使い分けるとしても、3色までに抑えましょう。たくさんの色を使うと、本当に強調したい部分が目立たなくなってしまいます。一般的な3色ボールペンの「赤」「青」「黒」のように、必要最低限の色だけ使いましょう。
そして、どの色をどんなときに使うかというルールを必ず決めます。以下の例は、前出の小澤氏による色分けルールです。
- 赤:重要項目
- 青:見出し
- 黒:それ以外
色分けルールを守れば、「赤で書かれているから、これは重要だな」「青で書かれているから見出しだな」とひとめでわかります。気分によって色の使い方を変えるのはNGです。
記号・略語を使う
「★」や「ex」のような記号・略語を駆使しましょう。すばやく書け、スペースを節約できるだけでなく、情報の意味や位置づけをわかりやすく表現できるためです。
たとえば、「★モノのインターネット」とマークを使うと、目立つので重要性が強調されますよね。【ここが重要!】と文字で表現することもできますが、書くのに時間がかかりますし、ほかの文字に埋もれてしまいます。
以下は、ノートに使える記号・略語の例です。参考にしてみてください。
★ 重要
ex たとえば
cf ちなみに
? 疑問
∵ なぜならば
∴ それゆえに
→ 因果関係・時系列
⇔ 反対・対立
テ テストに出る
◆ 見出し
丸写しをしない
ノートをとるうえでの鉄則は、講師の言葉やテキストの文章を丸写ししないことです。講師の言葉やテキストの文章といった「他人の言葉」には、なじみのない語彙や言い回しが含まれています。それを写しても、「読み返したとき理解できないノート」が生まれるだけです。
経営コンサルタントの高橋政史氏は、「インプット後、1秒待ってから書く」というノート習慣を推奨しています。講師の話を聞いたら、1秒かけて自分の言葉に変えてから書く。板書やテキストの文章も、1秒間かけてかみ砕いてからノートにまとめる。こうした「咀嚼(そしゃく)の1秒」を意識するだけで、ノートの仕上がりや学習の質が大きく変わります。
◆自分の言葉に置き換える例
「物体に通信機能を搭載する」
↓
「モノに通信機能をもたせる」
適度な余白を残す
復習しているときなど、ノートに情報を書き足したくなりますよね。そのため、コメントや補足、修正などを加えられるスペースを空けておきましょう。
見栄えの観点でも、余白は大切です。文字がびっしり書かれていると、情報の切れめがわかりにくく、読みづらいですからね。
コピーを活用する
自分で書くのが困難だったり、手間がかかりすぎたりする情報については、コピー機を活用しましょう。
- 地図
- 写真
- 組織図
- グラフ
- 表データ
- 年表
- 法律の条文
……などは、手書きでせっせと写すより、コピーして貼りつけるほうが楽です。「ノートは手書きすべき」という固定観念を捨て、必要なら迷わずコピー機を使いましょう。
用途で使い分ける
内容だけでなく、用途でもノートを使い分けましょう。「東京大学医学部家庭教師研究会」代表の吉永賢一氏は、以下のような使い分けを推奨しています。
- わかるノート:
知識を体系的にまとめる。授業やテキストの内容を整理し、理解する - 覚えるノート:
知識の覚え方を書く。語呂合わせを考えたりイラストを描いたりと、頭に入りやすいよう加工する - 慣れるノート:
知識の使い方に慣れる。問題の解法・解答をまとめ、試験に備える
- 「わかるノート」で整理
- 「覚えるノート」で定着
- 「慣れるノート」で実践
……と学習フェーズごとにノートを使い分ければ、知識が効率よく身につきます。気になったことを書き留める「疑問ノート」や、ミスした問題だけまとめる「間違いノート」など、自分なりに勉強ノートの使い方・まとめ方を考えるのもいいですね。
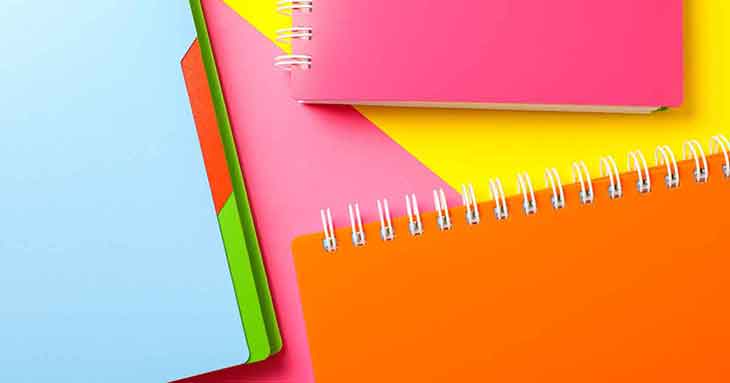
勉強ノートのフォーマット4選
勉強ノートのまとめ方として、4つの具体例をご紹介します。ピンときたものを使ってみてください。
コーネル式
米コーネル大学の教育学部教授だった、故ウォルター・パウク氏による「コーネル式」では、ノートを3つに分割します。
- 見出し欄:内容欄につながる問い
- 内容欄:講座やテキストで学んだ内容
- 要約欄:ページの簡潔な要約

左側の見出し欄には、「IoTとは?」「IoTで何が実現できる?」などの問いが書かれています。それに対する答えが、内容欄にまとめた情報です。
【見出し欄】
IoTとは?
【内容欄】
- 「Internet of Things」の頭文字
- モノをインターネットにつなぎ、便利にする技術
見出し欄により、全体像や要点を見渡せるのがメリットです。「見出し欄だけを見て内容欄を思い出す」という復習もできます。
5分割
前出の小澤氏は、1ページを5分割するまとめ方を紹介しています。「コーネル式」に、項目欄・メモ欄・感想欄が加わったかたちです。
- 項目欄:見出し番号
- 内容欄:講座・テキストの内容
- メモ欄:補足や余談、気づいたこと
- 要約欄:簡潔な要約
- 感想欄:学習した感想

項目欄には、内容欄における見出しの通し番号を書きます。上の図では、番号と見出しが以下のように対応していて、情報の区切りがわかりやすいですね。
- IoTとは
- IoTで実現できること
- IoTの4要素
メモ欄は、補足情報や脱線話、試験用のアドバイス、自分なりの気づきなど、自由に書くスペースです。上の図では、IoTの直訳および具体例をメモしています。
感想欄では、学習内容を振り返って感じたことを書きます。感情がともなうことで、知識が強く印象に残るのです。
見開き3分割
前出の高橋氏は、ノートの見開きを3分割する方法をすすめています。
- 内容欄:講座やテキストの内容
- 解説欄:内容欄の解説や補足
- 要約欄 :全体の要約

左→中央→右の順番で記入するのが特徴です。左端の内容欄には、学んだことをまとめましょう。そして、中央の解説欄では、内容欄の情報に説明・補足を加えます。上の図では、内容欄のキーワードから矢印を伸ばしました。自分なりの気づきや考えも記入してください。最後に、全体の要約を右端に記入したら完成です。左から順に記入していくだけで、見やすいノートが出来上がります。
見開き2分割
すばやくノートをとりたいときは、「見開き2分割」がおすすめ。見開きの左ページに走り書きをし、右ページにあらためて清書します。

左ページには、講座中に走り書きした情報が無秩序に並んでいます。これをきれいに書き直したのが右ページです。情報の順番が整い、見出しが加えられて、見やすくなりました。
会議や打ち合わせの最中にすばやくメモをとりたいときも、この「見開き2分割」が役立ちます。右ページに清書する際は、すでに紹介した「コーネル式」や「5分割」のレイアウトでもいいでしょう。
以上、4種類のフォーマットをご紹介しましたが、そのまま使わなくてもかまいません。変形させたり混ぜ合わせたりし、使いやすいかたちに変えるのもOKです。たとえば……
- 「3分割」に「コーネル式」の見出し欄を加える
- 「5分割」の感想欄を削る
自分で決めたまとめ方に従い、いつも同じフォーマットで勉強ノートを書くことを徹底しましょう。
***
ご紹介した「10のルール」と「4つのフォーマット」を参考に、自分に合ったまとめ方を研究してみてください。
小澤淳 監(2012)『中学生の成績が上がる ! 教科別「ノートの取り方」 最強のポイント55』, メイツ出版.
高橋政史(2014), 『頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか?』, かんき出版.
吉永賢一(2015), 『東大家庭教師の結果が出るノート術』, あさ出版.
Learning Strategies Center|The Cornell Note Taking System
佐藤舜
大学で哲学を専攻し、人文科学系の読書経験が豊富。特に心理学や脳科学分野での執筆を得意としており、200本以上の執筆実績をもつ。幅広いリサーチ経験から記憶術・文章術のノウハウを獲得。「読者の知的好奇心を刺激できるライター」をモットーに、教養を広げるよう努めている。

