
編集部より
「アンラッキー君と博士の教室」では、日常でつい感じてしまう「運の悪さ」や「うまくいかない感覚」を、科学の視点から読み解いていきます。主人公は、何かとうまくいかないぬいぐるみのアンラッキー君。そして彼を温かく見守る認知科学の専門家、バイアス博士です。
大事なプレゼンで、緊張のあまり失敗
朝9時、重要なプレゼンテーションが始まります。
壇上に立つアンラッキー君は、震える手でスライドを切り替えながら話し始めました。

次の瞬間、緊張のあまり頭が真っ白に。なにを話せばいいのかわからなくなってしまいました。

会議室の空気が重くなるのを感じるアンラッキー君。冷や汗が止まりません。 なんとかもち直してプレゼンを終えたものの、アンラッキー君は自分の席に戻ると机に突っ伏してしまいました。

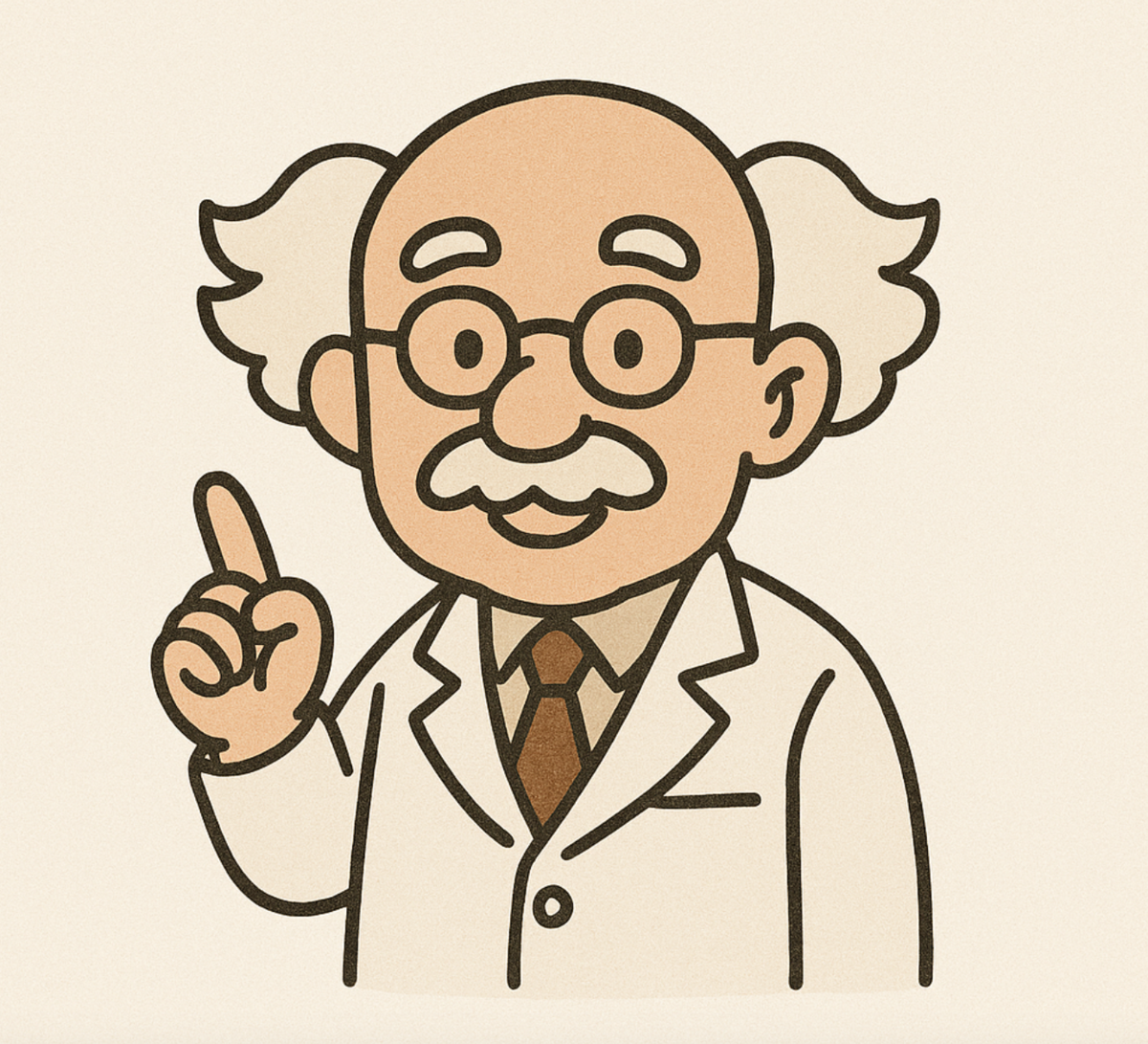
博士がアンラッキー君にコーヒーを手渡しながら微笑みます。
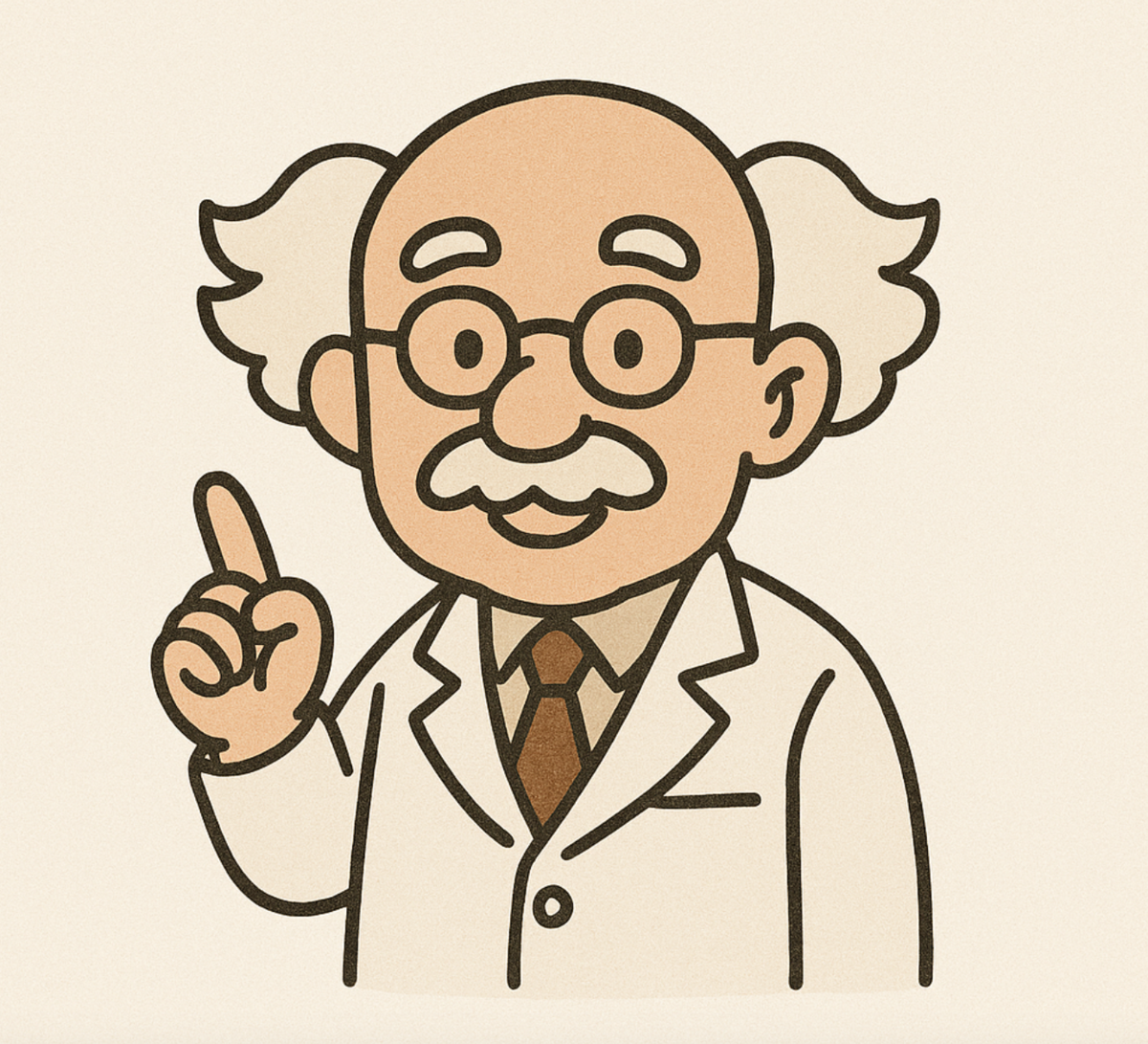

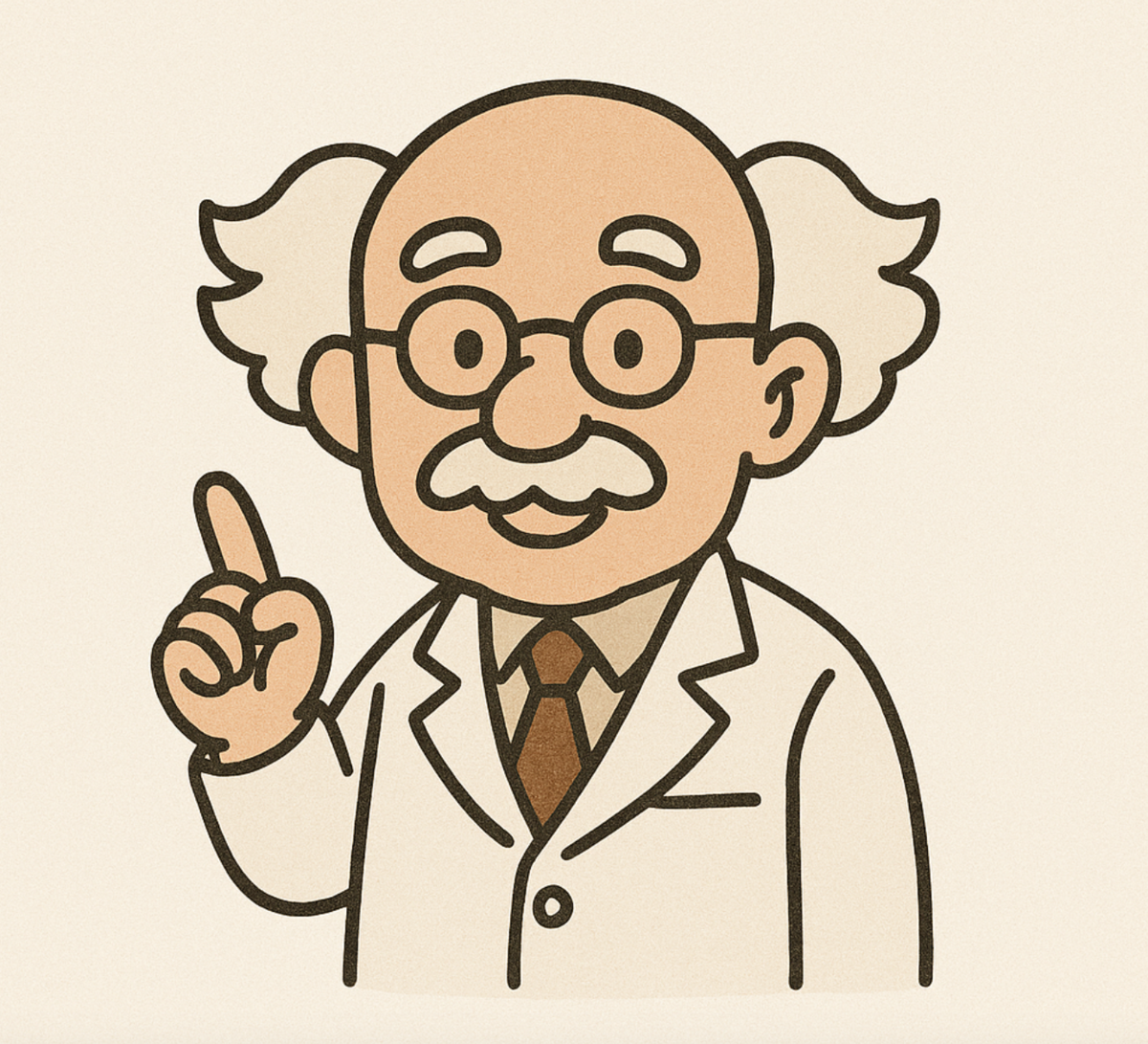
『破局思考』に陥ると、脳ではどんなことが起きるの?
博士はゆっくり話し始めました。
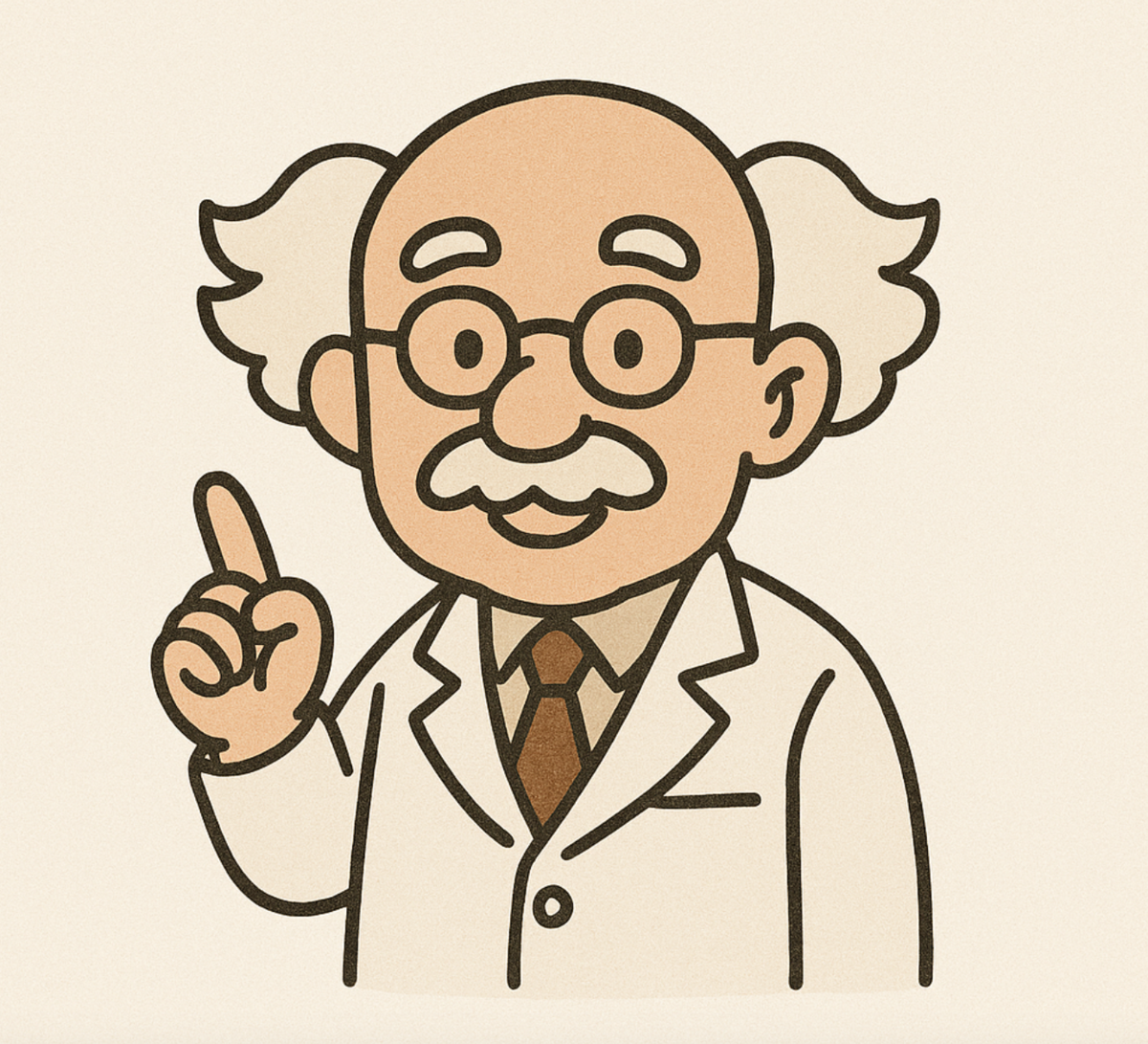

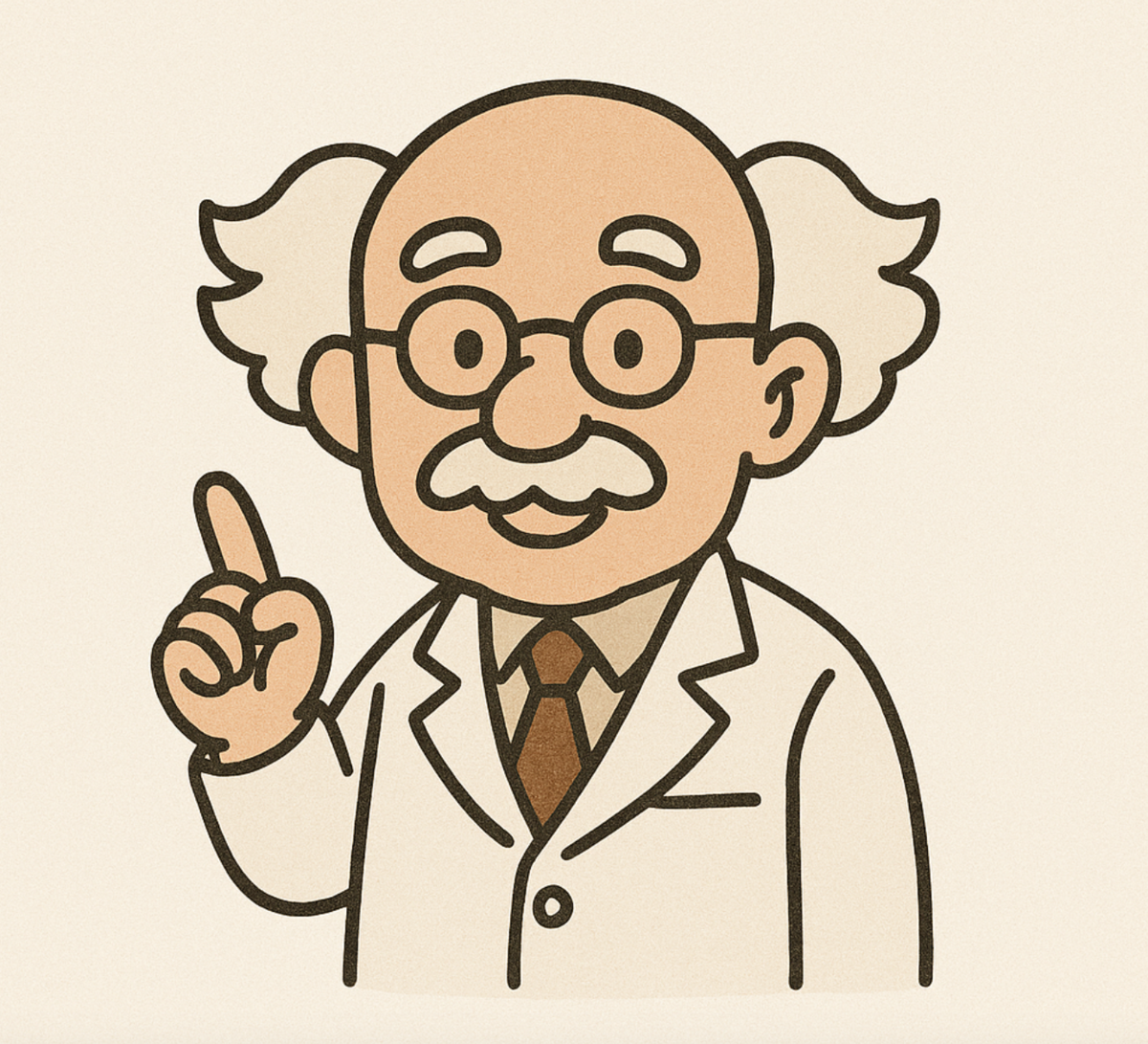

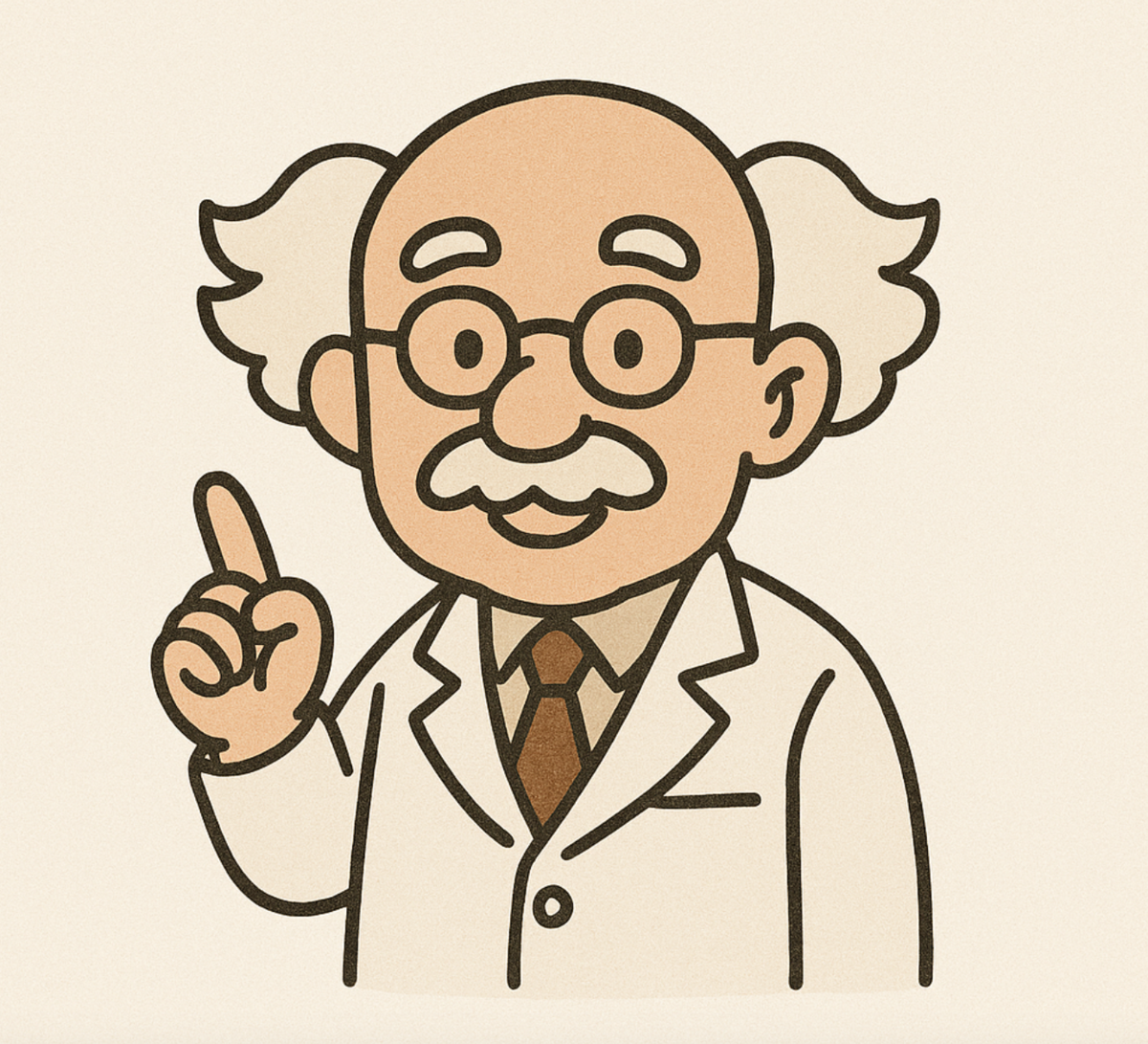

あなたも経験ありませんか?
読者の方のなかにも「破局思考」に陥りがちだという方はいませんか?
たとえば——
文章として読むと「自分はそんな極端な考え方はしない」と感じるでしょう。 しかし、実際にショックが大きい出来事に遭遇すると、このような「破局思考」に陥ってしまうこともあるのです。

「破局思考」から脱出するふたつの対策

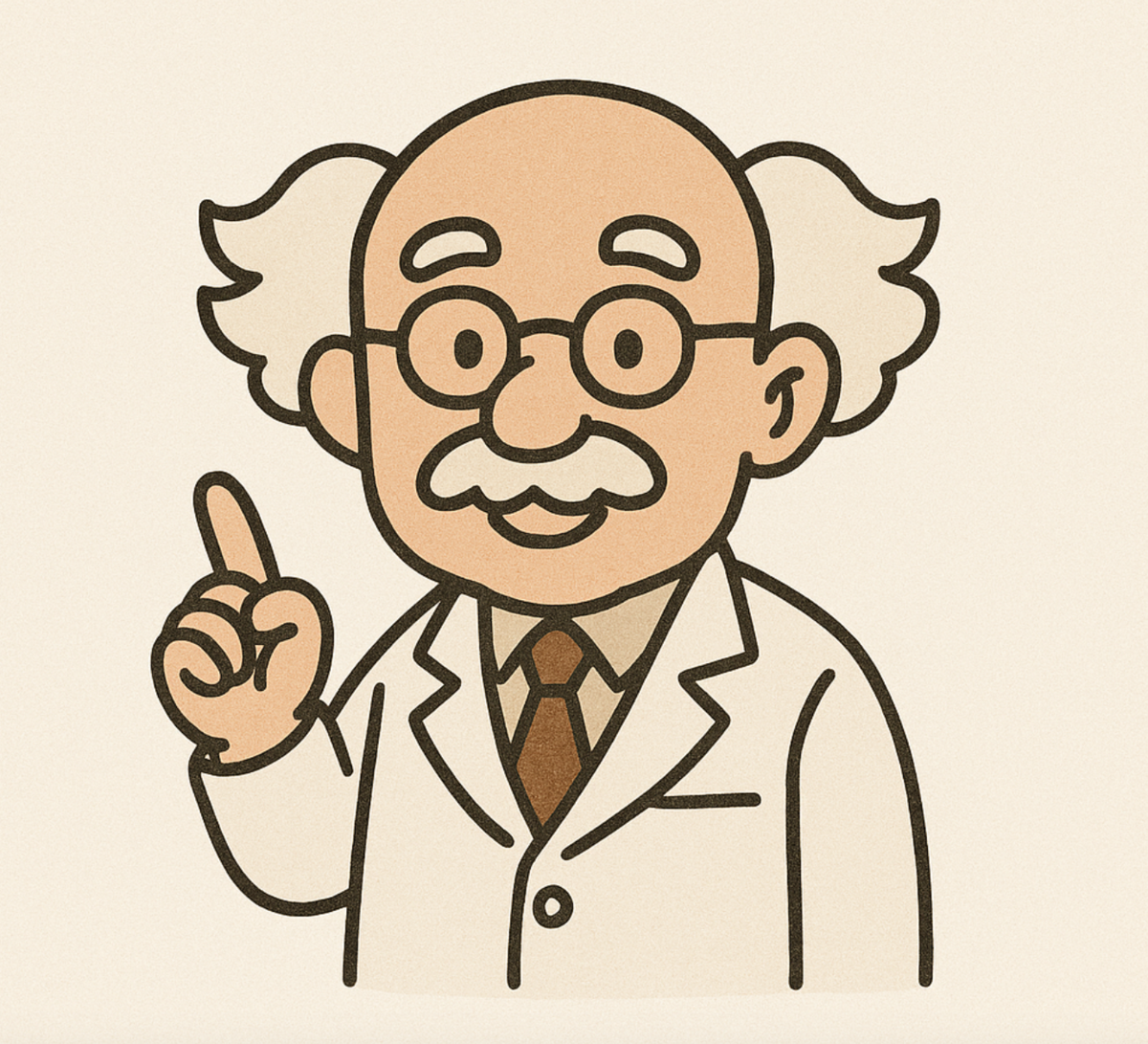
1. 感情を書き出す
行動科学専門家の永谷研一氏は、「ノートや手帳などに、『その日の中の一番強い自分の感情』として、自分がどんな気持ちだったかを書く」ことをすすめています。こうすることで、「自分の感情を客観的に見るクセ」をつけることができ、思考が極端になっていることに気づきやすくなるのです。*3
たとえば——
このようにノートに書き出してみましょう。書いた内容を改めて見てみると、「ちょっと思い詰めているかも。少なくとも『全部だめ』ってことはないな」と客観的にとらえられるようになります。
2. 脳内でネガティブな言葉のあとに「でも」を付け足す
1で紹介した「感情を書き出す」対策をしても、「破局思考」がクセになっている場合、なかなか抜け出せないこともあります。そんなときの対策として、脳科学者の西剛志氏は、ネガティブな言葉のあとに「でも、〇〇はできた・よかった」と付け足すことを提案しています。*4 理由は以下の通り。
- 前頭前野にある「視聴覚ミラーニューロン」は、言葉をイメージに変換する細胞。運動野という部分に隣接している
- 視聴覚ミラーニューロンが言葉をイメージに変換するたびに運動野が活性化され、体感覚も刺激される
→その結果、どんな言葉を自分に投げかけるかによって、実際の体感覚や行動が変化すると考えられる *5
たとえば——
『でも』指摘をちゃんとメモして、次回からできるように対策できた
このように「でも」を付け足すことで、「破局思考」から脱出し、いい面にも目を向けられるようになるのです。

失敗だけに注目せず、全体をフラットに見よう
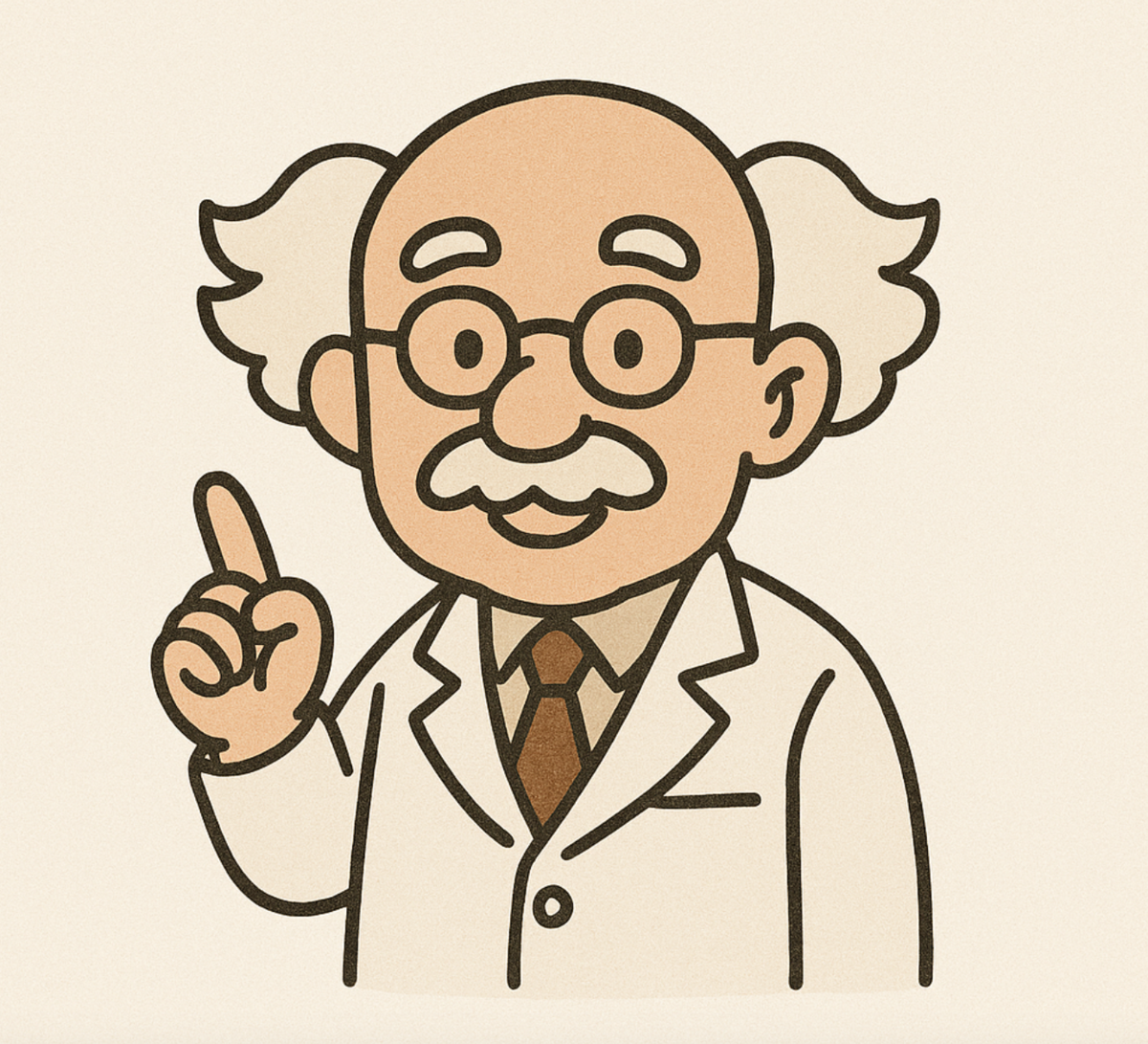

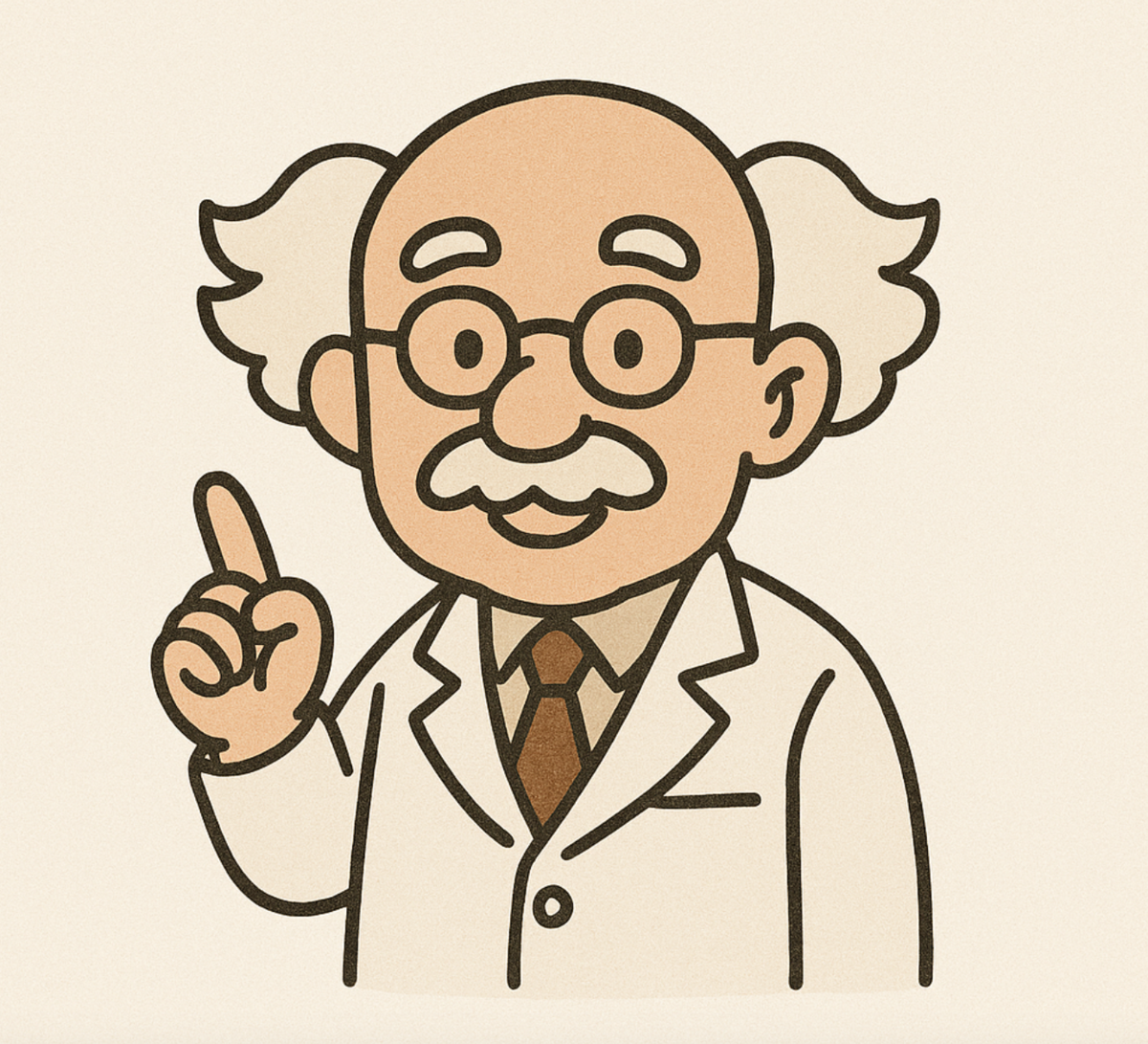

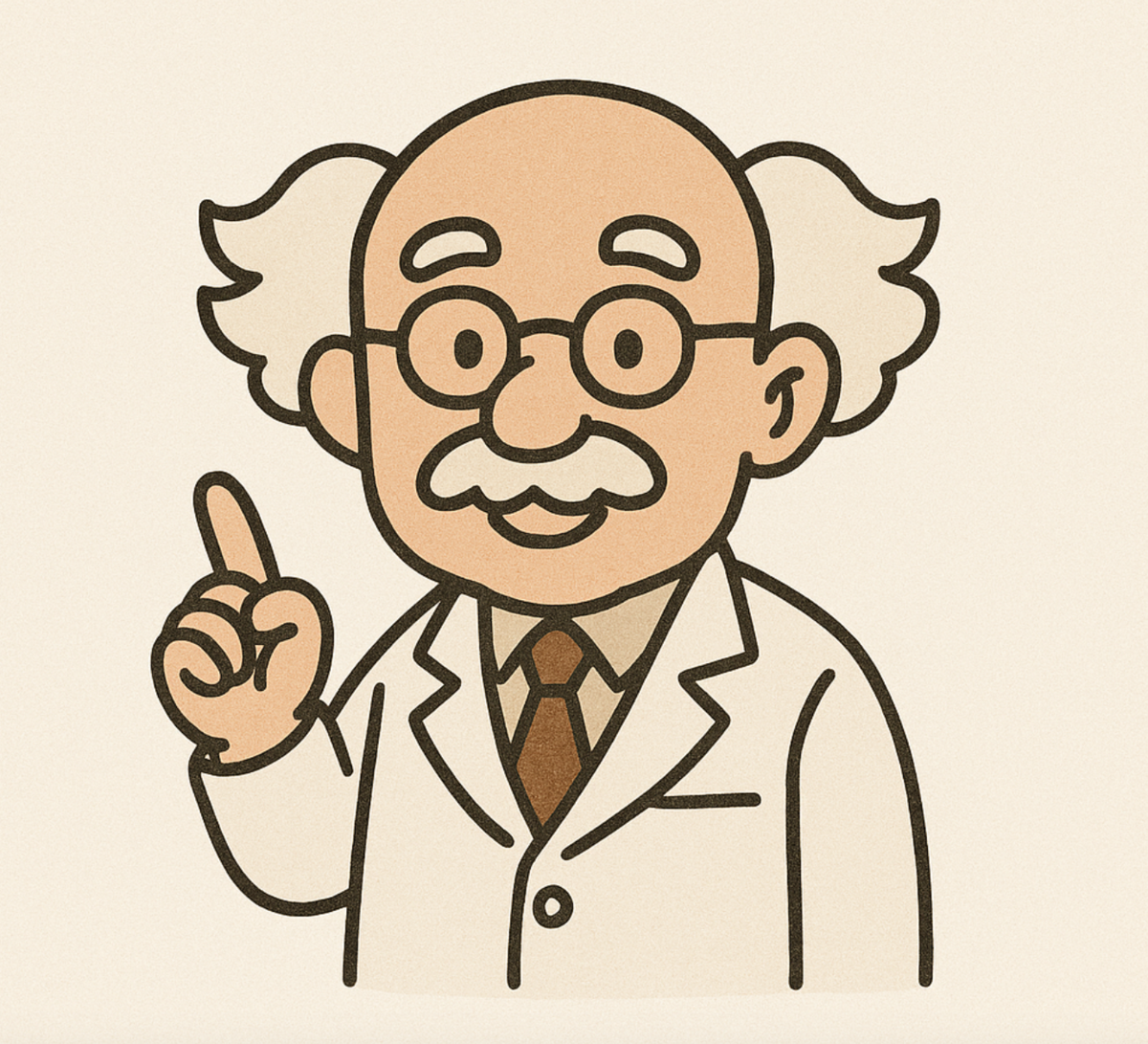
参考
*1 東京カウンセリングオフィス|過度の一般化 -認知の歪みと対策01-
*2 大阪メンタルクリニック|認知のゆがみ
*3 東洋経済オンライン|感情を「制御できない」→「できる」に変える"技術"
*4 パラサポWEB|勝つために必要なのは強いメンタルや努力じゃない。自分との対話“脳内トーク”のすすめ
*5 STUDY HACKER|ジョブズも毎朝やっていた。脳科学者が教える「脳内トーク」のすごい力――行動も人生も変えられる!
柴田香織
大学では心理学を専攻。常に独学で新しいことの学習にチャレンジしており、現在はIllustratorや中国語を勉強中。効率的な勉強法やノート術を日々実践しており、実際に高校3年分の日本史・世界史・地理の学び直しを1年間で完了した。自分で試して検証する実践報告記事が得意。

