
ビル・ゲイツ氏や柳井正氏といった著名な経営者が、読書を習慣にしていることはよく知られています。読書は単なる情報収集にとどまらず、新しい視点を得たり、思考を磨いたりするための「基本動作」として、古くから多くの人に重要視されてきました。
しかし、AI時代を迎えたいま、「読書の価値は薄れているのではないか」と思う人もいるかもしれません。AIは膨大なデータを処理し、私たちに整理された答えを提供してくれる便利なツールです。確かに、AIが進化したことで情報を得る手段は大きく変わりました。では、本当に読書は不要になったのでしょうか?
実際には、AI時代だからこそ、読書の重要性はむしろ高まっています。AIは「もっともらしい平均解」を導き出すことには長けていますが、その答えをさらに発展させたり、意外性のある切り口を加えたりするのは人間の役割。
そのプロセスを支える基盤が、読書で培った知識や論理的思考力です。本記事では、読書の価値を見直しながら、AIを “壁打ち相手” として活用し、発想を深化させるための方法をご紹介します。
- 壁打ちとは何か? AIが壁打ち相手に最適な理由
- AIとの壁打ちを高度化するために必要な「自分の知識」
- 具体例:読書による知識で壁打ちを深化させる方法
- 読書を壁打ちに活かす方法
- 読書習慣を無理なく身につける方法
壁打ちとは何か? AIが壁打ち相手に最適な理由
まず、壁打ちとは何でしょうか? 壁打ちとは、相手に問いやアイデアを投げかけ、その反応を通じて自分の考えを深めるプロセスです。たとえば、テニスの壁打ちでは、自分のショットを壁に向かって打ち返し、跳ね返ってきたボールを再び打つことでフォームや戦術を磨く。それと同じように、ビジネスにおける壁打ちは、自分のアイデアを試し、より洗練された考えに仕上げる行為と言えます。
壁打ちには次の3つの要素が求められます。
- 1つめは「無限の受け手」であること。相手が疲れず、何度でも問いを受けてくれる環境が必要です。
- 2つめは「感情に左右されない」こと。自由に試行錯誤できる環境でなければ、壁打ちは成立しません。
- 3つめは「整理された応答」が得られること。問いに対して的確で論理的な反応を返してくれる相手が理想的です。
ここで、AIが壁打ち相手として非常に優れている理由が見えてきます。AIは膨大なデータをもとに整理された答えを返し、感情や偏見を持たないため、無限に問いを試す場として理想的です。さらに、AIは問いを受けて新たな視点やデータを提供するため、壁打ちのプロセスを効率化してくれます。
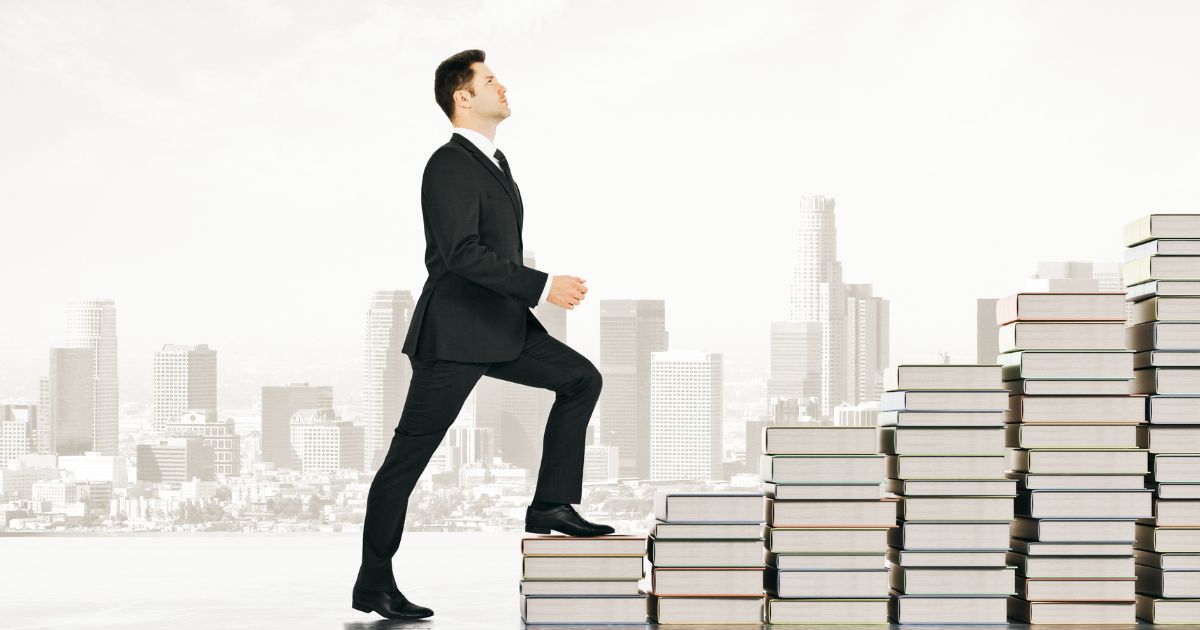
AIとの壁打ちを高度化するために必要な「自分の知識」
AIを壁打ち相手とすることで発想を深化させるプロセスは非常に有効です。しかし、それを高度化するには「自分自身の知識や視点」が不可欠です。
AIが提供する答えは「整理された結論」であり、それを発展させるには、自分自身に引き出しが必要です。知識や視点が乏しければ、AIの答えを深掘りする余地を見つけられず、「ふーん、そうなんだ」で終わってしまいます。逆に、自分の中にフレームワークや多様な視点があれば、「この前提を変えるとどうなる?」「この理論は応用できるか?」と問いを発展させることが可能になります。
では、その知識や視点をどう養うか。ここで読書の価値が生きてきます。読書は、情報を単に蓄積するだけでなく、異なる分野や著者の考え方を追体験することで、思考の幅を広げる場です。たとえば、歴史書を読むことで「パターンの繰り返し」に気づいたり、心理学書を読むことで「人間の行動原理」を理解することができます。
また、読書の最大の利点は、他者の視点を追体験することで「問いを立てる力」が養われる点です。読書で得た視点を壁打ちに活用することで、AIとの対話がより高度なものとなり、新たな発想が生まれやすくなります。
具体例:読書による知識で壁打ちを深化させる方法
読書によって得た知識を、実際のAIとの壁打ちでどのように活用すればよいか、具体例を見てみましょう。
具体例1:PDCAではなくOODAループを試す
- 問い1:「このプロジェクトの改善策を考える」
- AIの答え:「PDCAを使って改善を進めましょう」
- 切り口を加える:「OODAループの “観察(Observe)” に焦点を当てるとどうなる?」
- OODA(観察、判断、決定、行動)の視点を活用することで、「市場の変化をいち早く観察する」という新しい着眼点が生まれる。
- さらに深掘り:「観察フェーズで競合が見逃しがちなデータは何か?」 → 自分の仮説が進化する。
具体例2:加算バイアスを逆手に取る
- 問い1:「このチームの生産性を向上させるには?」
- AIの答え:「新しいタスク管理ツールを導入しましょう」
- 切り口を加える:「加算バイアス(人が改善策として “足す” ことを好む傾向)を踏まえ、減らす方向で考えるとどうなる?」
- 「どのプロセスを削ることで、チームの創造性が向上するか?」という新たな視点が得られる。
- さらに深化:「削減の効果が長期的にプラスに働いた事例は?」 → 過去の成功事例をもとに自分のアイデアが磨かれる。

読書を壁打ちに活かす方法
読書をAIとの対話に効果的に活かすには、単に本を読むだけでなく、読書の過程で意識的に問いを立て、新しい視点を見いだすことが重要です。以下の3つの方法を意識して実践してみましょう。
1. 読書で新しいフレームワークを得る
読書を通じて学んだフレームワークや理論は、AIとの壁打ちにおいて、問いを立てるための強力な武器になります。・ AIに「この理論を現状に当てはめると?」と問いかける
・ 例:マーケティング本で学んだペルソナ設定を新商品開発に活用
2. 異分野の本を意識して読む
心理学、哲学、歴史、科学など、普段触れないジャンルの本が、新たな切り口を提供します。・ 例:心理学の「加算バイアス」から、削減による改善を考える
・ 歴史書から「パターン」を学び、市場トレンドを予測
3. 問いを意識しながら読む
「この知識をどう活用するか?」を考えながら読むことで、読書が壁打ちと直結します。・ 読了後に具体的な問いをAIに投げかける
・ 例:「この戦略論は自社の競争戦略にどう活用できるか」をAIと対話
読書習慣を無理なく身につける方法
「読書の大切さはわかるけど、忙しくてなかなか時間が取れない」「決意はするものの続かない」
そんな方のために、無理なく始められる工夫をご紹介します。
まずは週に1章、あるいは月に1冊からスタートしましょう。できるだけ薄い本を選んで、読み終えた達成感を味わうことが大切です。「とりあえず1冊」という気軽な気持ちで始めるのがコツです。
目次をチェックして、面白そうな章から読み始めましょう。特に実例やケーススタディは理解しやすいものです。難しい理論は後回しにしても大丈夫。自分のペースで進めていきましょう。
通勤電車の中や昼休み、寝る前のちょっとした時間など、すきま時間を見つけて読書するのがおすすめです。
読んだ内容をAIに質問してみたり、チームで話題にしたり、簡単なメモを残したり。アウトプットの方法は自由です。小さな気づきを共有することから始めましょう。
***
AIは「整理された答え」を提供するツールであり、それを超える価値を生むのは人間の役割です。読書は、新たなフレームワークや視点を得るための最適な手段であり、壁打ちを通じて思考を深化させる基盤となるのです。
読書で得た知識を活かした「AIとの壁打ち」で、考えを深めていきましょう。いま、読書の価値はかつてよりより大きくなったと言えるのではないでしょうか。
大谷佳乃
「なぜ?」という疑問を大切に、日常に潜む人とモノとの関係性を独自の視点で読み解くライター。現在は、私たちが何かを選ぶときに働く「見えない力」に注目し、そのメカニズムを探求中。休日は、古書店で先人たちの知恵に触れるのが、自分にとっての「特別な時間」。

