
「スキルアップのために勉強を始めたけれど、内容がなかなか定着しない」
「周囲からすすめられたからビジネス書を読んでみたけれど、もう忘れてしまった」
このように、学習内容が記憶に定着せず悩んでいる人にお聞きします。
その勉強を始めた「動機」は何ですか?
なかには「なんとなく」勉強をしている人もいるのではないでしょうか。
万能の天才と呼ばれたレオナルド・ダ・ヴィンチは「欲求を伴わない勉強はむしろ記憶を損なう」という言葉を残しています。*1
つまり、知りたい・やってみたいといった欲求がなければ、いくら勉強をしても覚えられないということです。
この記事では、欲求と記憶の関係についてご説明するとともに、自分の欲求を探るための方法もご紹介します。
自分の欲求をベースにすることで、モチベーションに左右されずに記憶に残る勉強ができるようになるはずです。
「なんとなく勉強」が記憶に残らない理由
ビジネスパーソンにとっての勉強は、キャリアアップや転職、新たなスキルの獲得など様々なチャンスにつながります。
しかし、勉強の内容や目的が自由だからこそ「なんとなく」勉強してしまうケースが多いのも事実です。
こうした「なんとなく勉強」のデメリットについて、先にも述べたようにレオナルド・ダ・ヴィンチが次の言葉を残しています。
食欲がないのに食べると健康を害すのと同じように、欲求を伴わない勉強はむしろ記憶を損なう。*1
食欲がないときに食事が出てきても、多くの人が「いらない」と思うでしょう。
無理に食べれば体調を崩してしまいます。
同じように「知りたい」「やりたい」と思っていないのに無理に勉強をしても、脳がその知識を拒んで定着しないのです。
欲求と記憶との結びつきは、現代の脳科学でも証明されています。
脳科学者の瀧靖之氏によると「知的好奇心がドーパミンという脳内物質の分泌を促し、記憶力の向上に影響を与える」そうです。
これには感情をつかさどる扁桃体と、記憶をつかさどる海馬の働きが関係しているといいます。
「扁桃体」で「好き・快」と判断され、「ドーパミン」が分泌されると、「海馬」がプラスに刺激され、記憶力を高める、思考が深まる、達成感ややる気を生じさせる、といった効果が生み出されます。*2
つまり、記憶の定着には、興味のあることや好きなことなど、自身の知的好奇心が刺激されるような内容を勉強するのが一番だということです。
いま「なんとなく」勉強をしている人も、自分がなぜ勉強を始めたのか振り返ったり、興味のある内容がないか探してみたりすることで知的欲求を掻き立てられる可能性があります。

現代に活かす! 欲求ベースの学習アプローチ
「知りたい」という欲求が、学びの原動力になることがわかりました。
とはいえ、勉強に苦手意識のある人や、仕事で必要だから関心がないことも勉強しなければならない人もいるはずです。
このようなケースでは、知的欲求を刺激しにくいと感じるでしょう。
じつは、知的欲求以外にも脳が「好き・快い」とポジティブに受けとる3つの欲求があります。
スタンフォード大学のオンラインハイスクール校長を務める星友啓氏によれば、それは「つながり」「有能感」「自発性」。
これらの欲求も、記憶の定着に役立つと考えられます。
それぞれ詳しく解説しましょう。*3
つながり
「人に必要とされたい」「役に立ちたい」といった欲求は誰もがもつものです。
星氏は「誰かのために何かをしたり、他の人とのコミュニケーションをしたり、コラボをしたりする機会が、私たちのモチベーション」につながると言います。*3
「実際、他の人とコミュニケーションをしたり、コラボをしたりすると、脳の報酬系が活性化する」そうです。*3
この欲求を勉強に結びつける例として、次のようなものが挙げられます。
-
他部署との連携をスムーズにするために、ロジカルシンキングや課題整理のフレームワークを学ぶ
- 社内勉強会で価値ある情報を提供するために、最新の業界トレンドを調べて整理する
- 海外との取引先とスムーズにやり取りするために、ビジネス英語を学ぶ
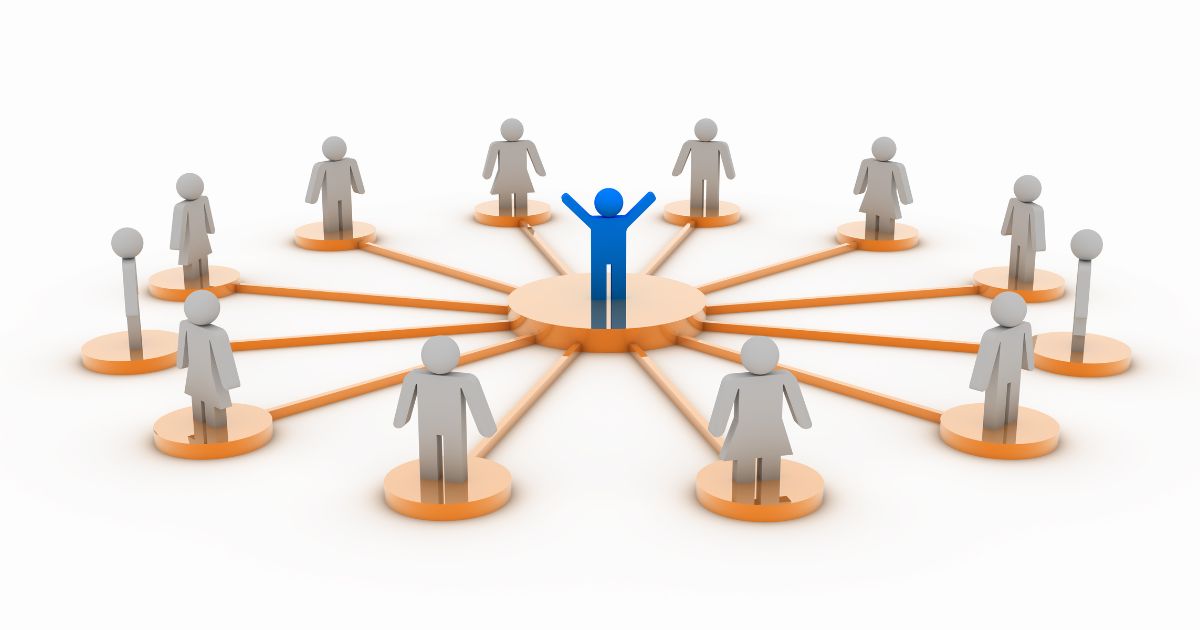
有能感
「できる」という感覚も、脳が喜ぶ要素です。
星氏は「私たちの脳が新しい知識やスキルを学ぶとき、ドーパミンが分泌され」ると述べています。*3
これは「興味のあることを知る・わかるようになる」という知的欲求とも結びついているといえるでしょう。
このほか、問題が解けたときや目標を達成したときなども、有能感を味わえます。
これを勉強に結びつけると、次のような例が挙げられます。
- 営業トークの精度を上げるために、心理学や交渉術の本を読む
- データ分析に強くなるために、ExcelやGoogleスプレッドシートの関数・ピボットテーブルを習得する
- 会議の進行をスムーズにするために、ファシリテーションスキルを学ぶ

自発性
「自分で決めた」「自分の意志でやっている」という感覚も重要です。
星氏は「『自分からやっている』『自分の意思でやっている』という感覚を欲するのは、人間の根本欲求」だと語ります。*3
先に述べたように、自分のやりたいことや興味が脳にとって「好き・快」と受け取られるのであれば、反対に嫌々やらされていることは「嫌い・不快」と感じるはず。
自分のしたいことを考え、決断したうえで勉強に取り組むことは脳の性質にもマッチした欲求の満たし方だと言えます。
自発性は「知的欲求を満たしたい」という欲求だけでなく、キャリアアップや転職など「なりたい自分に向けて勉強をする」といった動機づけでも発揮できます。
たとえば、次のようなイメージです。
- 将来独立することを見据えて、マーケティングや営業スキルを自主的に学ぶ
- 仕事をもっと楽しくしたくて、自分の得意を活かせるプロジェクトに自ら手を挙げ、必要なスキルを学ぶ
- 自分の伝えたい思いを表現するために、ライティングスキルや資料作成のコツを学ぶ

自分の欲求を探る「妄想ノート」
「興味のあることやしたいことはあっても、勉強につながらない」
「自分のやりたいことがまだ見つからない」
このような人は、ノートを使って自分の欲求を探ってみましょう。
脳内科医の加藤俊徳氏は「やりたいこと、行きたい場所、会ってみたい人など、頭に浮かんだ欲求を書き留めていく」妄想ノートをすすめています。
欲求を頭のなかで考えるだけでなく、書き出すことが重要です。
頭に浮かんだことは、そのままでは漠然としたイメージにすぎませんが、文字にすることで脳がその内容をより強く認識するんです。それによって自分の欲求を客観的にとらえることができるんですよ。*4
書き出すことで欲求を客観的にとらえることができ、それを勉強の原動力として意識しやすくなるというわけです。
また、たとえば「この業界に転職したいのはなぜ? 転職を叶えたら、そこで何をしたい?」といったように、欲求の掘り下げも書き出すことによってできるでしょう。
まずはざっくりとした内容でいいので、興味のあることや、やってみたいことなどを書き出してみるのがおすすめです。

***
「やったほうがよさそう」「職場で言われたから」と、なんとなく勉強している人は多いはず。しかし、自分の欲求に目を向けるだけで、記憶の定着率が向上します。勉強の成果を実感するためにも、まずは自身の欲求と深く向き合ってみてはいかがでしょうか。
※引用の太字は編集部が施した
*1 ダイヤモンド・オンライン|「知の怪物」ダ・ヴィンチはなぜ膨大なメモを残したのか?
*2 ピティナ調査・研究|第8回:「イヤイヤ練習」と「楽しく練習」とでは、上達に差があるの?
*3 ダイヤモンド・オンライン|脳がみるみるやる気を出し 情熱的モチベーションが生まれる 「3大習慣」
*4 タウンワークマガジン|大学生必見! 夏休み中に始める、脳がみるみる活性化する習慣5
藤真唯
大学では日本古典文学を専攻。現在も古典文学や近代文学を読み勉強中。効率のよい学び方にも関心が高く、日々情報収集に努めている。ライターとしては、仕事術・コミュニケーション術に関する執筆経験が豊富。丁寧なリサーチに基づいて分かりやすく伝えることを得意とする。

