
夜、スマホを片手にベッドに入り、ほんの少しのつもりでショート動画を見始める。ひとつ見終わってスワイプ、またひとつ——気づけば、あっという間に1時間が経過。目は冴えて眠れず、翌朝は寝不足でぼんやり……。
「今日は絶対に見ないようにしよう」そう思うのに、ついついスマホに手が伸びてしまう。
こんな経験はありませんか? ショート動画の視聴をやめられないのは、意志が弱いからではありません。動画プラットフォームが、私たちの脳のクセを巧妙に利用しているからなのです。
この記事では、なぜショート動画に依存してしまうのか、その科学的メカニズムと、ビジネスパーソンが実践できる具体的な対策法を解説します。
「いいことが起こるかも」という期待感に脳は弱い!
なぜYouTubeショートを見るのを止められないのか? この疑問を紐解くカギとなるのが、「ドーパミン」です。
ドーパミンは「幸せホルモン」として知られています。「欲しいものを手に入れたり、目標を達成したりしたときにドーパミンが出る」というイメージがありますよね。
しかし、神経科学者で、公立諏訪東京理科大学情報応用工学科教授の篠原菊紀氏は「ドーパミン神経系は、報酬予測でも働く」と説明しています。*1
つまり、実際に欲しいものを手に入れたときだけでなく、「手に入りそうだ」と期待した段階でもドーパミンは分泌されるのです。むしろ、「期待している状態」のほうが多くドーパミンが分泌されることもわかっています。
精神科医の曽良一郎氏は、以下のように説明しています。
例えば、動物が何かの報酬として食べ物を得られた場合、ドーパミンの分泌量は、食べ物を得られたときよりも、得られる直前の方が多かったのです。人もそう。実際に楽しいことが得られた瞬間よりも、その前の期待をしているときがすごくワクワクする。*2
これは私たちの日常でも実感できるでしょう。宝くじを買った瞬間から抽選日までのドキドキ感、好きなアーティストのライブチケットが取れるかもしれないという待ち時間、気になる相手からのLINE返信を待っているとき——実際に結果が分かる前の「もしかしたら」という期待感こそが、強い興奮状態を生み出すのです。
「いいことが起こるかもしれない」という期待感。これが、ドーパミンをたくさん分泌するというわけです。
ちなみに、篠原氏によると「もっとも、ドーパミンの総量が多くなるのは期待値が概ね50%から75%の間」。*1 つまり、毎回確実にごほうびがもらえるのでも、めったにもらえないのでもなく、「ときどきもらえる」という絶妙な確率が、人間の脳を最も夢中にさせるのです。これはパチンコや競馬などのギャンブルが多くの人を魅了する理由でもあります。
・報酬の確率が50〜75%だと、脳が最も反応しやすい
・「もしかしたら」が脳を興奮させるカギ
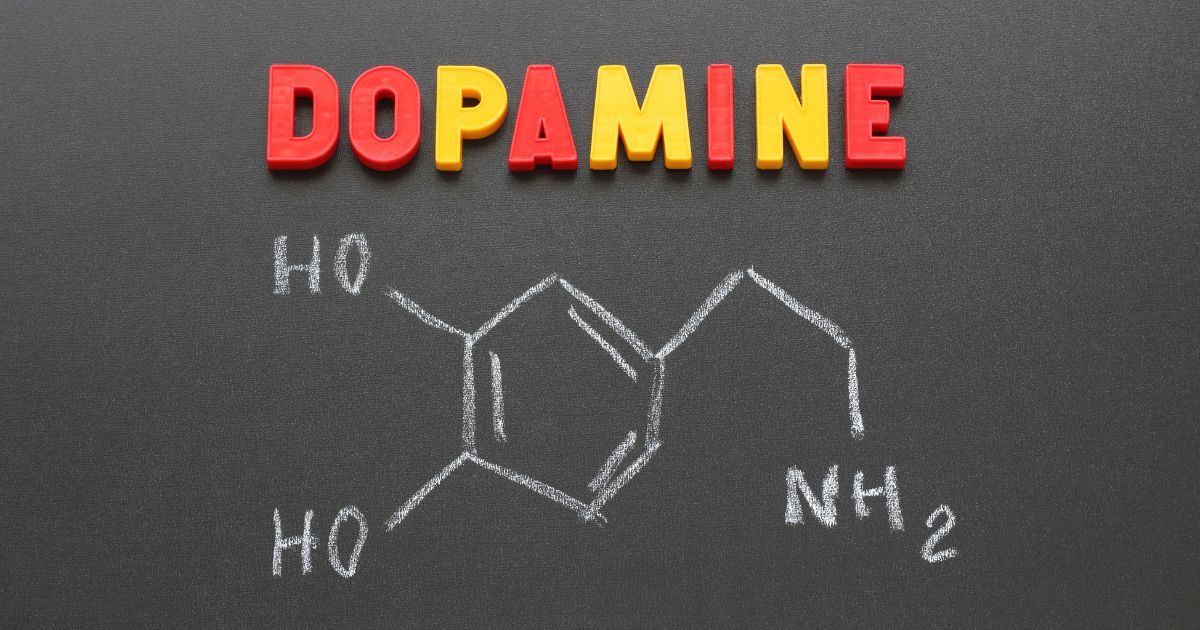
なぜYouTubeショートやTikTokを止められないのか?
前章で解説したように、私たちの脳は「いいことが起こるかも」という期待感に非常に強く反応します。じつは、YouTubeショートやTikTokのような短尺動画のプラットフォームは、まさにその「脳のクセ」を巧みに突いているのです。
これらのサービスでは、1本あたりの動画が数秒から1分程度と非常に短く、興味がなければスワイプひとつで次の動画に移れます。この手軽さが「もう1本だけ」という心理を生み出す第一の要因です。
そして重要なのが、出てくる動画の予測不可能性です。AIアルゴリズムによって配信される動画はランダムで、次にどんな動画が表示されるか誰にも分かりません。
「全く興味のない商品紹介」の次に「爆笑必至のペット動画」が来るかもしれませんし、「退屈な日常系動画」のあとに「驚愕の科学実験」が現れるかもしれません。この不確実性こそが「ときどき当たる」という条件を満たし、ドーパミン分泌を促すのです。
さらに、これらの動画の多くは視聴者の注意を瞬時に掴むよう巧妙に設計されています。「最後まで見ないと後悔する」「このあと、衝撃の展開が……」といった煽り文句で始まったり、冒頭数秒でインパクトのある映像を見せたりして、「続きが気になる」状態を意図的に作り出しています。これもまた、「どんな内容なんだろう?」と期待を高め、ドーパミンを分泌する仕掛けになっているのです。
YouTubeショートやTikTokがやめられないのは、単にコンテンツが面白いからだけではありません。脳科学的にドーパミンが分泌されやすい構造になっているため、私たちは意図せずハマってしまうのです。
・続きが気になる仕掛け=ドーパミンを引き出す構造
・やめられないのは意志の問題ではなく、設計のせい

適切に付き合うための対策
YouTubeショートやTikTokは、ほどほどに見るなら楽しい娯楽です。しかし、ズルズルと見続けて、健康を害したりやるべきことに支障が出たりするようでは困りますよね。
特にビジネスパーソンにとって、動画への依存は深刻な問題です。重要なプレゼン準備が進まない、資格取得の勉強時間が確保できない、睡眠不足で翌日のパフォーマンスが下がる——こうした状況を避けるために、科学的根拠に基づいた対策が必要です。
作業療法士の菅原洋平氏は、「わかっているけど、止められないこと」を解消するには、その行動をしたあとどうなったかを「リアルで具体的な身体感覚として」イメージすることが効果的だと述べています。*3
具体的には、「YouTubeショートやTikTokを見続けたあと、どういう状態だったか」を振り返って書き出しましょう。身体で感じた不快感を具体的に思い出すことがポイントです。
たとえば……
- 夜中の2時まで動画を見続けた結果、翌朝は目がショボショボして痛く、頭がぼんやりしてコーヒーを何杯飲んでも眠気が取れない
- 長時間スマホを見下ろしていたせいで、首と肩がガチガチに凝って、集中力が全く続かない
- ほかにやることがあるのに、スワイプするのを止められない。気持ちはずっと焦ってる感じで、イライラ、そわそわしている。
このように、見終わったあとの「やっちゃったな……」という後悔の理由を、身体で感じた不快感とセットで具体的に言葉にして振り返るのです。
菅原氏は、「ドーパミンには行動を制御する『コントロール回路』があり」、「これは、記憶されている身体感覚を振り返ったときに発動」すると説明しています。*3 つまり、その行動によってどんな不快な思いをしたのかを身体感覚とともに振り返ることで、脳の制御機能が働き、「わかってはいるけど、止められない」行動と自然に距離を置くことができるのです。
・予測不能性や即時性が “もう1本だけ” を誘発する
・「身体の不快感」を言語化することで、依存を抑えることができる
***
YouTube ShortsやTikTokがやめられないのは、脳が「次はおもしろい動画が見れるかも」と期待し、ドーパミンを分泌するから。
もし見すぎて仕事や生活に支障が出ているなら、まずは菅原氏が提案する「身体感覚を伴った振り返り」を実践してみてください。ショート動画は適切な距離感で楽しみ、本当に大切な仕事や自己成長のための時間を確保しましょう。
*1 プレジデントオンライン|人気のパチンコ台が駆使する脳科学の教え
*2 深デジ|専門家「ガチャは回す前が一番楽しい」脳内で起きていること
*3 プレジデントオンライン|ランチを仕事用デスクで食べてはいけない…仕事のできない人がやりがちな"昼休みの悪習慣"
柴田香織
大学では心理学を専攻。常に独学で新しいことの学習にチャレンジしており、現在はIllustratorや中国語を勉強中。効率的な勉強法やノート術を日々実践しており、実際に高校3年分の日本史・世界史・地理の学び直しを1年間で完了した。自分で試して検証する実践報告記事が得意。

