
「今度のプロジェクト、何から手をつけていいか分からない……」
「新しいアイデアが思い浮かばない。発想力が足りないのかな」
マニュアルや正解がない状況で、どう進めばいいか分からない。そんな経験はありませんか?
でも、よく思い出してみてください。私たちは子どもの頃、誰に教わるでもなく「自分で考えて、自分で調べて、自分なりの答えを出す」ことを自然にやっていました。そう、夏休みの自由研究で。
あの頃は嫌々ながらも、なぜかテーマを見つけて最後までやり遂げていた。いま思えば、誰に教わるでもなく「自分で考えて、自分で調べて、自分なりの答えを出していた」あの体験。
そのときに身につけていたスキルこそが、いまのビジネス現場で最も求められている能力だったとしたら?
多くの人が「創造性がない」「問題解決が苦手」と感じている一方で、子どもの頃には誰もが自然に発揮していた力があります。それが「自由研究力」──自分で問いを立て、試行錯誤しながら答えを見つける力です。
自由研究は最初の「アントレプレナー体験」だった
改めて自由研究のプロセスを振り返ってみましょう。
身の回りの疑問や興味から課題を見つける
仮説を立てて検証を重ねる
結果を整理して人に伝える
一見すると単純なプロセスですが、これこそが現代ビジネスで重要視される「イノベーションの源泉」です。
まず「テーマ決め」の段階を思い出してみてください。「どうして氷は浮くんだろう?」「近所の商店街はなぜ人が少ないんだろう?」——子どもたちは日常の「当たり前」に疑問をもち、自分なりの課題を設定していました。これは、まさにビジネスにおける「市場機会の発見」そのものです。
実際に革新的なビジネスの多くは、誰もが当然と思っている前提への疑問から生まれています。たとえば、最近話題のスキマバイトマッチングサービス「タイミー」は、労働者の「働きたい時間」と企業の「働いてほしい時間」をマッチングさせ、選考なしで即日働ける点が特徴。「アルバイトには履歴書・面接が必要」という常識を覆すサービスです。*1 革新的なビジネスは、自由研究の「テーマ決め」と同様に業界の「当たり前」に疑問をもつことから始まっているのです。
次の「実験・調査」段階では、子どもたちは限られた時間と材料を使い、自分なりの方法を考案していたはずです。図書館で調べる、実際に観察する、簡単な実験装置を用意する——これらはすべて「仮説検証」の手法です。
そして最後の「まとめ・発表」では、自分が発見したことを他者に分かりやすく伝える必要がありました。模造紙にグラフや図を描き、写真を貼り、要点を整理する。これは「価値提案」そのものです。どんなに素晴らしい発見をしても、それを相手に伝えられなければ意味がない——この重要性を、子どもたちは体験的に学んでいたのです。

これら自由研究のプロセスは、ビジネスにおけるアントレプレナーのサイクルそのものです。「アントレプレナーシップ」とは「事業やプロジェクトなどを立ち上げ、運営する能力やリスクに立ち向かう精神」のこと。*2
文部科学省では、アントレプレナーシップ教育を「自ら社会課題を見つけ、課題解決に向かってチャレンジしたり、他者との協働により解決策を探求したりすることができる知識・能力・態度を身に付ける教育」と位置付けています。*3
この定義を自由研究のプロセスと照らし合わせてみると、驚くほど合致していることが分かります。
- 「自ら課題を見つける」(テーマ決め)
- 「課題解決に向かってチャレンジする」(実験・調査)
- 「解決策を探求する」(まとめ・発表)
——まさに自由研究が体現していたプロセスそのものです。
つまり、多くの人が子どもの頃に体験した自由研究は、人生最初の「アントレプレナー体験」だったのです。そして、この体験を通じて身につけた思考パターンや行動様式が、のちのビジネス成功を左右する基盤となっている可能性があります。
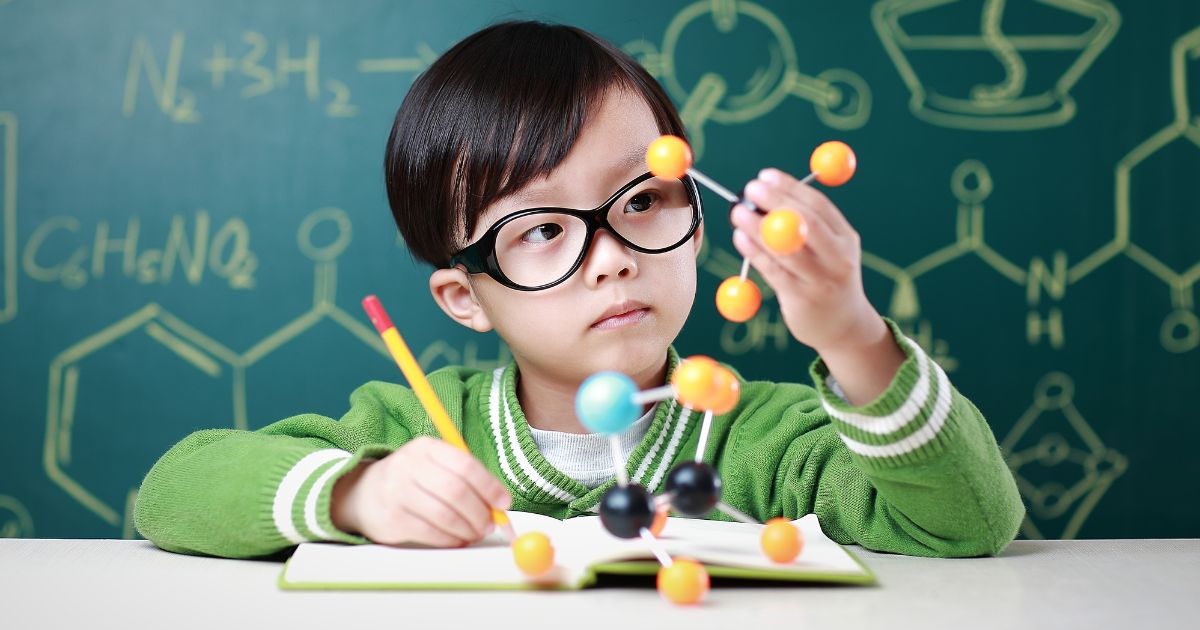
いまから鍛えられる「大人の自由研究」3選
では、大人になったいま、どのように「自由研究力」を取り戻せるのでしょうか。子どもの頃のような「なぜ?」「どうして?」という探究心を、ビジネスの現場で体系的に活用できる3つの方法をご紹介します。
1. 働き方マンダラート
マンダラートは、目標や課題を多面的に分解し、連想を広げながら整理するフレームワークです。メジャーリーグで活躍している大谷翔平選手が高校生のときに作成していたことで注目されているメソッドでもあります。
課題の構造化と新しい視点の発見
具体例として、「チームの生産性向上」を課題に設定してマンダラートを作成してみましょう。まずは中央の課題「チームの生産性向上」を解決する要素を8つ考え、中目標として、周囲に書き出します。今回は以下の8つを中目標に設定しました。
- コミュニケーション改善
- 業務プロセス見直し
- スキルアップ支援
- モチベーション向上
- 環境整備
- ツール活用
- 時間管理
- 評価制度改善
8つの中目標を残りの大きな正方形の中央に書き写すと、以下のようになります。

次に、中目標を解決する方法を考えてそれぞれの周囲のマスに書き出し、全72マスを埋めれば完成です。
このように課題を具体的なアクションまで細分化することで、「何から手をつけていいか分からない」状況を打破し、実行可能なタスクが明確になります。
マンダラートの真の価値は、課題の「見える化」だけではありません。作成プロセスによってこれまで気づかなかった課題の関連性や優先順位を発見するきっかけとなります。まさに、子どもの頃の自由研究で「あれ? これとこれって関係があるのかも」と気づいた瞬間の再現と言えるでしょう。
ビジネスの課題解決に活用することで問題の全体像を俯瞰でき、見落としていた関係性や新たな解決策を見つけられるはずです。
2. UX分析
自分自身がユーザーになる「ドッグフーディング」は、世界的企業でも採用されている手法です。顧客体験の流れを把握でき、現場感覚に基づいた改善提案ができるようになるでしょう。
顧客視点での問題発見力向上
自社サービスやプロダクトを、あえて一般ユーザーの立場で1週間利用し、不便な点や改善点を時系列で記録します。利用場面・感情・行動をセットで書き残すのがポイントです。
自社の営業支援システムをユーザーの立場で一週間利用してみたとしましょう。
1日目(月曜日)
利用場面:朝一番の案件確認
感情:焦り(ログインに時間がかかる)
行動:パスワードを3回間違える
気づき:IDとパスワードが複雑すぎる
3日目(水曜日)
利用場面:客先でのプレゼン資料作成
感情:イライラ(必要なデータが見つからない)
行動:5つの画面を行き来してようやく発見
気づき:検索機能が使いにくい
5日目(金曜日)
利用場面:週次レポート作成
感情:達成感(ようやくコツを掴んだ)
行動:ショートカット機能を発見して活用
気づき:便利機能の案内が不十分
この1週間の体験記録から「ログイン簡素化」「検索機能改善」「オンボーディング強化」という3つの具体的改善提案を導き出すことができました。
重要なのは、データや分析レポートでは見えない「感情の動き」をとらえることです。数字では「ログイン完了率95%」と表示されても、その5%の失敗の裏にある「焦り」や「イライラ」といった感情は見えません。自由研究で観察をしていたときのように、細かな変化に気づく観察眼こそが、真の改善につながります。
3. 5回"なぜ?"掘り
業務上の問題に対して「なぜ?」を5回繰り返し、表面的な症状ではなく真の原因を特定します。トヨタ生産方式で用いられる有名な問題解決手法です。
根本原因分析力の強化
問題に対して「なぜ?」を5回繰り返します。重要なのは、「なぜ?」を自分や他人には向けないこと。かつてトヨタグループに所属し、現在は経営コンサルタントである森琢也氏は「「なぜ?」を向ける対象」は、「「やり方」「進め方」など仕事のプロセスにする」のが基本だと伝えています。*4
問題:「プロジェクトの納期遅延が頻発している」
→ タスクの見積もりが甘いから
→ 過去の実績データを参考にしていないから
→ データが整理されておらず、探すのに時間がかかるから
→ プロジェクト終了後の振り返りが形式的で、データ蓄積の仕組みがないから
→ 振り返りの目的が共有されておらず、次のプロジェクトへの活用方法が明確でないから
根本原因:プロジェクト知見の組織的蓄積・活用体制の不備
解決策:
応用編:もし子どもがいるなら……相乗効果が生まれる理由
自分が「大人の自由研究」に取り組むことで、お子さんにも思わぬ好影響があることをご存知でしょうか。
心理学者アルバート・バンデューラの社会的学習理論によれば、人は他者の行動を観察し、その結果や評価を通じて学ぶとのこと。*5 特に親は、子どもにとって重要な「モデル(手本)」となるため、探究的な姿勢や好奇心をもって行動する様子を見せることで、子どもも自然と似た思考パターンや学びの姿勢を取り入れやすくなります。
さらに、教育心理学のモデル研究では、親の学習への関与が子どもの自己効力感や内発的動機づけを高める要因のひとつになり得ることが示唆されています。*6 親が主体的に学ぶ姿勢を示すことは、子どもの学習意欲形成にとっても有益な環境づくりと言えます。
では、親子でどんな探究活動に取り組めばいいのでしょうか? そのヒントが満載なのが、姉妹サイト「こどもまなびラボ」の探究型自由研究特集です。
>>「体の不思議」探究型プロジェクト【ワークシート無料ダウンロード】|夏休みの自由研究シリーズ①
>>毎日の食卓にある「食材」を研究テーマに—— 海苔プロジェクト【ワークシート無料ダウンロード】|夏休みの自由研究シリーズ②
>>お店やさんごっこを本格的にやってみた「こどもレストランプロジェクト」| 夏休みの自由研究シリーズ③
このほかにも、年齢や興味に合わせて選べるテーマが豊富。「何をやろう?」と迷う時間が、ワクワクの探究時間に変わります。
親子で「なぜ?」と問い、小さな実験を重ね、発見を共有する——そんな日常が、お子さんの探究心や問題解決力、将来のアントレプレナー精神を育む土壌になるでしょう。
自由研究のアイデアをもっと見る: こどもまなびラボ「自由研究特集」へ

***
子どもの頃の自由研究で培った「問いを立てる力」「試行錯誤する力」「持続する力」は、現代ビジネスで求められるアントレプレナー・スキルそのものでした。そして、これらのスキルは大人になってからでも再び磨くことができます。
今日から始められる小さな探究を通じて、あの頃の好奇心と達成感を取り戻してみませんか。そして、もしお子さんがいらっしゃるなら、一緒に取り組むことで相互強化の効果も期待できます。
未来がどれほど不確実でも、自分で学び続ける力さえあれば道は開けます。「自由研究力」こそが、私たちの未来への最良の投資なのです。
*1 @DIME|「世の中の当たり前を疑うことからイノベーションが起きる」タイミー・小川嶺代表インタビュー【前編】
*2 マイナビキャリアリサーチLab|アントレプレナーシップとは?現代社会で求められる起業家精神
*3 文部科学省|高校生等へのアントレ教育の拡大について
*4 STUDY HACKER|「なぜ?」は人ではなくプロセスに向ける。成果に直結する「なぜなぜ分析」のコツ
*5 Bandura, A. (1977). Social Learning Theory. Prentice Hall
*6 Hoover-Dempsey, K. V., & Sandler, H. M. (1997). Why do parents become involved in their children's education? Review of Educational Research, 67(1), 3-42
STUDY HACKER 編集部
「STUDY HACKER」は、これからの学びを考える、勉強法のハッキングメディアです。「STUDY SMART」をコンセプトに、2014年のサイトオープン以後、効率的な勉強法 / 記憶に残るノート術 / 脳科学に基づく学習テクニック / 身になる読書術 / 文章術 / 思考法など、勉強・仕事に必要な知識やスキルをより合理的に身につけるためのヒントを、多数紹介しています。運営は、英語パーソナルジム「StudyHacker ENGLISH COMPANY」を手がける株式会社スタディーハッカー。

