
「効率よく仕事をこなして、もっと自分の時間を増やしたい」
「自分の行動を振り返ってみれば、無駄な時間が見つかるかも」
このように考えながらも、自分の時間の使い方の何が問題で、どう改善すればいいのかわからず途方に暮れていませんか?
もしかしたら、自分の視点だけでは本当に変えるべきポイントは見えてこないのかもしれません。
なぜなら誰しも自分の生活に潜む無駄な時間には気づきにくいものだからです。
そこで活用したいのが、ChatGPTを使ったコーチング型の振り返り。ChatGPTに行動記録を分析させることで、自分だけでは気づけなかった意外な改善点がクリアに見えてきます。
この記事では、ChatGPTを使った行動記録の分析方法を、実践を交えて詳しく紹介します。
そもそも「行動ログ」とは?
そもそも、「行動ログ」とはどのようなものなのでしょうか。
行動ログとは、自分の1日の過ごし方を記録したもの。
「何時から何時まで、どのような行動をしていたのか」を時系列でメモしていく方法が一般的です。
「朝活」の第一人者で、キャリアコンサルタントの池田千恵氏は、この行動ログを「時間簿」とよび、以下のように記録することをすすめています。
- 1週間だけ毎日記録する
- 15分単位で、行動したらその都度記録する
- 表計算ソフトなど使いやすいツールを使う
- 仕事だけでなく、プライベートの行動も記録する *1よりまとめた
行動ログを記録することで、自分の時間の使い方を客観的に振り返ることができ、無駄な時間の発見や、時間の使い方の改善につなげることができます。
特に、頑張りすぎてオーバーワーク気味になっている人にこそおすすめです。
池田氏は、「自分がやっている仕事の量やキャパがどのくらいかを正確に見積もることができてくると、1日の許容量をはるかに超えたタスクを設定することもなくな」ると語り、時間簿をつけ現状把握をすることの重要性を指摘しています。*1
時間の効率化を目指すなら、まずは現状把握をすることが大切なのです。
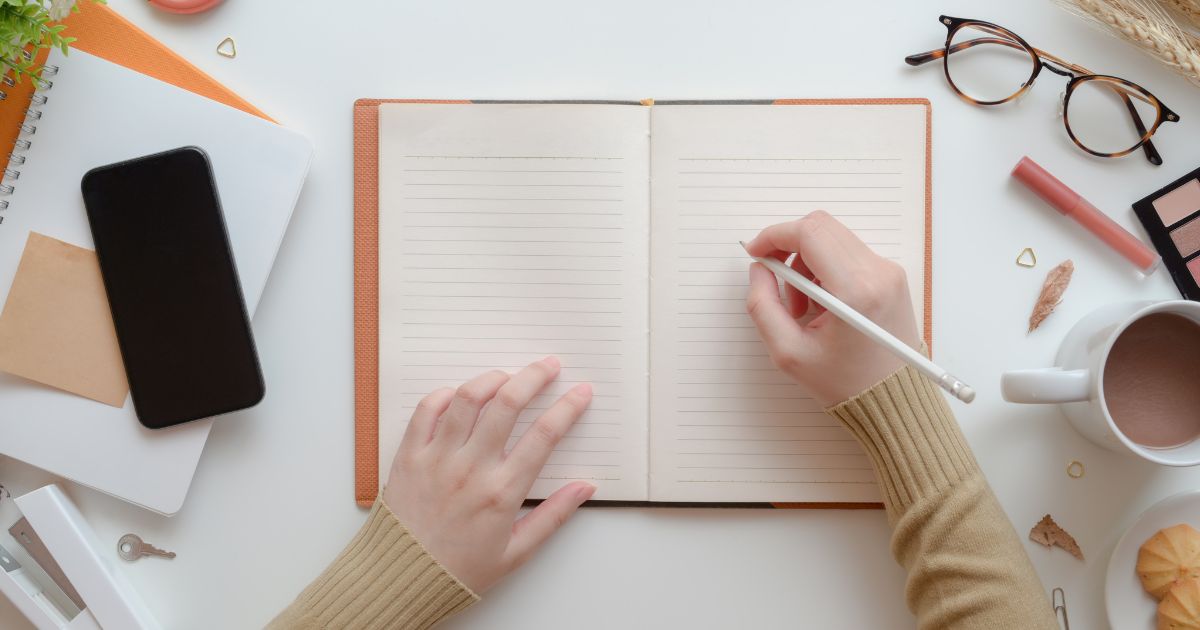
行動ログの分析に、なぜ「他者の視点」が必要なのか?
行動ログは記録するだけでなく、それを分析することが時間の効率化につながります。
記録をもとに、自分の時間の使い方にどんな傾向があるのか、どこに改善の余地があるのかを深掘りすることで、より効果的な時間の使い方を見つけることができるからです。
しかし、自分の視点だけでは、どこをどう変えたらいいのか見えてこないことも。
そんなときは、「行動ログを、他者に見てもらうこと」が打開策になります。
「自分の行動ログを分析する」とは、「自分自身を客観的に振り返り、その経験をこれからに活かす行為」とも言い換えられます。これはまさに内省そのもの。
リーダーシップや組織開発に関するコンサルティング活動を行なう、一般社団法人熊平セキュリティ財団 21世紀学び研究所 代表理事の熊平美香氏は、内省を行なう際には「1人で内省するのではなく、2人以上で行ったほうがより効果的」であると述べています。*2
その理由は、「強みは自分にとって簡単で当たり前のことだけに盲点となりがちで、内省しても気づけないことがあ」るから。*2
これは行動ログの分析にも言えるのではないでしょうか。
せっかく行動ログをつけてみても、普段の生活は自分にとって当たり前であるため、改善点が見えてこないものです。そこで、分析に他者の視点を取り入れれば、自分では気づけなかったボトルネックが見つかりやすくなるでしょう。
とはいえ、行動ログの分析のために毎回誰かに相談するのは現実的ではありません。友人や同僚、上司に相談するのは気が引けますし、コーチングには費用がかかります。
そこで、ChatGPTであれば気軽に相談でき、簡単にフィードバックを得られるというのが今回の提案です。次項から、その具体的な方法について解説していきます。

行動ログをChatGPTに分析してもらった
実際に筆者が、ある日の行動ログをChatGPTに分析してもらいました。
最近の筆者の悩みは、「リベンジ夜ふかし」がやめられないこと。
「リベンジ夜ふかし」とは、「日中に充実感や満足がないために、睡眠を削ってでも何かをして満足感を得ようとする行為のこと」を指します。*3
つい寝る前にスマホで漫画アプリをずっと見てしまい、そのせいで翌朝眠いという悪循環になっているため、リベンジ夜ふかしをやめることを目的に行動ログの分析を行ないました。
行動ログをテキストで用意
まずは、行動ログをテキストで用意しましょう。
筆者は、1日の行動をスマホのGoogle Keepに記録。
行動ログをアプリや手帳に書いている方は、写真を撮ってその画像を使用したいと思うでしょう。しかし、現状ではChatGPTで画像解析をすることは難しいようです。
そのため、行動ログはGoogle Keepなどメモアプリを使ってテキストで用意してください。
筆者は平日はほぼ似たようなスケジュールで動いているため、今回は1日だけの行動ログで分析を行ないました。
変則的なスケジュールで動いている、日によってモチベーションの変化を感じているという方は、数日間のログを分析させるといいかもしれません。

プロンプトを書き、分析させる
以下のプロンプトを書き、行動ログをコピーして貼り付け、分析させました。
プロンプトを入力する際に重要なのは、【分析の目的を示す】【特に見てほしいポイントを示す】の2点です。
<プロンプト>
以下の条件を元に、私の1日の行動ログを分析し、改善案を提案してください。
【分析の目的】
つい夜ふかしをしてしまうのを直したい。おそらく、日中の疲れやストレスを解消するために夜ふかしをしてしまっている。
【特に探してほしいポイント】
・効率化して時間のゆとりを作れそうな時間帯
・ストレスや疲れの原因になっている時間帯と、改善策
【1日の行動ログ】
【日付】2025年2月14日(金)
【行動ログ】
7:00〜8:30 朝の家事(洗濯・掃除・下ごしらえ)・朝食・身支度
8:30~10:00 今日の作業の確認・仕事用の勉強
10:00~11:30 仕事①(リサーチ・執筆など)
11:30〜11:45 休憩(ホットアイマスク)
11:45〜14:00 仕事①(執筆)
14:00〜14:10 休憩(トイレ、ラジオ体操)
14:10〜16:00 仕事①(執筆、加筆修正)
16:00〜16:30 退勤・休憩(スマホを見ていた)
16:30〜17:30 ウォーキング・筋トレ
17:30〜18:30 お風呂・スキンケアなど(中国語アプリをやった)
18:30〜19:30 料理・夕食
19:30〜20:30 休憩(録画したテレビを見ていた)、帰ってきた家族と過ごす
20:30~23:00 仕事②(制作)
23:00〜25:00 リラックス(マンガを読んでいた)
25:00 就寝
上記のプロンプトを受けて、ChatGPTの回答の一部がこちら。
1. 効率化して時間のゆとりを作れそうな時間帯
現在の行動ログから、 次の時間帯に効率化の余地がありそうです。
16:00~16:30 退勤・休憩 (スマホを見ていた)
- 分析
仕事が終わった直後の時間帯で、 疲れからダラダラとスマホを見てしまっている。
30分間のスマホ時間が、 その後のウォーキング・筋トレの開始時間を遅らせている可能性あり。
- 改善策
スマホを見ずにリフレッシュできる方法を試す
目を閉じて5分ほどリラックスする (昼のホットアイマスクのようなもの)
軽くストレッチをして気分転換
スマホではなく、ノートに「今日の仕事の振り返り」 を書き出す
2. ストレスや疲れの原因になっている時間帯
以下の時間帯が、ストレスや疲れの蓄積につながっている可能性があります。
14:10~16:00 仕事1 (執筆、加筆修正)
- 分析
昼休憩が短く、 午後の仕事にすぐ戻っている。
休憩が10分しかなく、長時間集中しているため、疲れが溜まりやすい。
午後の作業が長時間にわたるため、 16:00のスマホ休憩に流れてしまっている。
- 改善策
昼の休憩時間を少し延ばして、リフレッシュを増やす
たとえば、 14:00~14:30の間、 15分の休憩を取る (散歩・目を休める・ストレッチなど)。
休憩後の集中力を上げることで、 16:00の 「スマホだらけの休憩」を減らせる。
プロンプトで【特に見てほしいポイント】に指定した「効率化して時間のゆとりを作れそうな時間帯」と「ストレスや疲れの原因になっている時間帯」と、それぞれの改善策が具体的に示されました。
また、「夜ふかしを防ぐための具体的な改善プラン」も提案されました。
3. 夜ふかしを防ぐための具体的な改善プラン
以下のステップを試してみると、夜ふかしが減るかもしれません。
- 夜のリズムを整える
22:30までに仕事を終える (夜の仕事量を減らす or 軽めの作業にする)
23:00以降は「眠くなる習慣」を作る (マンガ読書やストレッチに変更)
スマホ・PCのブルーライトを減らす (ナイトモード設定)
- 日中の時間を効率化
16:00のスマホ時間を「短めの仕事」or「リラックス」に変更 午後の仕事の合間に、 15分の休憩を増やし、疲れを溜めない 朝の「仕事用の勉強」を一部制作に回し、 夜の負担を減らす
まとめ
夜ふかしの原因は「夜の仕事 + 刺激の強いリラックス時間」
改善策① 16:00のスマホ休憩を短縮し、 制作時間を分散する
改善策② 14:00 の昼休憩を少し延ばし、 午後の疲れを軽減
改善策③ 夜の仕事を22:30までに終え、 23:00以降は「眠くなる習慣」にする
これらを実践すると、 少しずつ夜ふかしを減らし、翌日のエネルギーを確保できるはずです! 試せそうなものがあれば、 ぜひ実践してみてください。
こうした分析が、ものの数秒で提供されました。

ChatGPTの分析から新しい視点を得た
ChatGPTの分析結果のなかから、筆者が参考になったものをいくつか紹介します。
- 22:30までに仕事を終える
ChatGPTは、筆者の20:30~23:00の過ごし方に夜更かしの原因があると指摘。
この時間帯に仕事をするのは避け、8:30~10:00の「仕事用の勉強」時間に仕事の一部を行ない、夜の仕事量を減らすことを提案されました。
- 仕事中の休憩を増やす
ChatGPTは、11:45〜16:00のあいだに10分間しか休憩がないため、そこで疲れやストレスが溜まっているのではと指摘。そのせいで、退勤後にスマホをずっと見てしまうのではと分析しています。
改善策として、10分間の昼休憩を少し延ばして、15分間程度の休憩を取ることを提案されました。
筆者の場合、日中にもう少し休憩を取り入れることで疲れを溜めずに行動でき、夜の仕事量を減らすことで23:00以降は眠くなる習慣をつけられるようです。
これであれば、リベンジ夜更かしをやめられる気がしてきました。
ChatGPTに分析してもらうことで「夜のタスクの負担を少し軽くするだけでいい」「昼休憩の時間を少し増やすだけでいい」という新しい視点を得ることができたのです。
これはまさに「他者の視点」を取り入れたからこその恩恵でしょう。
もちろんAI相手なので、現実には取り入れにくいアイデアが出てくることもありますが、変化のきっかけを得るには十分です。

***
行動ログはつけるだけでなく、適切に分析し、改善につなげることが重要です。
ChatGPTを活用すれば、客観的な視点で無駄な時間や改善点を見つけることができます。
「もっと効率よく働きたい」「時間を有効に使いたい」と思うなら、AIの力を借りて、行動ログを成長のためのツールに変えてみませんか。
*1 日本経済新聞|仕事がキャパ超えてない? 「時間簿」つけ朝活で分析
*2 リクナビNEXTジャーナル|内省とは?仕事やキャリアへのメリットや具体的なやり方を解説
*3 快眠手帖web|「リベンジ夜更かし」に気をつけましょう!
柴田香織
大学では心理学を専攻。常に独学で新しいことの学習にチャレンジしており、現在はIllustratorや中国語を勉強中。効率的な勉強法やノート術を日々実践しており、実際に高校3年分の日本史・世界史・地理の学び直しを1年間で完了した。自分で試して検証する実践報告記事が得意。

