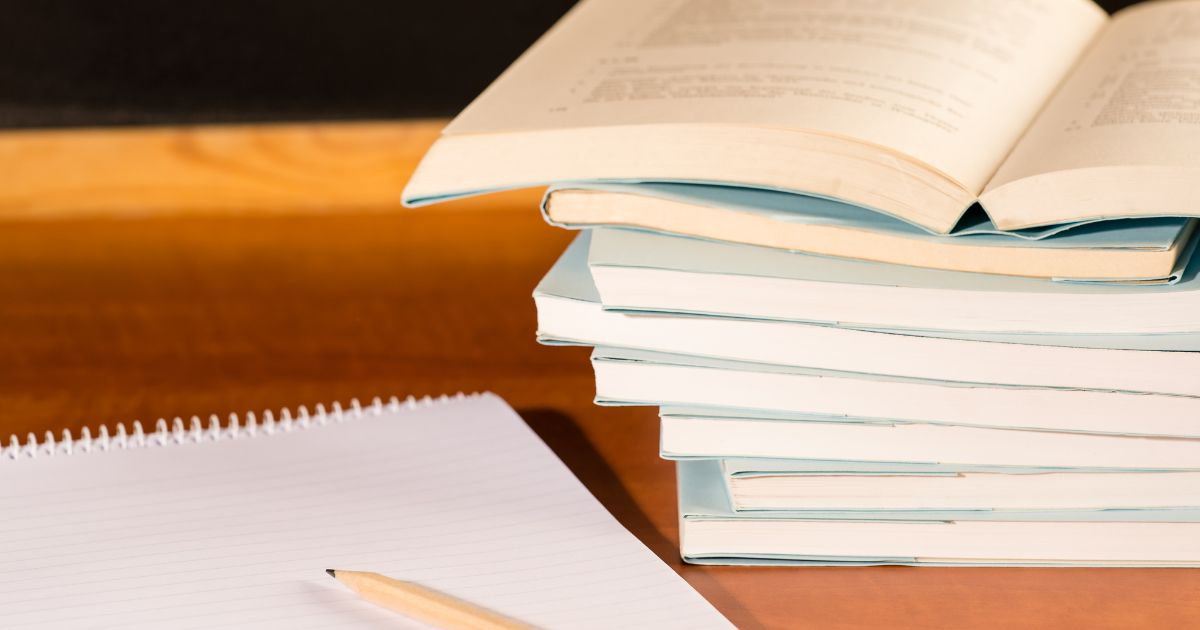
デスクに積まれているのは、先週末に読み終えたビジネス書。たしかに素晴らしい内容だったはず。でも、月曜のいま、具体的に何から始めればいいのか、何も思い浮かばない——。
「読んだ内容をどうやって仕事に活かせばよいのかわからない」
「本は読むけど、行動に移すのが苦手で、結局いつも同じ課題を抱えたまま」
こんなふうに悩んでいませんか? 多くのビジネスパーソンが「読書→実践」の壁に悩んでいます。せっかく貴重な時間をかけて読書しているのに、その学びが行動に結びつかなければ、もったいないですよね。
では、なぜ私たちは読書の学びを実践できないのでしょうか?そして、どうすれば読書を「確実な行動」に変えられるのでしょうか?
今回ご紹介する「ねぎま式読書ノート」は、単なる読書記録ではありません。ビジネス書の学びを確実に血肉化し、明日からの行動に直結させる具体的な方法です。筆者自身の実践例も交えながら、「読んで終わり」の読書から「読んだらすぐ実践」へと変わる方法をお伝えします。
読書の学びが「実践」につながらない理由
「本にいいことが書いてあったけど、どう活かせばよいかわからない」
この悩みを抱えるビジネスパーソンは決して少なくありません。そこで、多くの人が陥る「3つの落とし穴」を詳しく見ていきましょう。
❶ 読んだだけで「やった気」になってしまう
本を読むと「なるほど!」と納得し、頭の中でシミュレーションができます。この時、脳内では「理解=実行」という錯覚が起きています。心理学では、これを「理解の錯覚(Illusion of Understanding)」と呼びます。
例:時間管理の本を読んで「この方法、すごくいい!」と思っても、実際にスケジュールを変えなければ、時間の使い方は変わりません
📝読書の落とし穴は「インプットだけで満足してしまうこと」
❷ 抽象的な知識を具体的な行動に変換できていない
ビジネス書の多くは原理原則を説明していますが、「明日から何をすればいいのか」という具体的な行動指針までは示していないことがほとんどです。
例:マーケティングの本で「顧客視点が重要」と学んでも、「自分の担当している製品で、具体的に何をどう変えればいいのか」までは自分で考える必要がありす
📝「抽象から具体への変換」ができないと、知識は実践に結びつきません
❸ 知識と現実の間にある「実行ギャップ」
「やるべきこと」と「実際にやること」の間に大きなギャップがあります。
例:早起きの習慣化について書かれた本を読んでも、「朝5時起床」という習慣が現在の生活リズムとかけ離れていれば、実践は困難です
📝学んだことを「自分の状況に合わせて調整する」というステップが不可欠です
これら3つの壁が、私たちの「知る」と「行動する」を分断しています。では、どうすれば読書を「行動」に変えられるのでしょうか?
その効果的な解決策として「ねぎま式読書ノート」という方法があります。
ねぎま式読書ノートは学びを「行動」に変える最適なツール
ねぎま式読書ノートとは、単なる読書メモではなく「読んだ内容をしっかり記録し、後で振り返りやすくし、行動に移す」 ためのノート術のこと。ねぎま式読書ノートを考案したのは「読書は1冊のノートにまとめなさい」の著者で、元新聞記者の奥野宣之氏です。
名前の由来は 、焼き鳥のねぎま。以下のように、「本の抜き書き」と「自分のコメント」を交互に書くことで、情報が整理され、あとから見返したときに 「読むだけで学びがよみがえる」 ところがポイントです。

ここからは、ねぎま式読書ノートのつくり方をご紹介しましょう。*2
まずは、読書をする際に気になった箇所、学びになった箇所をペンでマーキングしておきます。 マーキングの方法をより詳しく知りたい方はこちらの記事もぜひご覧ください。
読書後に、事前に用意した読書ノートに基本情報を記録することから始めます。
📝 読書ノートの基本情報
・日付・本のタイトル
・著者名
この3点を書き残しておくことがファーストステップです。
📚 「ねぎま式」で記録する2つの情報
さらに以下のふたつの情報を追加します。・本からの抜き書き
・その文章に対する自分の感想
このふたつの情報を「ねぎま焼き」のように交互に書いていきます。
✍️ 具体的な書き方
1. 読書時にマーキングしておいた箇所から、厳選した文章を抜き書きする2. その文章に対するコメントを書く
3. 抜き書きには[〇]、自分の言葉には[☆]をそれぞれ付ける
4. これらを交互に書いていく
抜き書きとコメントを交互に書く理由について奥野氏は「書き写した印象が鮮明なうちに、感想を書きたいから」と述べています。*2
これは、脳の仕組み的にも理にかなっています。人の脳は、新しい情報を得たあと、数時間以内に自分の頭で考えたり整理したりする(=能動的に処理する)ことで、その情報を長く覚えていられるようになります。*3 さらに、自分の言葉でコメントを書くという行為は、ただ「分かった気になる」だけで終わらず、内容を深く理解したり、「自分ならどう使えるか?」と考えたりするきっかけになります。
こうしてすぐにアウトプットをすると、本の内容が知識として残るだけでなく、自分の考えの一部として、日々の行動や判断にも生かしやすくなるのです。
筆者も実際に「ねぎま式読書ノート」を試してみた!
実は筆者も読書をして「確かに!」「これはいい学びになった!」などそのときは感動や感想があるにもかかわらず、すぐに忘れてしまい、学びをまったく活かせていないことが悩みでした。
そこで「ねぎま式読書ノート」に挑戦してみました。今回読んだのは、『イシューからはじめよ――知的生産の「シンプルな本質」』です。

ノートに書き出した内容を部分的に抜き出してみます。
◯「悩む」=「答えが出ない」という前提のもとに、「考えるフリ」をすること
「考える」=「答えが出る」という前提のもとに、建設的に考えて組み立てること *4
☆他者の話を聞く際に「この人は悩んでいるのか? それとも考えたいのか?」を見極めることも大切。ただ悩みたいだけでアドバイスなど必要としておらず、愚痴りたい・話を聞いてほしいだけの人もいる。自分はどうか? 「考えているか?」を意識しよう。
🔍 実践してわかったこと
・「読んだだけで『やった気』になる」への対策実際に書き出してみて、具体性のない感想が多いことに気づきました。「自分の考えを深めようとする習慣」に欠けていたと思います。
また、ねぎま式では抜き書きした内容に対して必ず自分の考えを書くため、「理解の錯覚」に陥りにくいと感じました。
たとえば、「悩む」と「考える」の違いを読んだ際、以前なら「なるほど」で終わりでしたが、今回は「では自分はどうか? どう実践すべきか?」という具体的な思考に発展させることができました。
・思考の整理と課題の発見
抜き書きによって、自分が本当に大切にしている部分や関心がどこにあるのかが明確になりました。また、読書内容に対する自分の反応を書くことで、自分の課題や改善すべき点が見えてきました。
✨ 実践して感じたメリット
・「どの部分が自分にとって重要だったか」が一目でわかり、効果的な振り返りができる・「インプットで満足」せず、読んだ内容を自分の言葉で表現することで、理解が深まる
・抜き書きとコメントを交互に書くことで、抽象的な知識を具体的な行動指針に変換できる
・自分の考えの記録が残り、自分の課題を明確化できる
💡 継続するためのコツ
・ハードルを上げすぎず、毎日5分でも実践する・感想もはじめからきちんと書こうとせず、気楽に書く
・自分のペースで無理なく続けることを優先する
***
「読書をしても身につかない……」と悩んでいる人は、ぜひ、ねぎま式読書ノートを試してみてください。これまでとは違い、学びが実践につながるのを実感できるはずです。
*1 奥野宜之(2013),『読書は1冊のノートにまとめなささい[完全版]』, ダイヤモンド社.
*2 ダイヤモンド・オンライン|本を読みっぱなしにしない!確実に自分の血肉にする5つの技術
*3 McGaugh, J. L. (2000). Memory—a century of consolidation. Science, 287(5451), 248-251.
*4 安宅和人(2010),『イシューからはじめよ――知的生産の「シンプルな本質」』, 英治出版.
橋本麻理香
大学では経営学を専攻。13年間の演劇経験から非言語コミュニケーションの知見があり、仕事での信頼関係の構築に役立てている。思考法や勉強法への関心が高く、最近はシステム思考を取り入れ、多角的な視点で仕事や勉強における課題を根本から解決している。

