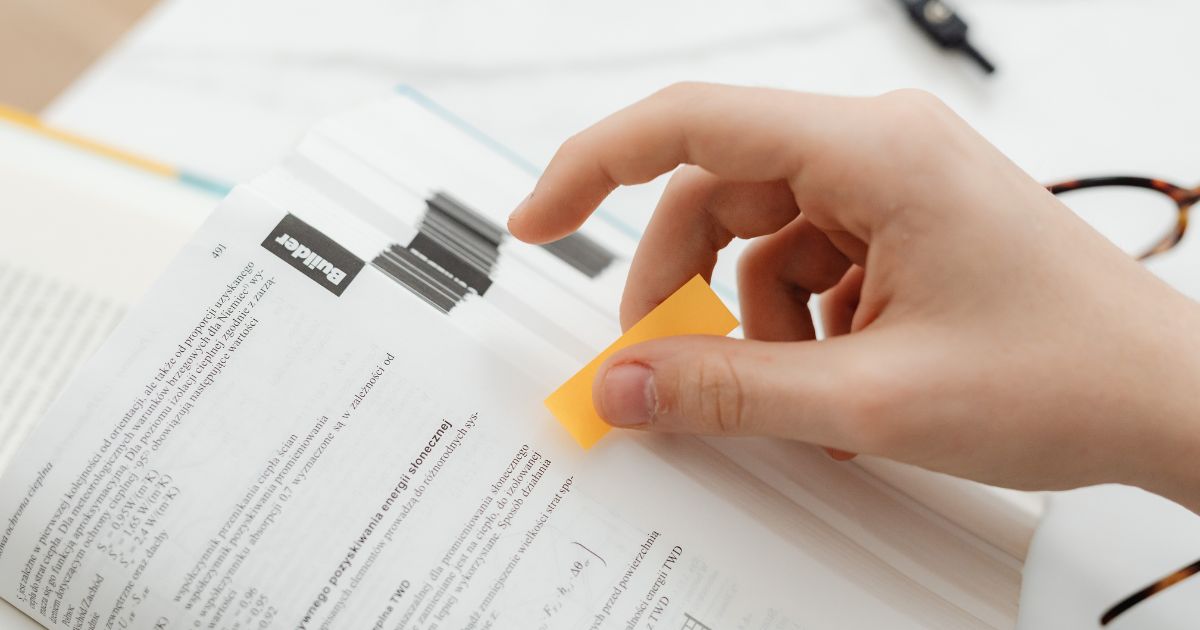
「スキマ時間にどのような勉強をすればいいのかわからない」
「スキマ時間といっても数分しかない」
仕事をしながら勉強をするために「スキマ時間」を有効活用しなければならないのは周知の事実でしょう。
しかし、実際にスキマ時間を手にしたときに、なにをどのように勉強すればいいのかわからない方もいるのではないでしょうか。
この記事では、スキマ時間をうまく使っている人が絶対にしない3つの行動を紹介します。
しないことを決めるだけで、勉強効率がぐんと上がるはず。
ぜひ参考にしてみてください。
- 数分であっても「スキマ時間」として活用できる
- しないこと1. 「事前準備の軽視」
- しないこと2. 「理解できるまで粘る」
- しないこと3. 「完璧主義の読書」
- しないことを決めると、勉強はもっとラクになる
数分であっても「スキマ時間」として活用できる
仕事をしながら勉強するのは時間との戦いです。
勉強しようと思っていても、「今日はもう時間がないから、明日にしよう……」と、後回しにしてしまうこともあるかもしれません。
しかし、「スキマ時間すらない」と感じている人は、「“スキマ” とはいえ、20分くらいはないと勉強なんてできない」というように、スキマ時間のハードルを上げていないでしょうか?
しかし、以下のようにスキマ時間を有効活用するための原則を押さえておけば、ほんの数分だとしても勉強はできます。
- スキマ時間用の勉強の準備をしておく
- わからないところは一旦保留にして、勉強を進める
- テキストは大枠を把握してから、必要な箇所を重点的に読む
ほんの数分でも「スキマ時間」は「スキマ時間」です。
その具体的な使い方について、次の項から説明していきます。

しないこと1. 「事前準備の軽視」
電車が遅延して、急に15分の空き時間ができたAさん。
「せっかくだから勉強しよう」と思ったものの、なにをするか迷っているうちに目的地に到着し、そのまま改札へ――。そんな経験、心当たりがある方も多いのではないでしょうか。
スキマ時間は、前触れなく突然訪れることも少なくありません。
Aさんのように、その場で「何をしようかな……」と迷ってしまうと、せっかくの時間を活かしきれずに終わってしまいます。
だからこそ、スキマ時間がいつ・どんな形で現れても困らないように、ちょっとした“ゆるい準備”をしておくのがおすすめです。
たとえば、時間の長さや場所に応じて「これならできそう」という行動を、ざっくりと決めておく。
社員研修などを手がけるイントランスHRMソリューションズ株式会社の竹村孝宏氏は、スキマ時間を活用するために「『5分でできる作業』『10分でできる作業』『30分でできる作業』に振り分けている」と語っています。*1
この考え方を参考に、筆者も以下のように簡単に振り分けています。
【5分でできる勉強】
- 参考書を1ページだけ読む
- 確認問題を1問だけ解く
- テキストの余白にメモした内容を見直す
【10分でできる勉強】
- 理解に時間がかかっている勉強内容について、インターネットで調べる
- 勉強内容に関連するPodcastを1つ聞く
【30分でできる勉強】
- 紙に書き出しながら勉強した内容を整理する
- 参考書やテキストを使って理解を深める
このように、することを事前に決めておけばすぐに勉強を始められるので、時間に無駄がありません。
さらに、次のような工夫もおすすめです。
- 覚えたい内容をボイスメモに録音しておく
- 見直したい箇所の写真をスマートフォンで撮っておく
満員電車など空間に余裕がないときは、録音したボイスメモを聞くようにしています
また、勉強したい箇所の写真を撮っておけば分厚いテキストを持ち歩かずにすみます。
突発的に発生したスキマ時間のチャンスをしっかりつかむためには、事前準備が欠かせないのです。
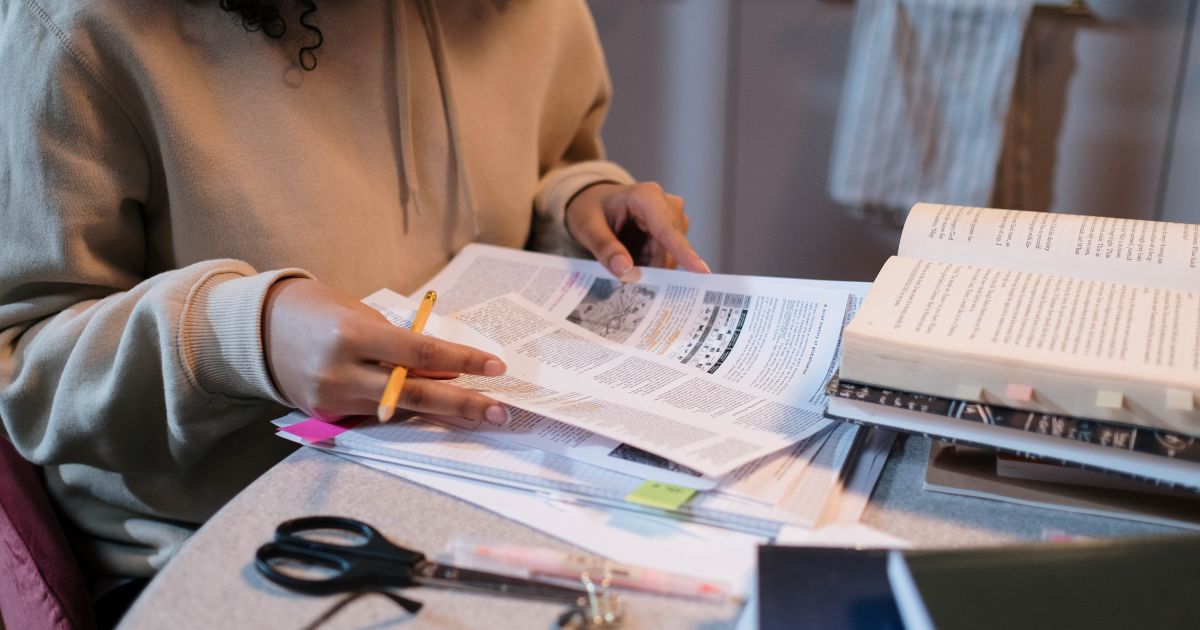
しないこと2. 「理解できるまで粘る」
30分のスキマ時間ができたので、資格の勉強を始めたBさん。
難解な箇所にぶつかり、先に進めないまま時間が経過してしまいました。
「結局なにもできず、フラストレーションがたまっただけだった」と落ち込んでしまいます。
Bさんのように「しっかり理解しよう」という姿勢は素晴らしいですが、限られた時間を有効に使うためには、状況に応じた戦略的なアプローチも大切です。
せっかくスキマ時間に勉強に取り組めたとしても、その時間に見合った進捗がなければ、もったいないと言わざるを得ません。
理解に行き詰まったときは一旦保留にし、次に進んでみましょう。
ビジネスマン向けの学習サポートなどを行なうトレスペクト教育研究所代表の宇都出雅巳氏は問題集を例に挙げ、「『楽に読める部分』から少しずつ読んでい」けば、「それらが潜在記憶となり、次に読むときの理解を助けてくれ」ると言います。*2
スキマ時間に効率よく勉強を進めるためには、こういった「脳の特性」を味方につけることも大切です。

しないこと3. 「完璧主義の読書」
資格取得を目指して勉強に励むCさんは、「テキストを1ページ目から丁寧に読んで、完璧に理解しよう!」と頑張っています。
しかし、時間ばかりかかり、なかなか問題演習までたどり着きません。
「要領が悪いのは、頭が悪いせいかもしれない」と落ち込んでしまいます。
Cさんの問題点はふたつ。
ひとつめは、「資格取得」という目的で勉強を始めたはずが、「完璧な理解」という目標にすり替わってしまったこと。
ふたつめは、目的がすり替わってしまったがために、勉強のアプローチを間違えたこと。
資格取得が目的であれば、合格点に到達できれば問題ありません。
限られた時間で目的を達成するならば、「合格」に焦点を当てたアプローチが必要です。
資格試験対策をオンラインで提供する「資格スクエア」創業者の鬼頭政人氏は、「勉強を始める前に、合格までの最短コースを調べて自分なりにそれを理解してから勉強を始める」べきだと主張します。*3
Cさんで言えば、次のような勉強の計画ができたのではないでしょうか。
- テキストの目次や太字部分などに一通り目をとおし、自分の理解度に合わせて勉強を進める
- 過去数年分の試験問題を分析し、頻出分野や出題傾向を把握する
- 把握した大枠に基づいて細部の勉強を進める
勉強を始める前に、アプローチを考える必要があったのです。
株式会社カルペ・ディエム代表取締役社長の西岡壱誠氏は、テキストや参考書を読むときは「なんとなく全体の枠組みを把握すれば十分」で、枠組みを把握できれば「理解できなかったところ」「気になるところ」「重要だと思うところ」が明確になり、明確になったこれらのポイントを意識しながら再度読むことで、理解や記憶が深まると言います。*4
テキストや参考書などを読むときは、まずは大枠を把握してから細部の勉強をしていくことが大切なのです。

しないことを決めると、勉強はもっとラクになる
スキマ時間を活用して勉強する人は、時間も場所も環境も限られたなかで、「できることだけする」と割りきっています。
だからこそ、無駄なエネルギーを使わずに継続でき、効率よく成果を上げ続けられるのです。
「スキマ時間をうまく使えない」「思うように進まない」と感じるのであれば、まずしないことを決めてみましょう。
完璧主義を手放せば、勉強はもっと気楽に、そして着実に続けられるようになります。

***
スキマ時間の活用は未来への投資とも言えます。今回ご紹介した「しないこと3選」を参考にスキマ時間をとらえ直し、さらに効率よく知識を蓄えていきませんか?
※引用の太字は編集部が施した
*1 日経クロステック|スキマ時間を効果的に活用するコツ
*2 STUDY HACKER|理解が進んで記憶に残る! 勉強法の専門家が説く「頑張らない」勉強法
*3 東洋経済オンライン|資格試験「落ちる人」「受かる人」の参考書の使い方
*4 STUDY HACKER|「高速回転数勉強法」と「さかさ勉強法」で記憶を強化する! 超効率的な本の読み方

