
DMNとは、デフォルト・モード・ネットワーク(Default Mode Network)の略語。ぼんやりした状態の脳が行なっている神経活動のことです。
近年の脳科学研究により、DMNの働きは「創造性」と関係していることがわかっています。DMNが活発になると創造力が高まり、いろいろなアイデアが浮かんできやすいのです。
一方、DMNの活発化には、「考えすぎ」による脳疲労のデメリットも。メリットとデメリットの両方を把握したうえで、DMNの「スイッチ」を適切に切り替える必要があるのです。
今回は、DMNの役割を説明したあと、DMNのオン/オフを切り替える方法をご紹介します。瞑想や運動など、難しくないものばかりです。ぜひあなたも、自身のDMNをうまく活用してみてください。
- DMN(デフォルトモードネットワーク)とは
- DMN(デフォルトモードネットワーク)が活性化しすぎると……
- DMN(デフォルトモードネットワーク)を活性化させる方法
- DMN(デフォルトモードネットワーク)を不活性化させる方法
DMN(デフォルトモードネットワーク)とは
DMNとは、脳が意識的な活動をしていないとき、つまり、ぼんやりしているときに活性化する神経回路です。医師の伊藤豊氏によると、脳の「内側前頭前野」「後帯状皮質」「楔前部(けつぜんぶ)」「下頭頂小葉」といった部位で構成されているのだそう。
ぼーっと散歩しているときや、コーヒーを飲んで一息ついているとき、とりとめもないことを考えながらシャワーを浴びているときなどに、DMNは活発化しています。反対に、何かに集中しているときには非活性状態なのです。
DMNの主な役割には、「危機への備え」と「情報の整理」があります。
DMNの役割1:危機への備え
DMNは、自動車の「アイドリング状態」に例えられます。車のエンジンを完全に切ってしまうと、再び発車させるのに時間がかかりますが、アイドリング状態ならアクセルを踏むだけですぐに発車できますよね。
DMNも同じです。脳が完全に休んでしまうと、突然の危機に反応しづらいため、脳の一部(DMN)を待機状態にして万が一に備えています。
DMNの役割2:情報の整理
脳神経外科医の奥村歩氏によると、脳は以下のプロセスで情報を処理しているのだそう。
- 入力:五感を通して情報を収集する
- 整理:入力した情報を取捨選択する
- 出力:言葉や行動として表す
DMNが重要になるのは、2番目の「整理」段階です。DMNの働きが弱いと、脳内で情報が整理されず、ぐちゃぐちゃに散らかったデスクのような「脳過労」状態に。インプットした情報が脳に定着しづらくなったり、脳の活動自体が低下したりといった恐れがあります。
しかし、DMNが正常に働いていれば、脳内の情報がスッキリと整理されます。また、蓄えられた情報がそれぞれ結びつきやすくなり、新しいアイデアが生まれるというメリットも。つまり、DMNが活性化すると、創造力が高まるのです。
余談ですが、11世紀の中国の文学者・欧陽脩(おうようしゅう)は、文章を考えるのに最も適した場面として「三上」を挙げています。
- 馬上:馬の上
- 枕上:布団の上
- 厠上:トイレの上
もちろん、欧陽脩はDMNの存在など知らなかったはず。しかし、「ぼんやりできる場所では、いいアイデアが生まれやすい」ということを、経験から理解していたのですね。

DMN(デフォルトモードネットワーク)が活性化しすぎると……
DMNのおかげで創造力が高まるとわかりました。しかし、メリットばかりではありません。
DMNが活性化しすぎると、頭がぼんやりして注意力が散漫になってしまいます。それに、余計なことを考えすぎて、不安にさいなまれることも。
また、前出の伊藤氏によると、DMNは脳の総エネルギーの60~80%を占める「大食漢」。DMNを働かせすぎると、脳のエネルギーが底を尽き、疲れを感じやすくなってしまうのだそうです。
そのため、休みの日などに一日中ぼーっとしていると、脳が休まるどころか疲れてしまう恐れがあります。DMNが酷使され、脳のエネルギーがどんどん奪われているからです。
ちなみに、自動車を何時間もアイドリング状態にしていると、熱がこもったりバッテリーが傷んだりしやすいのだとか。脳に関しても同じことが言えるのです。
DMNが活発な状態と活発でない状態には、それぞれメリットとデメリットがあります。両方を理解したうえで、DMNの「オン」と「オフ」を切り替える必要があるのです。
【DMNが「オン」状態のメリット】
- アイデアが生まれやすい
- リラックスできる
- 脳内の情報が整理される
【DMNが「オン」状態のデメリット】
- 注意が散漫になりがち
- 脳が疲れやすい
- ネガティブ感情に支配されてしまうことも
【DMNが「オフ」状態のメリット】
- 集中力が高まる
- 脳のエネルギー消費を抑えられる
- ネガティブ思考になりにくい
【DMNが「オフ」状態のデメリット】
- 思考が柔軟になりにくい
- 脳内の情報が整理されず、記憶能力などに悪影響が及ぶ可能性も
では、DMNのオン/オフを切り替える具体的な方法を学んでいきましょう。
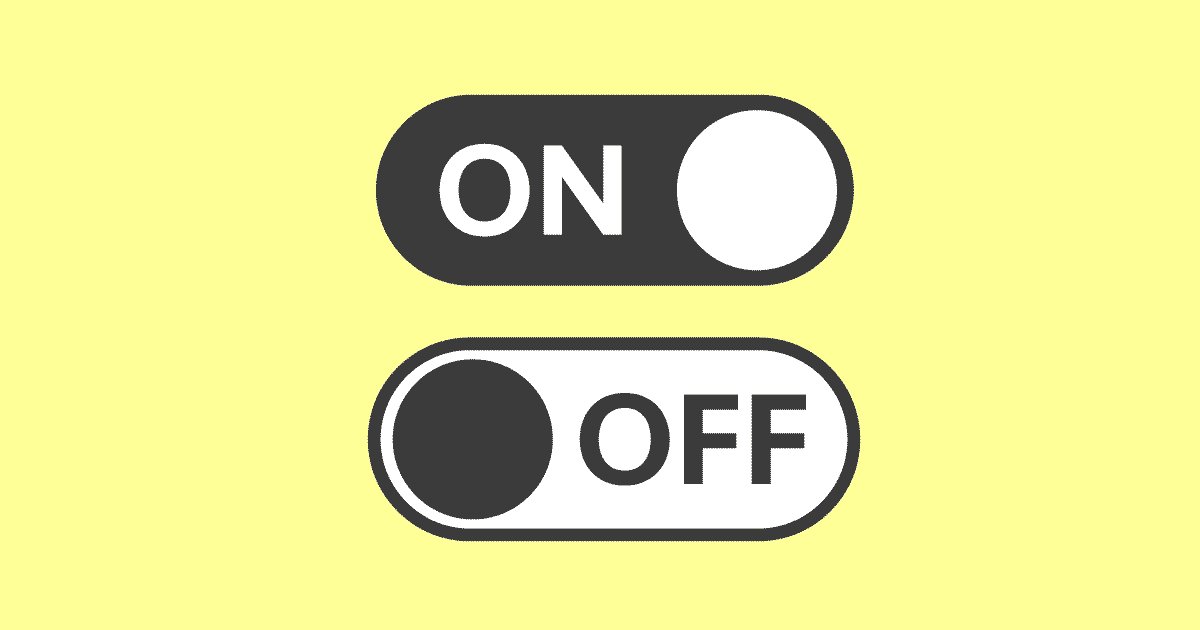
DMN(デフォルトモードネットワーク)を活性化させる方法
DMNが活性化すると、脳内に蓄積された情報が自在に結びつきやすくなるため、創造力や発想力の向上が期待できます。脳内にたまった情報をスッキリと片づけ、脳疲労を防ぐためにも、DMNをオンにすることは重要です。
以下では、DMNを活性化する方法を5つ紹介します。
観察瞑想
DMNのオン/オフを切り替えるのには、瞑想が有効です。
予防医学研究者の石川善樹氏によると、瞑想は「集中瞑想」と「観察瞑想」に大別できます。集中瞑想とは、自分の呼吸や身体の一部に意識を集中させる、一般的な瞑想のイメージ(いわゆる精神統一)に近いものです。
一方の観察瞑想では、無理に集中しようとせず、瞑想中に浮かんでくる感情や雑念をありのままに観察します。DMNの活性化に適しているのは、この観察瞑想です。石川氏の解説に従い、「調身」「調息」「調心」という3つのステップで、観察瞑想の実践方法をご紹介しましょう。
1. 調身:背筋を伸ばしつつ、力を抜く
調身とは、身体の姿勢を整えること。背筋が自然に伸び、余計な力が入っていない状態が理想的です。背筋さえ伸びていれば、座禅のようにあぐらをかいてもいいし、椅子に座ってもよいとのこと。
正しい姿勢をつくるには、まず肩をすくめるように力を入れてから、脱力してストンと肩を落としてみてください。背筋が楽に伸びた、理想的な姿勢が出来上がるはずです。
2. 調息:5秒かけて息を吸い、10~15秒かけて吐く
呼吸は精神状態と密接に関連しています。石川氏によると、息を吸っているときは、身体を活動モードにする「交感神経」が優位になり、吐くときには、身体を休息モードにする「副交感神経」が優位になる傾向があるのだそう。
瞑想では、「吐く息」のほうを長くし、心を落ち着けます。「5秒かけて息を吸う→10~15秒かけてゆっくり吐く」というリズムを守り、なるべく深く呼吸するよう意識してください。
3. 調心:感情・思考を観察する
準備が整ったら、瞑想の肝である「調心」に移りましょう。心をなるべく弛緩(しかん)させて、とりとめのない思考や感情の動きに身を委ねることを目指します。
観察瞑想では、心を無にしようと努めたり、雑念を消そうと頑張ったりする必要はありません。「夕飯に何を食べようかな」「あとで本屋に行きたいな」などのとりとめもない思考・感情が生まれたら、「こんな雑念が浮かんだな」と客観的に観察しましょう。すると、意識が何にも縛られず自由に発散する状態がつくられ、DMNが活性化していくのです。
PCD(楽しい空想)
瞑想よりも手軽なのが「空想」です。医学博士のスリニ・ピレイ氏によると、特に楽しい気分になれる空想をPCD(Positive Constructive Daydreaming、ポジティブで建設的な空想)と呼びます。PCDには、脳の集中状態を解除し、心を緩める効果的が期待できるのだそうです。
- 森のなかを駆け回る空想
- ヨットの上で寝そべる空想
- きれいな砂浜に座って、ぼんやりと海を眺めている空想
など、自分なりに心地よくなれる想像をし、心の世界をさまよってみましょう。シーンを思い描く過程で、脳内に眠っているさまざまな記憶が呼び起こされ、DMNの活性化につながります。
ピレイ氏によると、編み物や園芸、読書など「ちょっとした気晴らしになる活動」は、自分の心の内部へ向かう「準備運動」の役割をするため、PCDをスムーズにしてくれるのだそう。空想のシーンを思い描くのが難しければ、旅行や自然に関する映像を見てイメージを膨らませてもいいでしょう。
デジタルデトックス
私たちが日常的に使っているスマートフォンは、DMNの働きを妨げてしまいます。脳神経学者の枝川義邦氏によると、スマートフォンの画面は強い光を発し、色彩の情報量が多いこともあって、脳が疲れやすいのだそう。
特に、仕事の休憩時間にスマートフォンを見てしまうと、DMNが活性化しない(ぼんやりできない)ため、息抜きするどころか疲れを余計にためてしまいます。脳疲労を避けるには、スマートフォンを使う時間を管理し、DMNを意識的に活性化させる必要があるのです。
デジタル機器を遠ざけ、心身のリフレッシュを図ることは「デジタルデトックス」と呼ばれます。最もシンプルなデジタルデトックスは、スマートフォンにもとから備わっている機能やダウンロードしたアプリケーションを使い、スマートフォンの使用時間を制限すること。
たとえば、iPhoneには「スクリーンタイム」という機能があります。「22:00~翌9:00はSNSのアプリケーションを使えない」というように、時間や種類を指定してアプリケーションの使用を制限できるのです。同様の機能は、ほとんどのスマートフォンに搭載されているはず。
デジタルデトックスのためのアプリケーションとしては、「Flipd」(iOS/Android)があります。スクリーンタイムと同様、時間やアプリケーションを指定して、使用を強制的に禁止するものです。また、スマートフォンを使わなかった時間に応じて樹木が成長していく「Forest」(iOS/Android)のように、ゲーム感覚でデジタルデトックスできるアプリケーションも。
本格的にデジタルデトックスしたい方におすすめなのが、各種団体や宿泊施設が運営する「デジタルデトックスツアー」。スマートフォンを使えないよう預けたうえで、レジャーなどを楽しみます。
【デジタルデトックスの例】
- スマホの機能を使い、使用を制限する
- 専用アプリやグッズを使い、スマホの使用を制限する
- デジタルデトックスツアーに参加する
さらに詳しく知りたい方は、「デジタルデトックスをやってみよう! 自宅・キャンプなど方法6選」をご覧ください。
単純な作業・運動
前出の枝川氏は、皿洗いや散歩といった単純な作業・運動も推奨しています。あまり頭を使わない単純作業をしていると、自然とぼんやりした状態になれ、DMNが活性化するのです。
掃除や靴磨き、洗濯物干しなど、単純な動きを繰り返す作業ならなんでもOKです。運動の場合も、リズミカルに長時間続けられるものがオススメ。
【DMNを活性化させる作業・リズム運動の例】
- 皿洗い
- 掃除
- 靴磨き
- 洗濯物干し
- 散歩
- ゴルフの素振り
- スクワット
- 踏み台昇降
パワーナップ
DMNは、睡眠中にも活性化します。枝川氏によると、15分程度の昼寝や、椅子に座ったまま目を閉じているだけでもいいのだそう。
近年、生産性を高めるための昼寝を指す「パワーナップ」という考えも知られつつありますね。社会心理学者のジェームス・マース氏が提唱したものです。パワーナップは、GoogleやAppleといった世界的IT企業をはじめ、三菱地所など一部の日本企業でも導入されつつあります。
医師の末松義弘氏によると、パワーナップのポイントは以下のとおり。
- 時間は15~30分以内 :
あまり長いと、眠りが深くなりすぎて目覚めが悪くなる - 事前にカフェインをとる:
カフェインの効果が現れるまで30分ほど要するため、パワーナップが終わる頃にちょうど効いてくる - 午後4時以降は禁止:
夜のまとまった睡眠を妨げてしまう
パワーナップをすると、DMNが活性化されるだけでなく、午後の仕事のパフォーマンスも上がるはずです。

DMN(デフォルトモードネットワーク)を不活性化させる方法
DMNの活動を抑制するべき場合もあります。DMNがオンのままだと、脳のエネルギーがどんどん消費されていくためです。また、DMNが「暴走状態」になると、過去の嫌な記憶や将来への不安が次から次に湧いてきてしまいます。
そのため、仕事や勉強に集中したいなら、DMNの活動を抑制することが必要です。4つの方法をご紹介しましょう。
集中瞑想
DMNを活性化させる方法として「観察瞑想」を紹介しましたが、DMNを抑制したいときには「集中瞑想」が有効です。集中瞑想では、自分の呼吸や身体の一部分に意識を向けます。観察瞑想と異なり、雑念をシャットアウトして精神を研ぎ澄ます感覚です。
再び石川氏の知見に基づき、集中瞑想のやり方を3ステップでご紹介します。観察瞑想と同じく「調身」「調息」「調心」で成り立っていますが、「調心」における心の使い方がまったく異なるので注意してください。
1. 調身:背筋を伸ばしつつ、力を抜く
まずは、姿勢を整えます。観察瞑想と同じく、背筋がまっすぐ伸びながらも、余計な力が入っていないのが理想的です。肩をすくめるように力を入れたあと、ストンと脱力することで、正しい姿勢をつくってください。
2. 調息:5秒かけて息を吸い、10~15秒かけて吐く
呼吸を整えます。これも観察瞑想と同様、「吐く息」のほうを長めにすることで、副交感神経を刺激し、心を安らかな状態にしていきましょう。「5秒かけて息を吸う→10~15秒かけてゆっくり吐く」のリズムで、ゆったりと呼吸してください。
3. 調心:呼吸に集中する
「調心」では、自分の呼吸に全神経を集中させます。「5秒かけて息を吸う→10~15秒かけてゆっくり吐く」をキープしながら、鼻を通り抜ける息の感触や、膨らんだりしぼんだりする肺の感覚などに意識を向けてください。
雑念が浮かんできたり、呼吸から注意がそれたりしても焦らず、呼吸に注意を戻しましょう。うまくいかなくても、いら立ちは禁物。雑念を100%消すのは難しいかもしれませんが、呼吸に意識を留めようと努めることで、しだいにDMNの働きが抑制されてくるはずです。
歩行瞑想
『世界のエリートがやっている最高の休息法』(ダイヤモンド社、2016年)を著した医師の久賀谷亮氏は、「歩行瞑想」という方法を紹介しています。呼吸ではなく「歩行の動作」に集中することで、DMNの抑制を目指すものです。
歩行瞑想といっても、歩き方そのものは普段通り。ただし、歩行にともなう動作のひとつひとつに対し、並々ならぬ注意を向けていきます。
- 手脚を上げたときの、筋肉や関節の動き
- 足の裏が地面に着く感触
- 地面を蹴って前に進む感覚
などを、ひとつひとつ細かく感じてください。慣れないうちは、亀のようにゆっくりとしたスピードで歩くとやりやすいでしょう。
注意がそれてしまう場合は、「右、左、右、左」「上げる、下げる、上げる、下げる」などと口に出すとよいのだそう。慣れてしまえば、通勤中や散歩中にできる便利な瞑想なので、ぜひ覚えてみてくださいね。
食事瞑想
久賀谷氏は、「食事瞑想」という方法もすすめています。食事におけるひとつひとつの動作を注意深く行なうことで、DMNの抑制を目指すものです。歩行瞑想の “食事バージョン” だと言えるでしょう。
- 箸で食べ物をつかむ動作・感触
- 食べ物が口に入る感触
- 食べ物をかみ砕く感触
- 食べ物を飲み込む感触
など、各動作に全神経を傾けてください。しだいに意識が研ぎ澄まされ、心が落ち着いてくるのを感じられるはずです。慣れないうちは、動作をゆっくりにしたり、「つかむ」「かむ」と動作を口に出したりして、ひとつひとつの動作を確実に認識しましょう。
久賀谷氏によると、食事瞑想・歩行瞑想に限らず、日常のあらゆる動作は瞑想の材料になるのだそう。「歯磨きをする」「服を着る」など、毎日の生活の延長線上で瞑想をやってみてはいかがでしょうか。
雑念のコントロール
最後にご紹介するのは、DMNが暴走し、雑念や不安が収まらなくなってしまった場合の対処法。日常生活や瞑想において雑念が生まれ、どうしても集中できなくなったときに使います。
以下に挙げる5つは、久賀谷氏が提唱する、雑念・不安の払い方です。
- 捨てる:
心のなかで「もう十分!」と叫び、雑念を頭の外に放り捨てる様子をイメージする - 例外を考える:
心配事が当てはまらないケースを想像する - 賢者の目線で考える:
自分が尊敬する人や歴史上の偉人なら、問題をどう解決するか想像する - 善し悪しで判断するのをやめる:
雑念や心配事について「善い」とも「悪い」とも判断せず、中立に考える - 由来を探る:
なぜその考えにとらわれてしまうのか、原因を考える
5パターンの自己対話を通じ、雑念を封じ込めるコツがつかめれば、DMNをコントロールしやすくなるはずです。
***
DMNは、脳のポテンシャルを最大限に引き出すのカギ。休んだつもりでも疲れがとれない方や、頭がうまく働かない日が多い方は、今回ご紹介した方法を実践してみてくださいね。
伊藤豊(2018),『現役医師が教える 中村天風哲学 最強のマインド・フルネス』, ロングセラーズ.
NHK|“スマホ脳過労” 記憶力や意欲が低下!?
コトバンク|三上
石川善樹(2016),『疲れない脳をつくる生活習慣』, プレジデント社.
DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー|集中力をコントロールして、創造力を発揮する3つの方法
Apple サポート|iPhone、iPad、iPod touch でスクリーンタイムを使う
App Store|Flipd: Focus & Productivity
Google Play|Forest:スマホ中毒の解決法
NIKKEI STYLE|いつもスマホが招く脳過労 物忘れが増えたら要注意
幻冬舎ゴールドオンライン|寝る前に「カフェイン」を…医師が教える「上手な昼寝」の方法
Business Insider Japan|三菱地所が導入した仮眠制度。15分から30分の仮眠はこんなに集中力が回復する
ダイヤモンド・オンライン|なぜグーグル社員は「歩きながら瞑想」するのか?
ダイヤモンド・オンライン|いつも「同じこと」を考えてしまう人は要注意!!その「思考グセ」が脳疲労を招く!
佐藤舜
大学で哲学を専攻し、人文科学系の読書経験が豊富。特に心理学や脳科学分野での執筆を得意としており、200本以上の執筆実績をもつ。幅広いリサーチ経験から記憶術・文章術のノウハウを獲得。「読者の知的好奇心を刺激できるライター」をモットーに、教養を広げるよう努めている。

