
「このまま続けて、本当に意味があるのかな……」
思い切ってずっとやりたかったことをスタートしてみたあなた。
しかし、選んだやり方は正しいのか、思ったよりも手応えがなくやめたほうがいいのではないか——そんな不安や焦りが頭をよぎり、手が止まってしまうことが続いています。
変わりたい気持ちはあるのに、ネガティブな気持ちに負けて、せっかく始めたことをやめてしまう……。
でも実は、新しく始めた行動をやめたくなってしまうのは、脳が正常に働いている証拠。不安や迷いは、挑戦しているからこそ生じる健全な反応なのです。
この記事では、新しいことを始めたときに起こる不安や焦りの正体を理解し、適切に対処するための「視点の転換」について解説します。3つの典型的なパターンと、それぞれの具体的な対処法をご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
新しいことを始めると不安になる理由
「やりたかったことを始められたのに、不安になって止めてしまった……」
そんな経験はありませんか?
じつはこの状態は、行動心理学や脳科学の視点から見ると、「新しいことを始めた人に共通して起こる、ごく自然な反応」なのです。
つまり、不安を感じること自体は何も悪いことではありません。大切なのは、その不安との上手な付き合い方を身につけること。適切に対処できれば、むしろ成長につながるチャンスになるのです。
脳は「変化」を避けるようにできている
人間の脳には「現状維持バイアス」という性質があります。これは、人が新しい行動を本能的に避け、慣れた行動を続けようとする傾向のことを指します。
人間の脳は、体全体の重さのわずか2%しかありませんが、全エネルギーの約20%を消費しているといわれています。つまり、非常にエネルギーコストが高い器官なのです。*1
そのため、脳はできるだけ「省エネで済むこと」を好みます。
新しいことに取り組むと前頭前野が活性化し、とても負荷がかかります。脳が省エネを求める信号を、私たちは「不安」として受け取っているのです。
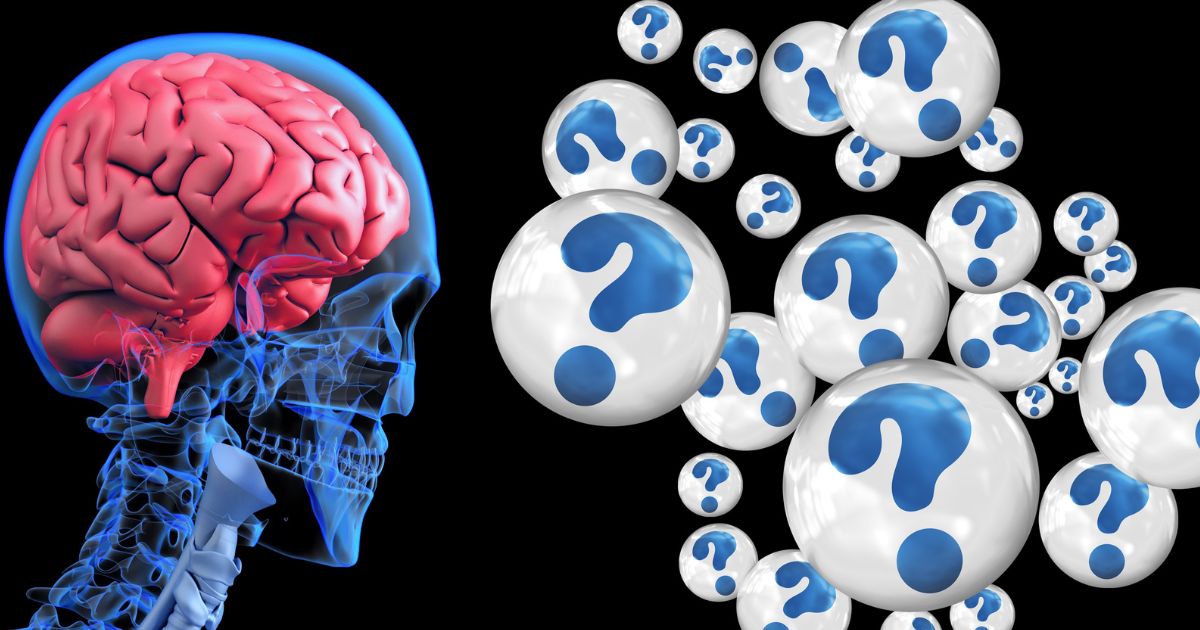
つまり、新しいことを始めて不安になるのは、脳が正常に働いている証拠。「危険だからやめなさい」ではなく、「新しいことに挑戦できている」というサインなのです。
次に、よくある3つのパターンと、それぞれの効果的な対処法をご紹介します。
3つの不安パターンと対処法
新しいことを始めたときの不安には、主に3つのパターンがあります。それぞれの特徴と対処法を詳しく見ていきましょう。
【パターン1】本当にやる意味があるのか不安になる
たとえばこんな感情
「こんなことをしていて、何になるんだろう?」
「もっと有意義なことに時間を使うべきでは?」
「自分なんかが挑戦する意味あるのかな……」
😰 なぜこの不安がおこる?
このような感情は、「この挑戦は、自分にとって本当に意味があるのか?」という、そのことに取り組む価値への疑問や迷いから起こりがちです。
「誰かの役に立つのか?」「時間のムダでは?」といった問いの裏には、「他者から評価されたい」「やるならそれなりの意義が必要だ」などの気持ちが隠れているのかもしれません。
😊 「やりたい」という気持ちに目をむける
こんなときは、「意味や成果」ではなく、「楽しいからやっている」という気持ちに立ち返ってみましょう。
いまの時代、何かに取り組むときには、「役に立つか」「意味があるか」が強く求められがちです。
でも、「もっと有意義なことに時間を使うべきでは?」という疑問が湧いてきたら、一度その視点は捨ててみましょう。
「やりたいから始めた」という原点に戻ると、やればやるほどやる気が出る、良いスパイラルに入ることができます。結果はそのあとについてきます。
【パターン2】自分のやり方が合っているか不安になる
たとえばこんな感情
「このやり方で合ってるのかな……?」
「どうせやるなら、もっと効率的にやらないと意味がない」
「まずは情報をもっと集めてからじゃないと始められない」
😰 なぜこの不安がおこる?
このような感情は、「できるだけ最短ルートで成果を出したい」という気持ちが強いときに起こりがちです。
「無駄な努力はしたくない」「最適解を見つけてから動きたい」──こんな焦りが背景にあるのではないでしょうか。
いまは「タイムパフォーマンス」が重視される時代。
さらに、SNSなどで「成功者の効率的なやり方」が大量に流れてくるなかで、「もっと自分に合った正解があるのでは?」と迷い続けてしまう人も多くいます。
😊 ベストを目指しすぎない
「ベストな方法」を探すことに時間を使いすぎると、肝心の行動がおろそかになるという矛盾に陥ってしまいます。
そんなときは、「まずは選んだ方法で、一定期間やってみる」と決めてみましょう。
哲学者のシャルル・ペパン氏は「不足しているのは自信」であると述べ、「確実な判断材料がないことを、自分の心の声を聞く能力で補い、とにかく前進すると腹をくくる」ことをすすめています。*2
「確実に自分に合う方法」ははじめから見つかりません。選んだことをしばらく続けることで、体験から判断材料が増え、より良い選択ができるようになるのです。

【パターン3】なかなか成果がでなくて不安になる
たとえばこんな感情
「こんなにやってるのに、まだ成果が出ない」
「結局ムダだったらどうしよう……」
「やっぱり、いまさら始めたって遅いんじゃないか?」
😰 なぜこの不安がおこる?
このような不安は、すでにある程度行動を起こしている人に起こりやすい「結果の見えなさ」による焦りや無力感がベースにあります。
「やったぶんだけ結果が出て当然」という期待があると、すぐに変化が見えない現実とのギャップに落胆し、「このまま続けて意味があるのか?」と疑いを抱いてしまうのです。
特に、数字や評価と結びつきやすい副業・発信・資格勉強などでは、一定期間がんばっても成果が目に見えないと、自己否定や焦燥感が強くなります。
😊 「結果」より「行動」に注目
こんなときは、「結果」より「自分がした行動」に注目してみましょう。
行動科学専門家の永谷研一氏は、「毎日『できたこと』を書くことで、つい陥りがちなネガティブな視点を矯正し、自己肯定感を高められる」と述べています。*3
自分が実際に行った行動をノートに書いていくことで、「これだけ積み重ねてきたんだ」と気づくことができ、小さな成長にも気づきやすくなります。
不安は挑戦している証拠
「新しいことを始めたら、不安や焦りは起こるもの」
このことがわかっていれば、翻弄されることなく、一歩ずつ進むことができます。
不安や焦りを感じたら、まずは「正常な反応なんだ」と受け入れて、どのパターンに当てはまるかを考えてみてください:
【パターン1】意味への不安 → 「やりたい」という気持ちに目をむける
【パターン2】方法への不安 → ベストを目指しすぎない
【パターン3】成果への不安 → 「結果」より「行動」に注目
適切な視点の転換で、きっと前に進み続けることができるはずです。
※引用の太字は編集部が施した
*1 神戸心理カウンセリングオフィス|「脳科学」から見た「やる気」の出し方
*2 ダイヤモンド・オンライン|「決断できない人」に欠けている1つのこと【書籍オンライン編集部セレクション】
*3 ダイヤモンド・オンライン|成功する人は、毎日「○○」をメモしている
柴田香織
大学では心理学を専攻。常に独学で新しいことの学習にチャレンジしており、現在はIllustratorや中国語を勉強中。効率的な勉強法やノート術を日々実践しており、実際に高校3年分の日本史・世界史・地理の学び直しを1年間で完了した。自分で試して検証する実践報告記事が得意。

