
「値上げします」の通知にモヤッとする。月額1,000円が1,200円に。割高に感じられるようになった。でも、なぜか解約できない——。
「ここまで使ったのに、いまさらやめたら損」
「年間プランにしたのに途中でやめるなんて……」
動画配信サービス、オンライン英会話、クラウドストレージ——現代のビジネスパーソンは、さまざまなサブスクリプションサービスと付き合っています。そして多くの人が、使用頻度が下がったり値上げされたりしても、なかなか解約に踏み切れずにいます。
「ここまで払ったのにいまさらやめられない」という気持ちの正体は、行動経済学でいう「サンクコスト効果」かもしれません。今回は、そんな「サブスク継続の心理」を手がかりに「サンクコスト効果」について解説します。
- なぜ人は、過去の支出に縛られてしまうのか?
- 「サンクコスト」はなぜこれほど強力なのか?
- サンクコスト効果の代表例:超音速旅客機「コンコルド」
- 企業が仕掛ける「解約しにくい仕組み」
- 本当に必要か? 「未来」で判断する力を身につける
- 「やめる」は「失敗」ではなく「最適化」
なぜ人は、過去の支出に縛られてしまうのか?
この本つまらないけど、買ったんだから最後まで読まなきゃ……
ジムに全然行ってないけど、入会金を払ってしまったから解約しづらい……
こんな経験に心当たりはありませんか? これらはすべて「サンクコスト効果」の典型例です。
経済的に考えれば、すでに支払った費用は回収不可能であり、今後の判断に影響を与えるべきではありません。つまらない本なら途中で読むのをやめてもっと有意義な時間を過ごし、使わないジムなら解約して別のことにお金を使うほうが合理的なのです。
それなのに、なぜ私たちは過去の支出に縛られてしまうのでしょうか?

「サンクコスト」はなぜこれほど強力なのか?
お金だけじゃない──「努力」や「時間」という見えない資産
語学学習アプリを例に考えてみましょう。毎日コツコツと学習を続け、連続ログイン記録が200日を超えたとします。たとえアプリの内容に飽きてきても、こんな気持ちが湧いてきませんか?
「200日も続けたのに、いまやめたら無駄になる……」
ここで働いているのは、お金だけでなく「継続した努力」というサンクコストです。
サンクコスト効果が強力な理由は、お金だけでなく「努力」や「時間」といった見えにくい資産も含んでいるため。これらは数値化しにくいぶん、感情的な重みを持ちやすいのです。
「失敗を認めたくない」という自己正当化
さらに、「失敗を認めたくない」という自己正当化の心理も加わります。サブスクを解約することは、そのサービスを選んだ過去の自分の判断が間違っていたことを認めることでもあります。 人間は一貫性を保ちたがる生き物であり、過去の選択を否定することに心理的な抵抗を感じるのです。
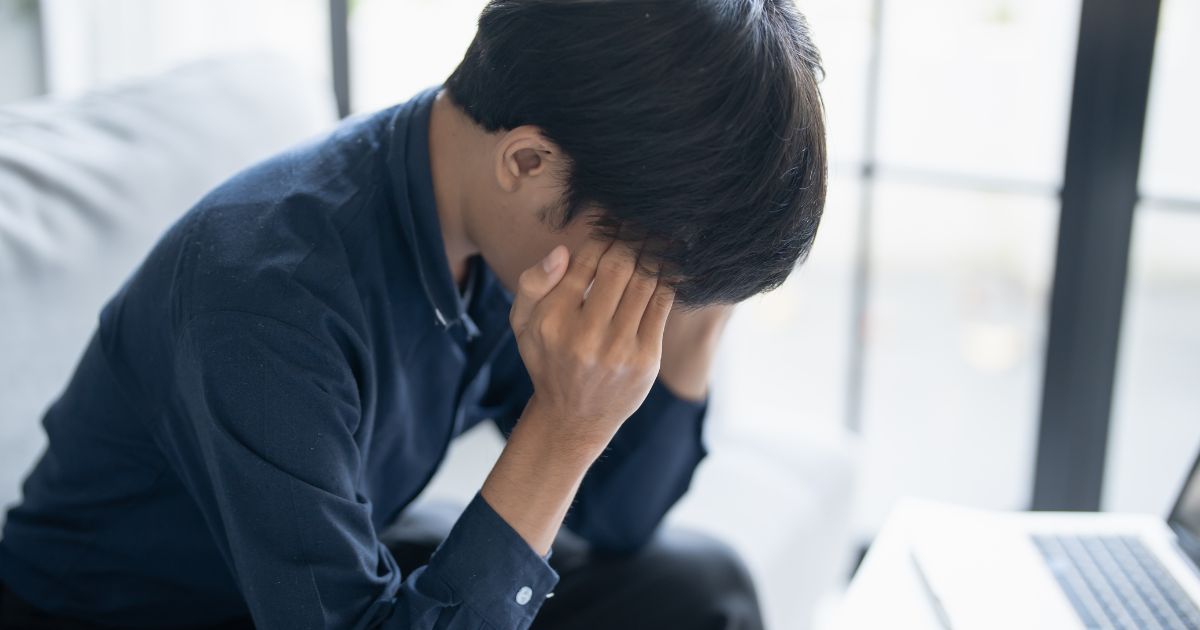
サンクコスト効果の代表例:超音速旅客機「コンコルド」
開発費が膨らみ続け、採算が合わなくなったにもかかわらず、開発を中止できなかったのです。この事例は「コンコルドの誤謬」とも呼ばれます。
本来は「将来の収益性」だけを基準に判断すべきでした。しかし「これまでの巨額投資を無駄にできない」という心理が、合理的な撤退判断を妨げたのです。
この事例が示すのは、サンクコスト効果は個人の小さな判断だけでなく、国家規模のプロジェクトでも同様に働くということです。私たちのサブスク継続判断も、規模は違えど同じ心理メカニズムが働いているのです。
企業が仕掛ける「解約しにくい仕組み」
多くの企業はこうした消費者心理を巧妙に利用しています。
これらの仕組みは、利用者に『これまでの投資を無駄にしたくない』という心理を生み出し、サンクコスト効果を意図的に誘発します。
- 年間プラン → 『まだ8ヶ月残っているから解約は損』
- 利用履歴表示 → 『100時間も投資したのに今やめるのは無駄』
- ポイントシステム → 『貯めたポイントを捨てるのはもったいない』
このように、企業は消費者の『過去への執着』を利用してサンクコスト効果を強化しているのです。消費者である私たちは、そうした戦略の存在を理解しておく必要があります。

本当に必要か? 「未来」で判断する力を身につける
では、サンクコスト効果に陥らないためにはどうすればいいのでしょうか。
✓ もしこのサービスが今日初めて提供されたとして、現在の料金で契約しますか?
✓ 過去の投資を一切考慮せず、純粋に今後の価値だけで判断したらどうですか?
✓ このお金をほかのことに使ったほうが、自分にとって価値があるのでは?

「やめる」は「失敗」ではなく「最適化」
重要なのは、やめることを「失敗」ではなく、「最適化」として捉えることです。環境や優先順位は常に変化しています。過去にいい判断だったことが、現在も最適とは限りません。 サービスを見直すことは、限られた時間とお金をより価値のあることに振り向ける賢明な選択なのです。
人間の意思決定には、多くの認知バイアスが影響しています。サンクコスト効果もそのひとつ。 「あ、これはサンクコスト効果だな」と気づけるだけで、感情的な判断から一歩引いて考えられるようになります。
過去の投資に縛られるのではなく、現在の価値観と将来の目標に基づいて判断する——そんな思考法を身につけることで、より満足度の高い人生を送ることができるはずです。
***
サブスクの解約という小さな決断も、私たちの意思決定能力を鍛える貴重な機会だと言えるかもしれません。値上げの通知が来たら、それを自分の選択基準を見直すきっかけとして活用してみてはいかがでしょうか。
STUDY HACKER 編集部
「STUDY HACKER」は、これからの学びを考える、勉強法のハッキングメディアです。「STUDY SMART」をコンセプトに、2014年のサイトオープン以後、効率的な勉強法 / 記憶に残るノート術 / 脳科学に基づく学習テクニック / 身になる読書術 / 文章術 / 思考法など、勉強・仕事に必要な知識やスキルをより合理的に身につけるためのヒントを、多数紹介しています。運営は、英語パーソナルジム「StudyHacker ENGLISH COMPANY」を手がける株式会社スタディーハッカー。

