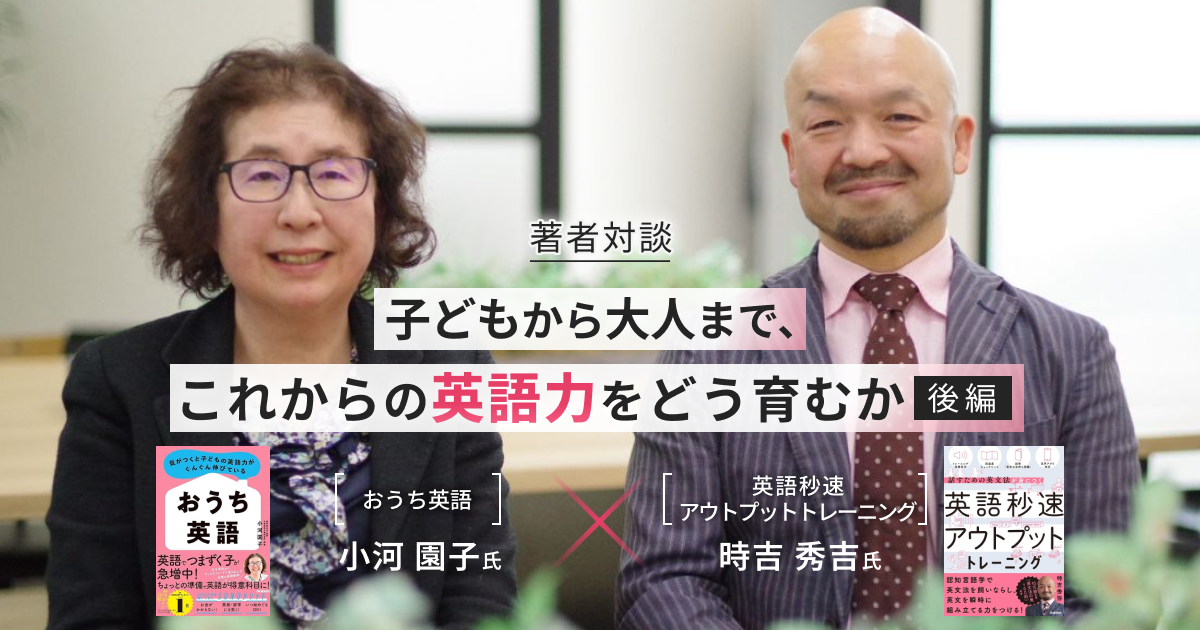
前編では、コミュニケーション重視への転換期を迎えている日本の英語教育について、文法教育の本質的な課題を中心に語っていただきました。後編では、英語ディベート教育の実践例や、日本語と英語の関係性について、さらに掘り下げていきます。
実践の現場から―英語ディベート教育の可能性
——小河先生は英語でのディベート教育にも取り組まれていたそうですね。
小河先生:はい。私は1980年代に教員になりましたが、自身の留学経験から、コミュニケーションを重視した英語教育を実践したいと考えていました。
その後、1998年頃から英語ディベートの活動に関わるようになりました。当時は「ディベートは受験英語と合わないのではないか」という意見もあったため、まずは進学校ではない高校で実践してみたのです。
この実践を通じて、高校3年生は予想以上に英語で議論ができることがわかりました。たとえば「資源の有限性」というような高度なテーマでも、その問題の深刻さを実感しながら議論を展開できるのです。
一方で、小学校高学年や中学生の場合は、まだ社会問題への認識が浅く、また英語での表現力も十分ではありませんでした。
2008年には浦和高校から「ぜひ英語ディベートを導入してほしい」というオファーをいただきました。私は「受験の成績や進学実績が落ちるかもしれませんよ、ほんとうに大丈夫なんですか」と前置きしたうえで、英語ディベートの導入、コミュニケーション重視の授業、海外留学の促進など、一見すると大学受験からは遠回りに見える改革に着手させていただいたのです。

受験と両立する英語力の育成
時吉先生:結果はいかがでしたか?
小河先生:進学実績は全く下がることはありませんでした。それどころか、私が担当していた時期は、浦和高校の過去20年間で最も東京大学への合格者数が多く、現役生・浪人生ともに最高の実績を残すことができたのです。
「これは県立トップの浦和高校だからできたのだ」と言われるかもしれません。しかし、その「浦和高校だから」という理由を詳しく見てみると、生徒たちに知的好奇心があり、日本語の基礎がしっかりしていて、英語の単語などを自主的に学習する力があった——そういった素地のある生徒たちに適切な学びの場を提供すれば、必ず伸びるということがわかったのです。
時吉先生:素晴らしい。
小河先生:この成果は、昨年教えていたお茶の水女子大学附属高校の3年生でも同じように確認できました。
基礎をしっかりと積み上げていけば、高校3年生での英語ディベートは非常に効果的なのです。なぜなら、この時期の生徒たちは知的に成長し、社会問題への関心も高まっているからです。
たとえば、「日本は再生可能エネルギーにどこまで取り組むべきか」というテーマで英語での議論を提案すると、最初は「そんなことは無理だ」「大学受験に差し支えるのではないか」という反対の声も聞かれます。
私はこのような反対意見と40年間向き合ってきましたが、実際にやってみると、必ずうまくいくのです。さらに興味深いことに、生徒たちも全く抵抗を示さないのです。
その理由は明確です。受験のために学んできた英単語や表現を、実際のコミュニケーションの場で活用できるからです。
「将来どうあるべきか」「なぜそうなったのか」といった議論に必要な英語表現は、じつは大学入試で求められる英語力と大きく違わないのです。むしろ、このように実際に使用する機会を得ることで、学習した内容がより確実に定着するのです。

日本語と英語の関係性を考える
時吉先生:私はいわゆる旧来的な、通訳したり日本語に訳したり、あるいは単語を覚えたり文法をちゃんと理解したりする英語教育は最初から全く否定してないんです。なぜならばそれは自分もやっていたしその恩恵も受けてきたから。でも、それで終わりは本当に勿体なくて。
小河先生:そうですね。それは日本語力のベースなしには無理だというのは、私も本当に感じています。
時吉先生:外国語の学習には、自分の母語を客観的に見直す効果があります。たとえば、日本語の自動詞や他動詞、主語や目的語といった文法的な要素に、英語を学ぶことで初めて気がつくことがある。そのおかげで「なんとなくの自己流の日本語」が「より正確で伝わりやすい日本語」になっていきます。このように、外国語の学習は日本語を客観的に理解する機会を与えてくれるのです。
小河先生の本『おうち英語』でも触れられていましたが、たとえば謝罪の方法でも、日本語と英語では興味深い違いがあります。
日本では、謝罪の際に理由を説明すると「言い訳をしている」という印象を与えかねないため、多くの人は表情や態度で誠意を示そうとします。しかし英語圏では、なぜその事態が起きたのかという説明がない謝罪は、むしろ不適切とされます。
この違いは、私たち日本人が「理由を述べる」という文化的習慣を、英語に比べればということですが、あまりもっていないことを示しています。こうした気づきも、英語学習を通じて得られる重要な視点の一つと言えるでしょう。
日本語と英語では、日常会話の進め方にも興味深い違いがあります。たとえば、食べ物の好みについて話す場合、日本語では「焼肉が好き」という発言に対して「焼肉いいよね」と共感で返すのが典型的な会話の流れです。
一方、英語圏では「なぜ焼肉が好きなの?」と、その理由を尋ねることが一般的です。このような質問に対して、日本人のなかには「プライベートなことを詮索されている」と不快に感じる人もいます。
しかしじつは、これは相手に対する関心の示し方の違いなのです。英語圏の人々は、会話を表面的な共感で流すのではなく、理由を尋ねることで「あなたのことをもっと知りたい」という積極的な関心を表現しているのです。

小河先生:そうですね。たしかにこれまで日本語と英語のコミュニケーションの違いについては、文化的な観点から説明されてきました。
日本は「阿吽の呼吸」が通じる「ハイコンテクスト」な文化で、状況に依存したコミュニケーションが特徴です。一方、英語圏は「ローコンテクスト」な文化で、状況に依存せず言葉で明確に伝えようとする——そういう対比で語られてきました。
この違いを非常に印象的な形で感じたのが、じつはコロナ禍でした。日本でも「なぜ外出してはいけないのか」「なぜマスクが必要なのか」「なぜ居酒屋は8時までなのか」という「なぜ」を問う声が次々と上がり、まるで英語圏のような光景だと感じたのです。
それまで日本では、ある事象に対して周囲の人も同じ判断をするだろうという前提で物事が進められてきました。
しかし、コロナ禍という死活問題に直面し、特に営業時間制限や酒類提供の是非といった切実な問題に直面したとき、人々は「なぜ」という問いを発し始めました。説明を求め、より詳しい根拠を求める——その様子を目の当たりにして、「英語圏の人々はこういった『なぜ』の問いかけを、ずっと当たり前のものとしてきたのか」と考えさせられました。

これからの英語教育に向けて
——最後に、今後の英語教育の展望と、お2人が今後取り組んでいきたいことについて、小河先生からお願いします。
小河先生:時吉先生も指摘されていたように、英語教育の目標は「議論ができること」「気持ちを伝えられること」にあります。ここで重要なのは、コミュニケーションの本質が「共有」にあるということです。
つまり、一方的に自分の意見を述べるのではなく、相手の話をしっかりと受け止めながら対話を進めていく。そして、必ずしも対立する必要はなく、むしろ意見の微妙な違いや濃淡を理解しながら、対話を発展させていくのが英語圏の文化なのです。
私は、このような実践的なコミュニケーション能力を育てる英語教育が、もっと高校現場に広がってほしいと願っています。
そして私自身の今後についてですが、4月から小学校でアドバイザーとして教育現場に関わらないかというお話をいただいています。もし実現すれば、3年生から6年生までの英語教育の現場で新たな経験ができることを、いまからとても楽しみにしています。
その経験を通じて得られる知見を、ブログやノートの形で発信し、次世代の英語教育に貢献していければと考えています。
時吉先生:日本の少子化は今後も止まらないと考えています。人口が減少すると、これまで国内市場だけで成り立っていたビジネスも、必然的に海外市場に活路を見出さなければならなくなります。そのとき、自社の商品やサービスの魅力を海外に効果的に伝えられるかどうかが、重要な鍵となるでしょう。
このような状況を見据えると、現在の英語と日本語を別々に扱う「縦割り」の教育システムは、ぜひとも改善していく必要があります。
私が理想とするのは、日本語と英語を融合させた一体的な言語教育です。つまり、まず日本語で論理的な思考や議論の基礎を築き、それを土台として英語での表現力を育てていく——そんな連携の取れた教育を日本全体で推進していってほしいと考えています。
幸いなことに、教員養成の最高峰である東京学芸大学で、私の文法の著書『英文法の鬼100則』(明日香出版)が指定図書として採用されていると聞いています。これをひとつのきっかけとして、私の研究や実践が日本の英語教育の発展に少しでも貢献できればと願っています。
***
40年の教育実践をもつ小河氏と、認知言語学の理論から新しい文法教育を提唱する時吉氏。異なるアプローチながら、両者は「使える英語」の重要性で一致しています。小学校での動的な学びから、中学・高校での論理的思考の育成まで、そして究極的には日本語と英語の——一体体的な教育の実現まで——。グローバル化が進むなか、確かな英語力を育むための道筋が、二人の対話から見えてきました。
◾️小河園子先氏 × 時吉秀弥の対談紹介記事
第1回:【前編】『おうち英語』×『英語秒速アウトプットトレーニング』著者対談 |子どもから大人まで、これからの英語力をどう育むか
第2回:【後編】『おうち英語』×『英語秒速アウトプットトレーニング』著者対談 |子どもから大人まで、これからの英語力をどう育むか
STUDY HACKER 編集部
「STUDY HACKER」は、これからの学びを考える、勉強法のハッキングメディアです。「STUDY SMART」をコンセプトに、2014年のサイトオープン以後、効率的な勉強法 / 記憶に残るノート術 / 脳科学に基づく学習テクニック / 身になる読書術 / 文章術 / 思考法など、勉強・仕事に必要な知識やスキルをより合理的に身につけるためのヒントを、多数紹介しています。運営は、英語パーソナルジム「StudyHacker ENGLISH COMPANY」を手がける株式会社スタディーハッカー。



