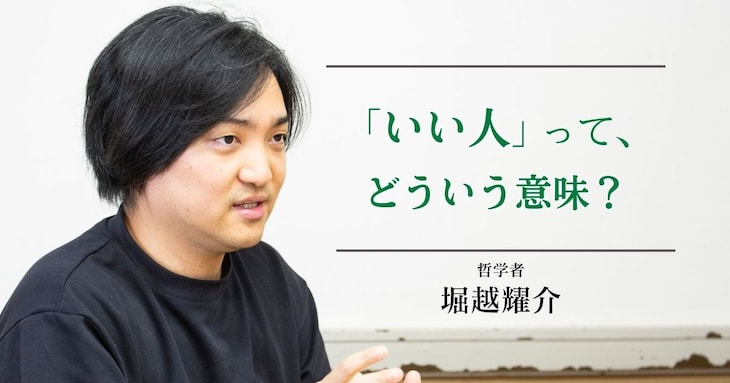
上司の指示通りに仕事をしているつもりなのに評価されないといったネガティブな状況を招いているのは、それぞれがもつ「言葉のイメージのずれ」にあるのかもしれません。著書『世代と立場を超える 職場の共通言語のつくり方』(クロスメディア・パブリッシング)を上梓した哲学者の堀越耀介先生は、そうしたずれを防ぐために、「哲学対話」という手法をすすめます。
構成/岩川悟 取材・文/清家茂樹 写真/石塚雅人(インタビューカットのみ)
【プロフィール】
堀越耀介(ほりこし・ようすけ)
1991年生まれ、東京都出身。東京大学共生のための国際哲学研究センター上廣共生哲学講座特任研究員。哲学コンサルタント。東京大学大学院教育学研究科博士課程修了。博士(教育学)。学術的な知見と5,000人以上に対する対話のファシリテーションの経験を融合させ、企業が課題解決や価値創造に取り組む活動を支援。NECソリューションイノベータ株式会社、三井不動産株式会社、株式会社SBI新生銀行、株式会社LegalOn Technologiesなど多様な企業に対して、「哲学」と「対話」によって組織の潜在能力を最大限に引き出すコンサルティングを実施。株式会社ShiruBe(哲学クラウド)でコンサルタント、上席研究員を務めるほか、株式会社電通と研修プログラムの共同開発を行なうなど、活動の場を広げている。著書に『哲学はこう使う 問題解決に効く哲学思考「超」入門』(実業之日本社)がある。『FORBES JAPAN』をはじめ、各メディアでも幅広く活躍する。
ある言葉に対するイメージは、人それぞれに異なる
これは職場に限った話ではありませんが、相手と同じ言葉を使っているにもかかわらず、「相手に伝わらない」ことは頻繁に起こります。当たり前の話かもしれませんが、同じ言葉であっても、その言葉に対してもっているイメージは人それぞれに微妙に異なるからです。
職場での例を挙げれば、「主体性」という言葉もそのようなすれ違いを招く代表的な言葉のひとつでしょう。部下に対して「主体性を発揮してほしい」という思いをもっている上司にとっての主体性は、「組織の目的を理解し、指示されずとも自ら課題を見つけて積極的に挑戦すること」だとします。対して部下は、「指示された仕事の進め方について自ら考え、そつなくこなすだけで十分」ととらえているかもしれません。
そうなると、上司側からすれば「部下の働きぶりは物足りない」と感じますし、そう指摘された部下側からすれば「自分なりにしっかりやっているつもりなのに……」と不満を募らせることになるでしょう。このような言葉のイメージのずれによるすれ違いが、職場では日常的に起こっているのです。
もっと身近な例を挙げるなら、「いい人」という言葉がわかりやすいかもしれません。これは、私自身が友人との会話のなかで経験したことです。「○○さんって『いい人』だよね」と言う友人の言葉に対し、私は「え、そうかな?」と思ってしまったのです。そこで私は「どういう意味でいい人って言ったの?」と聞くと、友人は「自分にとって害がない人」と答えました。
私としては、「いい人」とはただ害がないだけでなく、「自分になんらかの利益をもたらしてくれる人」のようなイメージをもっていました。それぞれのイメージの違いにより、私たちのあいだで「伝わらない」「すれ違う」ということが起きてしまったのです。

「共通言語」をつくり、すれ違いを防ぐ
もちろん、このようなことが職場でたびたび起これば、認識の齟齬によって問題が引き起こされるのは明白です。そうした事態を招かないためにおすすめしたいのが、「共通言語」をつくることです。
共通言語とは、「組織やメンバー間において、その意味と文脈が共有されている言葉」です。先の例で言えば、「主体性とはこういうことだよね」「いい人ってこういう人だよね」と認識を共有できていれば、認識の齟齬による問題が起きるのを防げるわけです。
共通言語の定義として「『文脈』が共有されている言葉」としたことにも、もちろん重要な意味があります。というのも、言葉の意味は、それぞれの文脈によって微妙な変化が生じるものだからです。
ここで言う文脈とは、端的に言うと、その人がこれまで生きてきた環境や経験してきたことです。先の例で言えば、幼い頃から学校生活などのなかでまわりから嫌がらせをされてきたような文脈をもつ人ならば、ただ「自分にとって害がない人」であっても「いい人」ととらえるようになるといった具合です。
ですから、そうした文脈も含めて、「この人が言うこの言葉はどのような意味なのだろう?」とひとつひとつ確かめていく必要があります。そのように、人それぞれがもつ文脈と意味を互いにすり合わせていくことで、すれ違いを大きく減らせるのです。

「そもそも〇〇とは?」という問いで、互いの認識を確かめる
しかし、ある言葉に対して人それぞれがもつ文脈や意味を日常のなかでいちいち確かめるのは、現実的ではないかもしれません。そこで、私が専門とする「哲学対話」をぜひ実践してほしいのです。
「哲学」なんて言葉がつくと「難しそう」と感じる人もいるかもしれませんが、決して難しくありません。哲学対話とは、正解を導き出すための議論ではなく、「そもそも主体性とは?」といった答えが確定的ではないような根源的な問いについて、「人それぞれだから」と諦めずに一緒に考え続ける対話のことです。
しかし、この哲学対話をする際にも注意が必要です。「そもそも」で始まる問いには、相手を責めるニュアンスも含まれていることがあるからです。上司から「そもそも、あなたは『主体性』をどうとらえている?」とか「『お客様第一』ってどういうことだと思う?」などと聞かれたら、「本当にそれで正しいのか?」となんだか責められているような気持ちにもなりますよね。
ですから、「これはお互いを侮辱したり責めたりするためのものではない」「ある言葉の認識についてお互いの認識を確かめ合い、共通言語をつくってよりスムーズに仕事を進められるようにするためのものだ」という前提を事前に共有したうえで、哲学対話の場を設けることが重要なポイントです。
そのうえで、先の主体性でもいいですし、「そもそも『斬新なアイデア』とは?」「そもそも『チームワーク』とは?」など、みなさんそれぞれの職場において、メンバー間のイメージの違いによりすれ違いを生んでしまっている言葉について話し合ってみてください。きっと、「え、そういうふうに思っていたの?」「だからあんな問題が起こっていたのか」と驚くとともに、職場で共通言語をつくることの重要性や有用性を実感できるはずです。

【堀越耀介先生 ほかのインタビュー記事はこちら】
「会話」と「対話」は似て非なるもの。仕事をスムーズに進めるための「共通言語」をつくる対話の技術
「あ、それって〇〇ということ?」。認識の齟齬を生まない「共通言語」が生まれる瞬間
清家茂樹(せいけ・しげき)
1975年生まれ、愛媛県出身。出版社勤務を経て2012年に独立。ジャンルを問わずさまざまな雑誌・書籍の編集に携わる。


