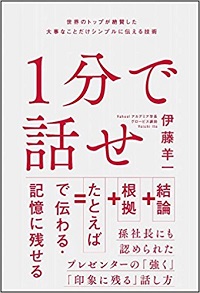ビジネスパーソンの多くが、苦手意識を持っているのに避けて通ることができないもの――。それがプレゼンです。「うまく話せない……」「伝えても結果につながらない……」と悩んでいる人も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、伝わるプレゼンの極意を明らかにした著書『1分で話せ』がベストセラーになっている伊藤羊一さんに、大事なことだけをシンプルに伝えるプレゼンの大原則を聞いてきました。
■第1回『人を動かすプレゼンの極意』 ■第2回『ロジカルに納得させ、人生を賭けた「想い」で人を動かす』 ■第3回『自分を導ける者だけが、優れたリーダーになる』
構成/岩川悟 取材・文/辻本圭介 写真/玉井美世子
相手に伝わらないのは、話に「骨組み」がないから
いまでこそわたしはプレゼンを人に指導する立場ですが、20代の頃はプレゼンで人を動かすことなんてまったくできませんでした。話は長くなるし、ロジカル・シンキングも苦手で、「どうすれば説得力のあるプレゼンができるのだろう?」といつも悩んでいたのです。
そこから紆余曲折を経て、ようやく人に伝えられるようになったいまとの一番のちがいは、話に「骨組み」をつくることができるようになったこと。わたしは、話に「骨組み」がないことは、「自分がない」ことに等しいと考えています。後で説明しますが、要はかつてのわたしは、本気で人に伝えたいことがなかったということです。
また、もうひとつ話が伝わらない理由があります。それは、話に「骨組み」がないと、聞き手はたとえ5分でも話を聞かなくなるということです。言葉としては理解できても、「で、結論はなんなの?」という気持ちになってしまう(苦笑)。最初の1、2分でよくわからなければ、ほとんどの人はもう話を聞いていないと考えていいでしょう。
話す側が伝えるべきストーリーの「骨組み」をつくらず、聞く側も聞いていない。すると、「いったいこの時間はなんなのだ?」となりますよね。でも、仕事が進まないのは困るから、結局は聞く側が歩みよることになる。「つまり、君が言いたいのはこういうこと?」と、聞き手が頭を働かせているようなコミュニケーションが現実にはとても多いのです。
そこで、プレゼンでは話に「骨組み」をつくって、聞き手が理解しやすいかたちで伝える必要があります。その「骨組み」がこれです。
結論+根拠+たとえば
まず「結論」を伝え、次にその「根拠」を示し、最後にその根拠たる「たとえば」をつける。すると聞き手は、結論をてっぺんに話の「骨組み」がつながったピラミッド型で、ストーリーをロジカルにイメージすることができます。ここでひとつ、簡単な例を挙げましょう。
わたしは牛丼屋が好きなんです(結論)。なぜなら早いし(根拠1)、安いし(根拠2)、美味しい(根拠3)から。どのくらい早いか(たとえば1)というとね……
あくまで話の「骨組み」だけですが、それでも言いたいことは十分明確に伝えられると思いませんか?

仕事もプレゼンも、目的は「相手を動かす」こと
どうして結論から伝えないのか? これには言語的・社会的・文化的な理由も大きいと思います。なぜなら、わたしは欧米人に指導することもありますが、彼らは「骨組み」の部分であまり苦労しないからです。
たとえば英語なら、文頭から「主語+動詞」によって「誰がなにをした」と結論が示されます。そして、その理由は3つあって……と自然に続いていく言語なのです。でも日本語は、結論を最後まで聞かないとわからないことが多く、しかも結論から言わないという文化も根づいています。日本人は結論をぶつけあうよりも、同じ場所での人間関係を大切にし、「波風立てずにゆっくりわかり合えばいい」と振る舞う傾向があるのかもしれません。
しかし、ここ20年で世界は急激にグローバル化し、次々とイノベーションが生まれて変化が激しい時代になりました。そして、ビジネスパーソンは否応なくグローバル市場で戦わなければなりません。そんなときに、「その背景はですね……」「前提としましては……」などと言っていては、時間とチャンスをどんどん失って置き去りにされてしまいます。
わたしはマインドセットを欧米流に変えようなどとは一切思いませんが、少なくともビジネス上のコミュニケーションでは、先に結論を伝える「英語脳」に変えることは必要だと考えています。先に結論を考えるときのポイントはこれです。
・相手は誰か ・ゴールはなにか
人に伝えるときは、まずこれを考えることからはじめましょう。でも、これはプレゼン以前に、仕事をする前提となるマインドではないでしょうか。結局のところ、仕事は新しいものをつくったり改善したりと、「なにかを動かす」ために行います。そして、それはコミュニケーションでも同じで、「わたしはこう思います」と結論や主張を伝えて、「それはこういうことですね」と相手に理解や納得をさせて動いてもらいます。つまり、
結論+根拠+たとえば=相手を動かす
プレゼンはもちろんのこと、そもそも仕事というものは「相手を動かす」ことなのです。

ゴールを明確に言語化し、伝える相手に「思いを馳せる」
こんな話をすると、「言われればわかるけど、それが難しいんだよね……」という人がたくさんいます。そんな人たちに伝えたいのは、「本当に『相手を動かす』意識で臨んでいますか?」ということ。わたしが見たところ、この「相手を動かす」という根幹の部分をなんとなくやっている人がとても多いようです。酷い場合には、「上司がやれと言ったからやりました」と言う人までいます(笑)。
そこで、先に書いた「相手は誰か」「ゴールはなにか」という要素を言語化することを強くおすすめします。いったん言葉にすると、仕事のすべてのプロセスにおいてその瞬間ごとに考えることができます。「相手は誰か」であれば、「どんなことに興味があるのか」「どんなことが気がかりなのか」「この人たちが達成したいことはなにか」というところまで深く考えられるようになるでしょう。
また、伝える相手をイメージすることも大切です。もっと言うなら、「思いを馳せる」。じつは、大切な人や大事な瞬間には誰でもそれをやっているはずです。たとえば、絶対に失敗が許されないプロポーズであれば、シーンの設定から相手の心の動きにいたるまで、もう必死になって何日もイメージして考えますよね(笑)。わたしがお伝えしたいのは、「それをすべての瞬間にやろう!」ということなのです。
【Yahoo!アカデミア学長 伊藤羊一さん インタビュー記事一覧】 ■第1回『人を動かすプレゼンの極意』 ■第2回『ロジカルに納得させ、人生を賭けた「想い」で人を動かす』 ■第3回『自分を導ける者だけが、優れたリーダーになる』
【プロフィール】 伊藤羊一(いとう・よういち) ヤフー株式会社コーポレートエバンジェリスト。Yahoo!アカデミア学長。株式会社ウェイウェイ代表取締役。東京大学経済学部卒。グロービス・オリジナル・MBAプログラム(GDBA)修了。1990年に日本興業銀行に入行し、企業金融、事業再生支援などに従事。2003年からプラス株式会社に勤務し、事業部門であるジョインテックスカンパニーでロジスティクス再編、事業再編などを担当。2011年より執行役員マーケティング本部長、2012年より同ヴァイスプレジデントとして事業全般を統括。2015年4月よりヤフー株式会社に転じ、次世代リーダー育成を行う。かつては、ソフトバンクアカデミアに所属。孫正義氏へプレゼンし続け、国内CEOコースで年間1位の成績を修めた。グロービス経営大学院客員教授としてリーダーシップ科目を教える他、多くの大手企業やスタートアップ育成プログラムでメンター、アドバイザーを務めている。
【ライタープロフィール】 辻本圭介(つじもと・けいすけ) 1975年生まれ、京都市出身。大学卒業後、主に文学をテーマにライター活動を開始。2003年に編集者に転じ、芸能・カルチャーを中心とした雜誌の編集に携わる。2009年以後、上場企業の広報・IR媒体の企画・専門編集に携わりながら、月刊『iPhone Magazine』編集長を経験するなど幅広く活動。現在は、ブックライターとしてもヒット作を手がけている。