
論理的で、正確で、筋道立てて話せる――そんな 「論理的に話せる人」 はたくさんいます。
しかし、それだけでは聞き手を 「惹きつける」ことはできません。
「論理的に話せる」のと「聞き手を惹きつける」のは別のスキルなのです。
たとえば、こんな場面を思い浮かべてください。
会議で何人かが順番に話しているなか、ある人が話し出した瞬間、思わず耳を傾けてしまう――そんな経験がありませんか?
そんな「思わず聞き入ってしまう」ような話し方には、「視聴覚ミラーニューロン」という脳細胞の働きが関わっています。
本記事では、脳のしかけを使って相手を惹きつける話し方についてお伝えしていきます。
ぜひ本記事を参考に、日々の実践に取り入れてみてください。
- 「論理的に話せる人」と「惹きつける話ができる人」の違い
- 脳科学でわかった「聞き手を惹きつける話し方」の正体
- 惹きつける人の "ストーリーテリング" 3つのポイント
- "ストーリーテリング" が向く場面と向かない場面
「論理的に話せる人」と「惹きつける話ができる人」の違い
一生懸命論理立てて話しているのに聞き流されてしまったり、退屈そうにされてしまったり……。そのようなことが続くと、話すことに対して自信を失ってしまうでしょう。
しかし、ちょっとした工夫で相手を惹きつける話し方ができるようになります。
コミュニケーション指導などを手がける株式会社グッドコミュニケーション 代表取締役の野口敏氏は、相手を惹きつける話し方をする人には「聞き手に映像を見せる力」があると話します。*1
たとえば、次のふたつの文章を比べてみてください。
iPad Airの処理能力についての説明です。
iPad AirはM3チップを搭載しており、M1チップと比較してCPU・GPU・Neural Engineの性能が約2倍に向上しています。
これにより、動画鑑賞やあらゆる作業での各種処理が高速化されました。
また、電力効率も改善されており、バッテリーの持続時間は終日使用可能です。
「飛ぶような速さのM3チップが、Apple Intelligenceにパワーを、そしてiPad Airに凄まじいパフォーマンスをもたらします。
パワフルなCPU、GPU、Neural Engineを積み、処理速度はM1チップ搭載iPad Airの約2倍もレベルアップ。
作業する。ストリーミングを楽しむ。何かを作る。ゲームで遊ぶ。
どんな時も、GPUアーキテクチャが先進的なグラフィックスを届けます。
そのすべてを、バッテリーを一日中持続させる優れた電力効率でどうぞ。」*2
ひとつめは論理的で正確な情報ですが、事実の羅列で印象に残りません。
一方ふたつめは、以下の点で内容を映像としてイメージしやすい工夫が盛り込まれています。
- 「飛ぶような速さ」→処理の速さをイメージしやすい
- 「作業する。ストリーミングを楽しむ。何かを作る。」→手にしたユーザーが得られる体験をイメージしやすい
同氏によれば、このように聞き手は映像をイメージできると「まるで自分に起こった出来事のように話に入り込むことができ」るのだとか。*1
つまり、自分の話に相手を惹き込めるかどうかは、「聞き手が話を自分ごとのようにイメージできるか」どうかにかかっているのです。

脳科学でわかった「聞き手を惹きつける話し方」の正体
このように、伝えたい情報を物語のように話し、聞き手に印象を与える手法を「ストーリーテリング」と言います。*3
ストーリーテリングはテレビCM、広告、企業のブランディングなど、さまざまな場面に取り入れられています。
たとえば炭酸飲料のCMであれば、視聴者はCMのストーリーに無意識に自分を重ね、「自分がCMの炭酸飲料を手に取ったら?」「飲んだらすっきりした爽快感を味わえそうだな」といった具合に、CMのストーリーに惹きつけられ、「欲しい」という感情が動くでしょう。
CMに限らず、私たちが話す場面においても同じことを起こすことができます。
このストーリーテリングには、脳の前頭前野にある "言葉をイメージに変換する細胞"「視聴覚ミラーニューロン」が関係しています。
脳科学者の西剛志氏は、脳内のイメージが行動に与える影響について、以下の実験を紹介しています。
アスリートたちが自分に「強い、強い」と言うのか、それとも「弱い、弱い」と言うのかにより、その後の握力測定では5〜10%ほどの違いが出たのです。もちろん、好成績を残したのは前者です。*4
頭のなかで思い描いたイメージが、実際の身体の反応や行動にまで影響を与える――つまり、人は想像したことを、ある種の "擬似体験" として受け取るのです。
これは、誰かの話を聞いているときにも同じことが言えます。ストーリーを通して情景や感情を思い浮かべると、視聴覚ミラーニューロンが働き、まるで自分が体験しているかのような感覚が生まれるのです。
だからこそ、ストーリーテリングが聞き手の心を動かすカギとなります。

惹きつける人の "ストーリーテリング" 3つのポイント
では、どうすれば相手を惹きつける話し方ができるようになるでしょうか?
ここでは、ストーリーテリングを実践するための3つのポイントを紹介いたします。
1. 短くまとめる
ストーリーテリングで大切なのは、話し手が伝えた内容を聞き手がイメージできることです。
前出の野口氏は、聞き手がイメージしやすいようにするためには「一気に話してはいけない」と言います。*1
プレゼンで聞き手の注意を引くための「つかみ」を例に考えてみましょう。
今日は私たちの新しいプロジェクトについてお話ししますが、このプロジェクトは社内の生産性を大きく改善し、業務の無駄を省くことができるもので、導入後には社員の満足度向上にもつながると期待されています。
みなさん、いまの業務に「無駄が多い」と感じたことがありませんか?
私はあります。
毎日、同じ報告書を何度もまとめたり、同じデータを部署ごとに入力し直したり。
もし「無駄」だと感じる作業を手放せたとしたらどんな未来が待っているでしょうか?
今日お話しするのは、「その無駄をごっそり減らすプロジェクト」です。
一気にまとめて話されるとイメージが追いつきませんが、短く区切られた話はイメージしながら聞くことができます。
Xで日常を短くまとめて共感を誘う練習をしてみたり、同僚との雑談でも短くまとめながら話してみたり。
普段から「短く区切って話す」ことを意識して、ここぞというときに惹きつけ力を発揮できるように準備しておくといいでしょう。

2. 間(ま)をとる
短く区切りながら話すことで生まれるのが「間」です。そしてこの「間」は、聞き手のペースに合わせて話すことにもつながります。
言葉のあいだに「間」をつくり、聞き手のあいづちを確認してから話を進めるのが、ストーリーテリングをより効果的に実践できるポイントです。
先ほどの例で言えば、「☆」のところで「間」をおき、聞き手のうなずきなどリアクションを確認してから話を進めるようなイメージ。
みなさん、いまの業務に「無駄が多い」と感じたことがありませんか?
☆
私はあります。
毎日、同じ報告書を何度もまとめたり、同じデータを部署ごとに入力し直したり。
☆
もし「無駄」だと感じる作業を手放せたとしたらどんな未来が待っているでしょうか?
☆
今日お話しするのは、「その無駄をごっそり減らすプロジェクト」です。
もしかすると、話している側は「間」が長く感じて落ち着かないかもしれませんが、聞き手からするとちょうどよいペースに感じるものです。
もし不安であれば、話している様子をボイスメモで録音して確認してみるといいでしょう。
筆者はよくボイスメモを使って話すテンポを確認するのですが、自分ではゆっくり話しているつもりでも、意外と早口になっていることがあります。
録音を誰かに聞いてもらって、どのくらいの「間」だと退屈せずに楽しめるかを確認してもらうのもいいかもしれません。

3. 感情を込める
先述したiPad Airの処理能力についての説明でもそうでしたが、ただ論理的に事実を述べるだけでは聞き手の印象に残りません。
私たちが映画を観たり、誰かのスピーチを聴いたりして強い印象を受けたときには、必ず感情が動いています。
そして感情が動くときというのは、相手の感情に触れて共感できたときではないでしょうか。
リーダーシップについての講演などを行なうブルース・ワインスタイン氏がこれまでに感動した講演について、「メッセージの感情的な部分により、スピーチは忘れられないものになった」と話します。*5
ストーリーテリングを意識して話すとき、「自分はどう感じたのか」といった感情を込めて話せば、あなたの話はただの論理的な情報伝達ではなくストーリーとして聞き手を惹きつける話になるはずです。
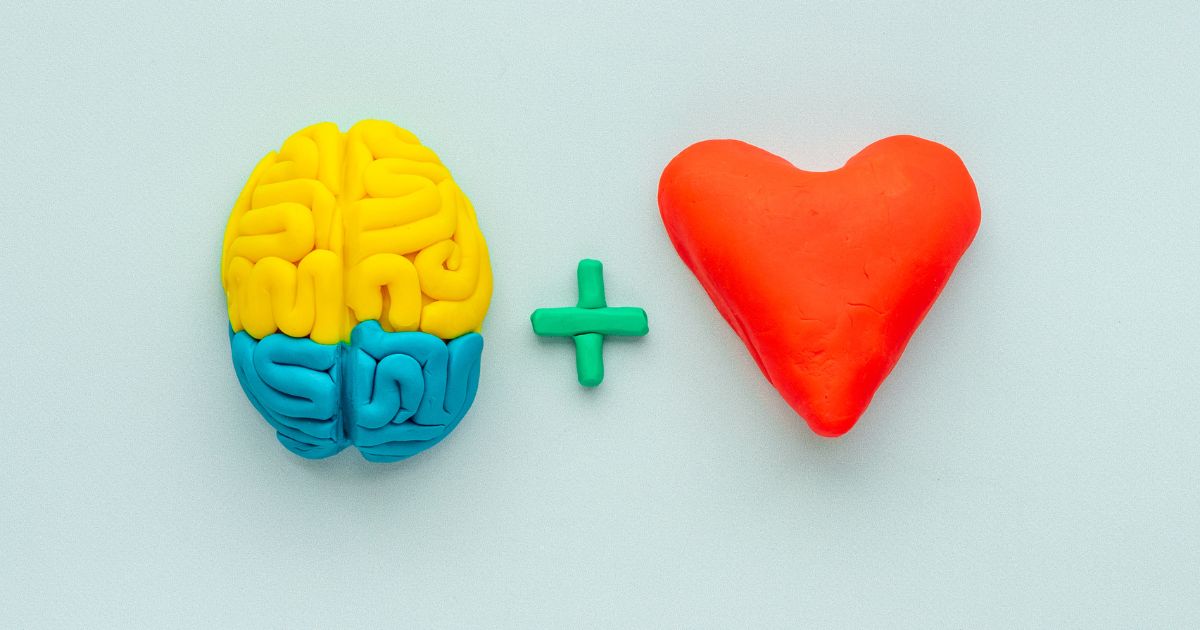
"ストーリーテリング" が向く場面と向かない場面
ここまで相手を惹きつける話し方「ストーリーテリング」についてお伝えしてきましたが、状況に合わせて使い分ける必要があります。
【ストーリーテリングが向く場面】
- 共感・感情を引き出したいとき
→商品紹介、プレゼンの冒頭、講演、自己紹介、マーケティング、教育や指導、信頼関係を構築するためのコミュニケーションの場など。
聞き手が「自分ごと化」しやすく、印象に残りやすい。
- 複雑な概念をわかりやすく伝えたいとき
→新技術の紹介、企業理念の伝達など。
抽象概念をストーリーに落とし込むことで、「なるほど、そういうことか」と理解をスムーズにする。
- 行動を促したいとき
→広告コピー、採用説明、営業活動など。
ストーリーを通じて価値観や理想を共有し、「自分もなにかしたくなる」気持ちが生まれやすい。
【ストーリーテリングが向かない場面】
- 短時間で正確に情報を伝えなければならないとき
→緊急時の報告、仕様説明など。
ストーリーは回りくどくなりやすく、情報伝達のスピードと正確性が落ちる恐れがある。 - 聞き手が "結論ファースト" を求めているとき
→経営層へのプレゼン、進捗報告、技術レビューなど。
ストーリー展開が冗長に感じられ、結論がどこにあるのかわかりにくい印象を与える可能性がある。 - 聞き手が高ストレス・情報過多な状態にあるとき
→クレーム対応、謝罪、緊急対応中の会話など。
感情に訴えるよりも「事実」や「解決策」の提示が優先される状況のため。
ストーリーテリングが向かない場面でも、事実や解決策を提示したあとに、根拠としてストーリーを添えることはできるかもしれません。
そのときの状況に合わせて判断するといいでしょう。
***
短くまとめ、間をつくり、感情を込める。普段からこの3つを意識しながら話し、実践を積んでみてはいかがでしょうか。
※引用の太字は編集部が施した
*1 ZUU online|話がうまい人がやっている「区切りの技術」
*2 Apple|iPad Air
*3 リンクアンドモチベーショングループ|ストーリーテリングのメリットとは?
*4 STUDY HACKER|ジョブズも毎朝やっていた。脳科学者が教える「脳内トーク」のすごい力――行動も人生も変えられる!
*5 フォーブス ジャパン|相手を引き込むストーリーテリング 良い話し手になる7つのコツ
澤田みのり
大学では数学を専攻。卒業後はSEとしてIT企業に勤務した。仕事のパフォーマンスアップに不可欠な身体の整え方に関心が高く、働きながらピラティスの国際資格と国際中医師の資格を取得。日々勉強を継続しており、勉強効率を上げるため、脳科学や記憶術についても積極的に学習中。

