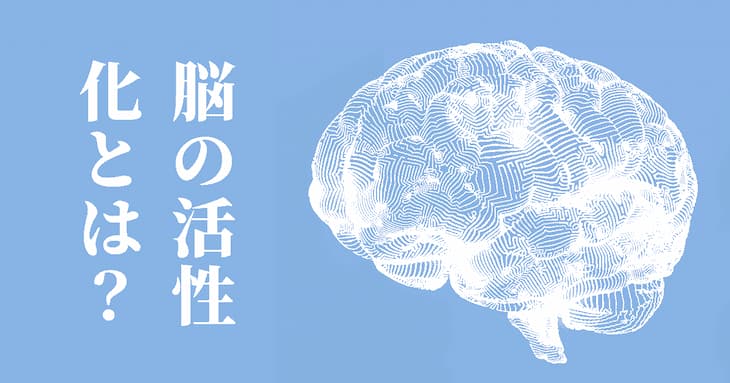
「脳の活性化に効く!」なんてキャッチフレーズは、あまりにも濫用されていてうさん臭い……。そんな風に考えている方もいらっしゃるかもしれませんね。
たしかに、脳は肉体のなかでも特に未知の領域。わかっていないことは多くあります。そして脳について数々の観察実験が行われているものの、結果は実験の細かな条件に大きく左右されるため、「これは脳によい、悪い」と断定することが難しい状態です。
しかしもちろん、「脳の活性化」がデマだというわけではありません。今回は、脳の活性化とは何を意味しているのか、活性化させるとどのような利点が生まれるのか、そしてどうすれば脳が活性化するのかをご紹介します。
脳の活性化とはどういうことか
「脳の活性化」という言い回しは、そもそも何を意味しているのでしょうか? それを明らかにせず、脳の活性化について語ることはできませんよね。
結論を述べると、脳の活性化とは「脳血流が上昇する」ことです。脳の活性化に関する実験においては脳血流を測定して、脳血流が上昇したことを「脳が活性化している」と判断することが多いようです。つまり、「脳を活性化させる」とは、「脳血流を上昇させる」ということなのです。なお、反対に脳の血流が低下することは、認知機能の低下を招くとされています。

脳が活性化する方法
「脳の活性化」の方法はあるのでしょうか? 脳の活動についてまだわかっていないことが多いとはいえ、少なくとも脳血流は神経活動と関係しているそうです。国立研究開発法人・日本医療研究開発機構によると、脳の神経活動が起こると酸素が消費され、減った分の酸素を補うため、一時的に脳血流量が増えます。また日本比較生理生化学会によれば、神経が活動すると血管が拡張するため、血が流れやすくなって脳血流量が増加するのだそうです。
つまり、神経を活発に働かせることが「脳の活性化」につながるのですね。神経を活動させるにはいくつもの方法があります。
本を読む
ニンテンドーDS専用ゲームソフト『脳を鍛える大人のDSトレーニング』の監修などで知られる医学博士の川島隆太教授(東北大学)によると、被験者たちに「日本語の現代文を黙読」してもらったところ、視覚処理情報を処理する脳の部位「後頭葉」、思考や創造性を担う「前頭前野」などの神経細胞が活性化したそうです。また教育工学を専門とする磯野春雄氏らの研究によって、電子書籍の読書も前頭前野を活性化させることがわかっています。皆さんも、文字を認識したり、書かれていることについて頭のなかでイメージを膨らませたりすると、脳が働いているのを感じた経験があるのではないでしょうか。
さらに、声を出して本を読む「音読」をすると、脳はますます活性化するようです。
音読で使用される感覚は、文字を読み取る「視覚」とそれを再び聞く「聴覚」。そして、音読で生じる処理とは、「文字を読み取る」「読んだ文字の意味を理解する」「理解した文章を声に出す」「声に出した文章を音として聞く」「音として聞いた文章を再び理解する」と多岐にわたります。 音読は、これら非常に多くの処理を同時にこなす複雑な行為。これにより前頭前野を中心として脳全体が満遍なく利用され、結果的に脳が活性化されるのです。
(引用元:StudyHacker|音読の効果で脳が活性化! 知識が増え、ストレスも軽減、良いことだらけの音読を始めよう)
計算
川島教授によると、足し算・引き算など簡単な計算を行っているとき、前頭前野、後頭葉、計算したり体の感覚を認識したりする「頭頂葉」が活性化するそう。そして、複雑な問題よりも単純な問題を解いているとき、じっくり考えているときよりも急いで解いているときほど、前頭前野が活性化するそうです。
新しいこと・難しいことへの挑戦
脳科学者の茂木健一郎氏によると、新しいことや難しいことにチャレンジしたとき、脳内で「ドーパミン」が分泌されて脳が活性化するそうです。ドーパミンとは、神経細胞から放出されて別の細胞に興奮/抑制の作用を引き起こす「神経伝達物質」の一種。公益財団法人・東京都医学総合研究所の客員研究員である渡邊正孝氏によると、前頭前野が効率的に働くには適量のドーパミンが必要なのだそう。つまり、普段のドーパミン分泌が少ない人が、新しいことや難しいことに挑戦すると、ドーパミンが分泌されて適量となり、前頭前野がうまく働くのだといえます。
人と笑顔で楽しくつきあう
脳生理学者の有田秀穂氏によると、家族や恋人と親密なコミュニケーションをとることによって、ホルモンの一種「オキシトシン」が分泌されます。そして精神医学を専門とする山末英典教授(浜松医科大学)らが行った臨床試験では、自閉症スペクトラム障害の患者にオキシトシンを投与したところ、前頭前野の一部である「内側前頭前野」が活性化し、コミュニケーションにおける障害が改善したそうです。
また、作業療法を専門とする山田英徳教授(常葉大学)の実験でも、微笑んだり微笑みを向けられたりした人の前頭前野において脳血流量が増えることがわかりました。親しい間柄の人と微笑み合った場合、特に脳血流量が多かったそうです。仏頂面より笑顔をつくるほうが、脳の活性化の方法として効果的ということですね。

脳の活性化の効果
脳が活性化するとどのような効果が生まれるのでしょうか? 上記の説明で何度も出てきた「前頭前野」。これは、脳のなかでも特に大事な部分だと考えられています。前頭前野がうまく働くと、仕事や勉強などさまざまな活動によい影響を与えるとされているのは周知のとおりです。
セロトニン研究の第一人者で脳生理学者の有田秀穂氏は、この部分を“人間のこころ”と表現しています。【前頭前野】には、「考える・記憶する・アイデアを出す・感情をコントロールする・判断する・応用する」といった働きがあります。脳を人間のコンピューターとするならば、【前頭前野】はコンピューターのなかのコンピューター。 つまり【前頭前野】の役割は、「人間を知的かつ理性的にすること」なのです。
(引用元:StudyHacker|カギは “楽しさ” を供給すること。脳の「前頭前野」を活性化させて仕事の効率を高めよう。)
脳には前頭前野のほかにもさまざまな部位があります。たとえば、「海馬」は日常の出来事に関する記憶を形成したり思い出したりするのに必要な脳領域です。筑波大学などの共同研究グループによると、被験者たちに10分間のペダリング運動をさせたところ、海馬が活性化し、記憶力テストの成績が向上したそう。つまり、海馬が活性化すると記憶力がよくなるのです。脳の活性化の効果としては、まず「記憶力の向上」が挙げられるということです。
人間は生きていく過程において、さまざまな仕事や家事をこなしたり、他者とコミュニケーションを取ったりしています。これらのことをうまくこなして豊かな人生を送るには、脳が活性化していないよりはしているほうがよい、ということに議論の余地はほぼないといえるはずです。では、どうすれば私たちの脳は活性化しやすくなるのでしょう? 次からは脳を活性化させる方法をご紹介します。

脳の活性化と運動の関係
運動と脳の活性化には密接な関係があることをご存知ですか? 運動が脳を活性化させることは、よく知られるようになりました。上述したように、10分間のペダリング運動という「超低強度運動(※)」によって海馬が活性化し、記憶力テストの成績が向上したという実験結果があります(※若者の場合で心拍数が100以下の、かなり楽な運動)。運動によって脳が活性化するメカニズムは、次のとおり。
運動する際には、脳から筋肉や関節等の運動器に指令が下されます。この時、単に脳が一方的に命令をしているわけではなく、運動器から脳へも命令信号が送られているのです。そうして相互に刺激し合うことで、脳が活性化します。 また、運動をすることで、脳の神経細胞であるニューロンを増やす効果があることも分かっています。さらに、認知機能を高めるために必要な神経結合を増やしたり、ドーパミンやセロトニンといった思考・感情に関わる神経伝達物質の分泌を促したりする効果もあるのだそう。
(引用元:StudyHacker|「運動が脳に効く」はもはや常識! ハードな運動は不要 “脳フィットネス” で、生産性アップを。)
脳を活性化させるための運動は、自転車をこいだりジョギングをしたりといった程度で充分。また、階段の上り下りはジョギングと運動強度がほぼ同じという見解もあるので、「エスカレーターもエレベーターも使わない」というルールを自分に課すのも効果的です。体力がつくだけでなく、脳の活性化に効くなんて、一石二鳥ですね。運動と脳の活性化の関係を見逃すことはできません。

脳の活性化に効く体操
脳を活性化させるには、外での運動だけでなく、室内での簡単な体操も充分な効果があります。脳の活性化に効く体操をご紹介しましょう。
指の体操
- 卵を包みこむように、両手の指先をそれぞれ合わせる。
- 左右の親指を、互いにぶつからないよう時計回りに20回まわす。
- 今度は半時計回りで20回まわす。
- 人差し指から小指まで同様に行う。
上半身の体操
- 手のひらを上にした状態で右腕を前に伸ばす。
- そのまま、右手のひらを反り返らせる。
- 右手の指を、左手の指で体側にぐっと引き寄せる。
- 右のひじ裏を伸ばすことを意識しながら、3回深呼吸する。
- 左腕で同様に行う。
下半身の体操
- 仰向けに寝転ぶ。
- 両足を10cmほど上げる。
- 息を吐きながらゆっくり両脚を上げていく。
- 脚と床が45度になったら、5秒間姿勢をキープ。
- 息を吐きながらゆっくり元の体勢に戻る。
- 1~5を15回繰り返す。

脳の活性化に効く食べ物なんてあるのでしょうか? 運動が面倒な人には気になるところですよね。
脳が活性化しやすくなる食品とは、つまり脳血流を上昇させてくれる食品です。特定非営利活動法人・日本食品機能研究会によると、脳血流を活発化させる成分のひとつが「GABA(gamma-aminobutyric acid、ガンマアミノ酪酸)」。チョコレート製品の商品名として、一躍知られるようになりましたよね。
農学博士の横越英彦教授(中部大学)が代表を務める「ギャバ・ストレス研究センター」の話では、現代人は30mg以上のGABAを摂取するべきとのこと。横越教授によると、発芽玄米には100gあたり10mgのGABAが含まれているそうです。また、カルビー株式会社の研究開発本部は、100gのじゃがいもに20~40mgのGABAが含まれていると説明しています。じゃがいも1個の重さが150g程度なので、じゃがいもを1つ食べれば充分な量のGABAが摂取できそうですね。
アミノ酸などファインケミカルを扱う協和発酵バイオ株式会社が運営する「シトルリン研究会」によると、アミノ酸の一種「シトルリン」にも脳血流を活発にする効果があります。シトルリンには一酸化窒素を増やす効果があり、一酸化窒素は血管を広げるのだそうです。
血管内科学などを研究する林登志雄教授(名古屋大学)によると、シトルリンを多く含む食べ物とは、スイカ。100gあたり180mgのシトルリンが含まれているそう。シトルリンの一日あたり摂取量目安は800mgで、スイカおよそ1/7個に相当します。1/7個ならなんとか食べられそうですが、毎日食べるのは難しいですし、スイカが出回らない季節もあるので、サプリメントによる摂取が現実的だといえます。
食品が含む成分以外にも注目してみましょう。よく知られているのが、「噛(か)むと脳が活性化する」ということ。噛むという行為は単に顎と歯を動かすだけでなく、脳の高度な機能と関係しているそう。歯学博士の志賀博教授(日本歯科大学)らの実験によると、ガムを噛んでいるあいだの脳血流量は有意に増えているため、ガムを噛むことが脳の活性化につながることが明らかになりました。神経生理学を専門とする柿木隆介教授(生理学研究所)は、ガムが脳を活性化させる効果を以下のように強調しています。ガムも脳を活性化させる食べ物だといえるでしょう。
記憶力、思考力、認知力、集中力、精神安定力がアップし、脳の活性化につながります。ガムほど歯の奥を持続的、かつリズミカルに刺激できるものはありません。ガムを噛めば午後の眠たい会議も乗り切れますし、集中力が増していい発想が生まれるかもしれません。
(引用元:日刊ゲンダイヘルスケア|噛むと脳活性化なのに…若者「ガム離れ」なぜ起きた?)

脳の活性化に効く食べ方
脳の活性化のためには、食べ方も見逃せません。脳を活性化させるためには、「何を食べるか」だけでなく「どのように食べるか」も重要なのです。食事のしかたは、記憶を司る脳の部分「海馬」の体積に影響を及ぼすそう。そして、海馬の体積が大きくなるほど、記憶力も高くなるらしいのです。
北米神経科学学会によると、60代の被験者400人の脳を調べたところ、肥満者の海馬はそうでない人よりも小さく、萎縮していくスピードも速いことが明らかになりました。そのため、海馬を健康に保ちたいのであれば、太り過ぎないように食事の内容や時間帯に配慮する必要があります。
また、海馬などが担当している認知機能は、ドーパミンと関係しています。脳内のドーパミンが少なくなりすぎると、記憶力や注意力が低下してしまうのです。ドーパミンを生産するのに効果的な食事法は、「空腹になること」および「おいしいものを食べること」。空腹感を覚えるまで間食を我慢し、それからおいしいものを食べると、ドーパミンが出て脳が活性化されやすくなるといえます。これが、脳の活性化に効く食べ方です。

脳の活性化に効くゲーム
家族や友人と楽しめる、脳の活性化に効くゲームもあります。カードゲーム「UNO」で知られる玩具メーカー・マテル社の日本法人であるマテル・インターナショナル株式会社が行った実験によると、スマートフォンの対戦ゲームアプリケーションよりも、ボードゲームで遊んでいるときのほうが、脳血流量が多いそうです。実験を監修した精神科医の古賀良彦氏によると、「常に相手の先を読むような戦略性を必要とする点」「目の前にいる相手とのコミュニケーションを自然と促す点」が関係しているのだとか。
たしかに、ボードゲームで遊ぶ際は、たいてい相手と向き合った状態です。表情の変化もよく読み取れるため、脳の多くの部分が活発になるのかもしれません。脳の活性化に効くゲームとは、コミュニケーションをとりながら遊べるゲームといえるかもしれませんね。
***
脳が活性化していると、仕事や勉強などさまざまな物事がはかどって気持ちのよいものです。上で紹介した方法を、ぜひ試してみてください。
(参考) 京都大学|脳の血流低下が認知機能障害を引き起こす -脳の免疫細胞「ミクログリア」による脳内炎症と白質傷害が原因か- 国立研究開発法人日本医療研究開発機構|脳の神経活動の空間パターンは脳血流のパターンに写し取られる―安静時脳活動の詳細な時空間構造を神経発火と脳血流の両面から解明― JSCPB wiki|脳の血流調節メカニズム 志村尚夫, 天道佐津子監修, 天道佐津子編著 (2011), 『読書と豊かな人間性の育成 改訂版』, 青弓社. 脳科学辞典|前頭前野 J-STAGE|電子書籍の読取りおよび聴き取りをした場合の脳活性化と内容理解度 J-STAGE|微笑みと脳血流について J-STAGE|ポジトロンCTで測定した正常若年者と高齢者の咀嚼時の局所脳血流の変化 J-STAGE|近赤外分光装置によるチューインガム咀嚼時の脳内血流の変化 StudyHacker|音読の効果で脳が活性化! 知識が増え、ストレスも軽減、良いことだらけの音読を始めよう StudyHacker|カギは “楽しさ” を供給すること。脳の「前頭前野」を活性化させて仕事の効率を高めよう。 StudyHacker|脳を育てる “戦略的な” 食事習慣。「空腹 × おいしいもの」で脳力は劇的にアップする。 StudyHacker|「運動が脳に効く」はもはや常識! ハードな運動は不要 “脳フィットネス” で、生産性アップを。 StudyHacker|筋トレで記憶力がアップする。脳も鍛えてくれる偉大な『筋トレ』のチカラ StudyHacker|受験の世界で注目! “指回し体操” が脳をフル稼働させる。速読にも効果が。 StudyHacker|疲れがたまりすぎる前に。1日 “数分” でできる疲労回復習慣を取り入れよう。 まなびの杜|特集 脳科学レポート サイエンスポータル|インタビュー 東北大学 加齢医学研究所 教授 川島隆太 氏「道を拓く- Frontiers - 脳のメカニズムに迫る」 プレジデントオンライン|「ファーストキス」のドキドキ感が脳を活性化させる PHPオンライン 衆知|「脳の疲れ」がスーッととれる!“癒しホルモン”オキシトシンの増やし方 理化学研究所|海馬から大脳皮質への記憶の転送の新しい仕組みの発見 ARIHHP|★【プレスリリース】短時間の軽運動で記憶力が高まる!~ヒトの海馬の記憶システムが活性化されることを初めて実証~ 日刊ゲンダイヘルスケア|噛むと脳活性化なのに…若者「ガム離れ」なぜ起きた? ギャバ・ストレス研究センター|GABAとは? レシピ大百科【味の素パーク】|食材の目安量 公益社団法人 日本生化学会|動脈硬化とアルギニン、シトルリン 一般社団法人ディベロップメントシニアPCコミュニティ|肥満は認知症につながる 東邦大学医療センター大森病院 臨床検査部|ドーパミンとパーキンソン病 NIKKEI STYLE|毎日「指先体操」脳を活性化・準備いらず PR TIMES|スマホ時代に激震!これからはスマホゲームよりボードゲームを買うべき!?ボードゲームは“脳の司令塔”である前頭葉を活性化!
STUDY HACKER 編集部
「STUDY HACKER」は、これからの学びを考える、勉強法のハッキングメディアです。「STUDY SMART」をコンセプトに、2014年のサイトオープン以後、効率的な勉強法 / 記憶に残るノート術 / 脳科学に基づく学習テクニック / 身になる読書術 / 文章術 / 思考法など、勉強・仕事に必要な知識やスキルをより合理的に身につけるためのヒントを、多数紹介しています。運営は、英語パーソナルジム「StudyHacker ENGLISH COMPANY」を手がける株式会社スタディーハッカー。

