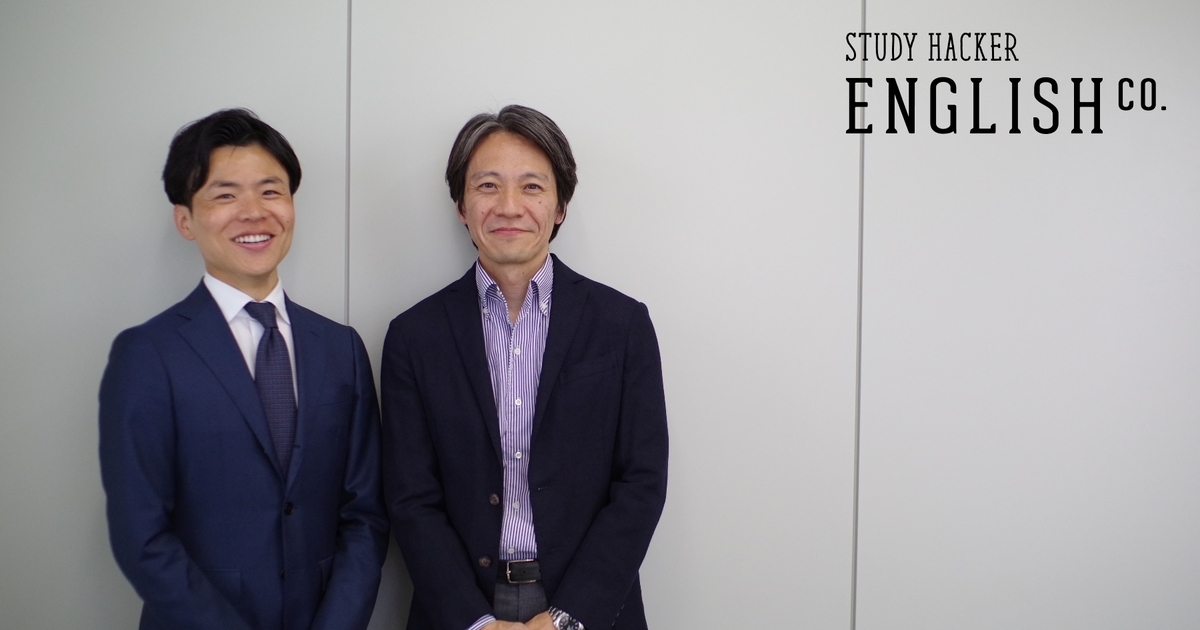
「研修を導入したが、思うような成果が出ない」「受講者のモチベーションが続かない」──こうした悩みを抱える研修担当者は少なくありません。特に英語研修は、業務時間外での学習も必要になるので、継続に頭を悩ませやすい研修の一つです。
そのような中、株式会社NTTドコモのマーケティング戦略部では、2024年から英語研修「ENGLISH COMPANY for biz」を導入し、累計16名が継続的に受講、TOEIC最大340点アップ、シリコンバレー海外研修2名輩出、MBA留学成功者1名など、目覚ましい成果を上げています。
研修成功の要因は、正しい研修ベンダーの選択だけではありません。むしろ重要なのは、受講者が自然と「やりたい」と思える社内の仕組み作りです。
今回は、英語研修導入を先導し、自らもVERSANT 37点から56点への大幅スコアアップを実現したNTTドコモマーケティング戦略部 料金戦略担当部長の内山清人様にお話を伺いました。内山様のお話から見えてきた研修成功の原則には、行動経済学の「ナッジ理論」が効果的に活用されていました。
NTTドコモ様、研修成功の3つの秘訣
- 本人の意思による手挙げ制を基本とし、強制ではなく自主性を重視
- 負担が大きすぎない適切な強度の研修プログラムを厳選
- 上長自らが学習する姿を見せて英語学習への意欲を後押し
これらの仕掛けには、人の行動を自然と望ましい方向に導く「ナッジ理論」の考え方が隠されていたのです。
内山清人様プロフィール
株式会社NTTドコモ マーケティング戦略部 料金戦略担当部長。ドコモMAXなどの料金プランや爆アゲセレクションなどのサービス開発を手がける。グローバルテック企業とのアライアンスを担当し、部署の英語研修を統括。自らもENGLISH COMPANY for bizを受講し、VERSANT 37点から56点への大幅スコアアップを実現。
*内山様の肩書は取材当時(2025年6月末)のものです。
NTTドコモの英語研修体制とは?
内山様: グローバルのビッグ・テック企業とのアライアンスが本格化し、英語でのビジネスコミュニケーションが必須となりました。以前は通訳を介していましたが、より直接的で深いコミュニケーションの必要性を感じ、2024年から本格的な英語研修を導入しました。
内山様: 基本的に手挙げ制です。英語を使う業務に携わるチームを中心に対象者を選定しますが、強制ではなく「こういうのがあるけど、やりたい人」ということで募っています。自分で手を上げてもらわないと、結局続かないんですよね。
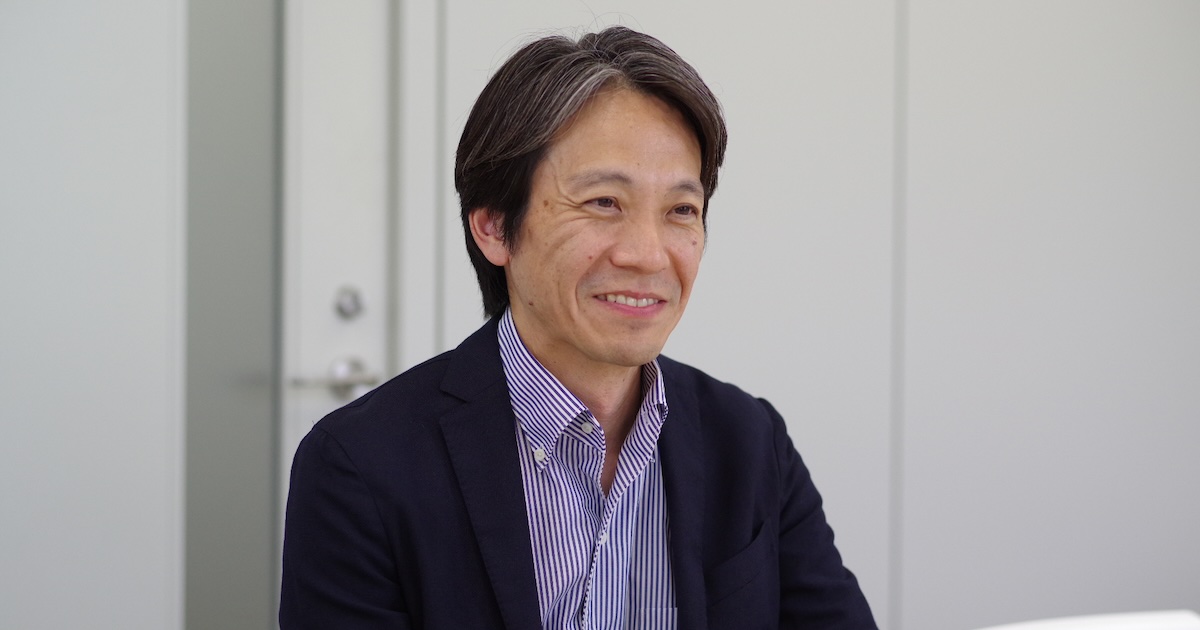
内山様: おっしゃるとおりです。毎日忙しいので、負担が大きい研修だと続かなくなってしまうので、一定の強度はありつつ、効率的で現実的な英語研修先を選ぶことにしました。
他社との比較検討の結果、ENGLISH COMPANY for bizは一人ひとりの課題解決型で短期集中のプログラムなので、私たちの業務の忙しさを考慮すると、最も適していると判断しました。業務時間外の学習時間があまりに長すぎると、若いメンバーから「仕事も忙しいし、そこまではできません」と断られることも想定していました。
内山様: 我々は国内事業が中心の会社なので、海外の方と話す機会や英語を使う機会はどうしても少なくなってしまいます。ただ、私自身、30代のときの出向を通して、ビジネスパーソンとして英語が使えて当たり前なんだという世界をたくさん見てきました。
ですので、自分の経験を踏まえて20代のメンバーには繰り返し「英語はいずれ必要になるから」「早くスタートするに越したことはない」と伝えています。今この部署で英語を使わなくても、彼らが将来いろんな部署に行ったときに「あの時、英語を学んでいたから今がある」となればいいなと思って、人材投資として研修をやらせています。
NTTドコモの成功の秘訣には行動経済学の「ナッジ理論」が隠されていた!
内山様:どうすれば部内のメンバーにとって一番良い研修ができるだろうか、と考えたら自然とそうなっていたのかもしれません
ナッジ理論とは?
ナッジ理論とは、人々を強制することなく、より良い選択を自然に促す手法のことです。2017年にノーベル経済学賞を受賞したリチャード・セイラー教授が提唱し、現在では企業の人材育成や組織運営において広く活用されています。
「ナッジ(nudge)」は「軽く肘で押す」という意味で、相手に気づかれないよう自然に望ましい行動を促すことを指します。内山様の事例では、強制的な研修参加ではなく、自然と「やりたい」と思える環境作りを行っており、これはまさにナッジ理論の実践といえるでしょう。
ナッジ理論についてより詳しく知りたい方は→ナッジ理論の効果的な活用法
自分が英語学習をしている姿を見せる
内山様: 私自身が、誰よりもちゃんと英語学習に取り組んでいました。直接メンバーに言うことはありませんが、一番忙しい私が英語学習をやっているのを見せるのは効果的かと思いまして(笑)。
学習時間を確保できないメンバーには、講師の方を経由して指導してもらっています。担当部長である私から直接言うとプレッシャーになってしまいますから。一方で、私は「これだけやっているよ」という形で、さりげなく伝えています。
例えば、毎回の宿題の仕上がりについて、「こういうふうにやっているんだよね」と、さりげなく伝えて、「担当部長も、そんなにやっているんだ」っていうふうに背中を見せるようにしています。
英語研修を導入して、一番うれしかった瞬間
内山様: 嬉しかったのは、同じチームの英語が堪能な若手に、2年ぶりに英語を話している姿を見せたときのことです。「内山さん、めちゃくちゃ話せるようになっていますね!」と驚かれました。衝撃的だったみたいです。
実は2年半前、海外の方がいらしたときに質問をしようとしたのですが、うまく通じませんでした。その様子を見ていた彼は「内山さんはそんなに英語得意じゃないんだな」と思ったそうです。今年3月の海外出張では、パートナー企業とのミーティングで冒頭の挨拶から自分の意見まで、すべて英語で話すことができました。その様子を見たチームメンバーの2人が「私たちももっと英語勉強しなきゃと思いました」と言ってくれました。それが私にとって一番嬉しいエピソードでした。
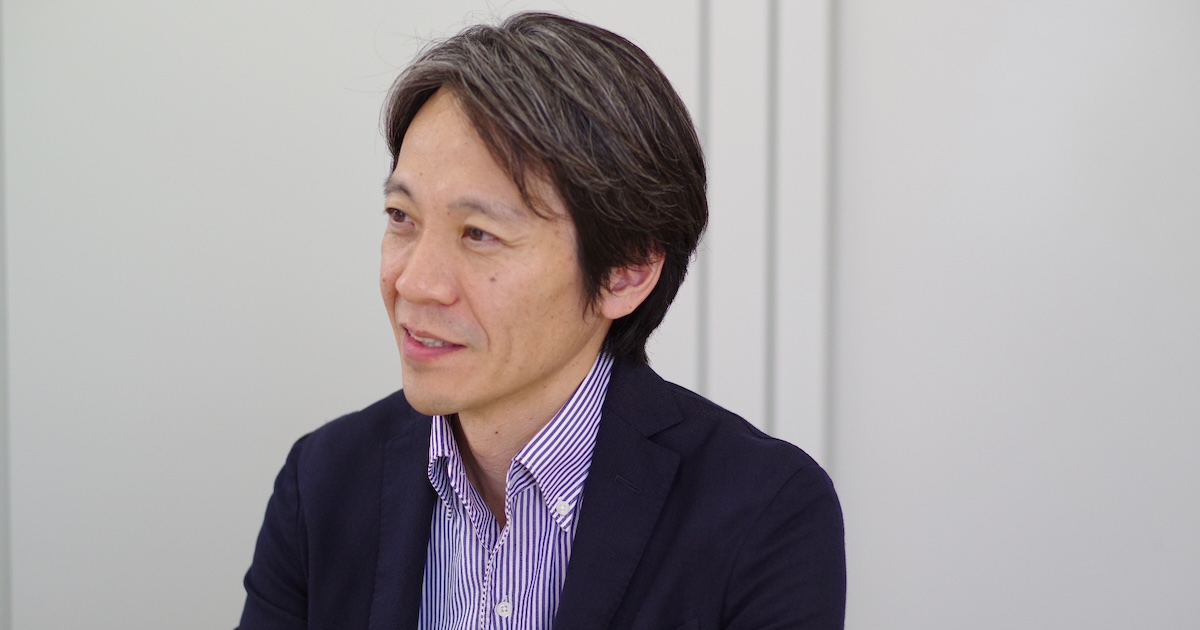
意外なところにも反響が……
家族にも英語学習の好循環が生まれました。
現在高校2年生の娘が、私が英語学習をしている姿勢に刺激を受けて、英語の勉強に対してより真剣に取り組むようになりました。「英語のこの問題わからないから教えて」と相談してくるなど、家庭内でも英語学習の好循環が生まれています。自宅で勉強している姿を見せるのが、効果的なのだと思っています。
社内コミュニケーションも活発に
内山様: 若いメンバーと担当部長という立場の違いがあるので、なかなか会話しづらいことも多いのですが、今回の英語研修を話題にして、「この間、英語のテストを受けてすごく上がっていたよね」などの会話から、コミュニケーションが活発になりました。共通の話題があると、やはり距離が縮まりますね。
研修成功の「ナッジ」を設計せよ
NTTドコモの英語研修成功事例から見えてきたのは、単に良い研修プログラムを選ぶだけでは不十分だということです。重要なのは、受講者が自然と「参加したい」「続けたい」と思える環境の設計でした。
研修成功のための3つのナッジ
- 選択の自由を残す:手挙げ制で自主性を重視し、強制感を排除
- 負荷を適正化する:継続可能な強度の研修プログラムを厳選
- 社会的証明を活用する:上長自らが学習する姿を見せて行動を促す
内山様の事例が示すように、研修担当者自身が率先して学習に取り組む姿勢は、最も強力なナッジとなります。「一番忙しい担当部長がやっているのだから」という社会的証明が、部下のみなさんの行動変容を自然に促したのです。
さらに、英語学習は将来への投資であるという長期的視点で価値を伝え続けることで、若手社員の学習意欲を維持することに成功しています。
他の研修にも応用可能な普遍的原則
この事例は英語研修に限らず、DX研修、リーダーシップ研修、コンプライアンス研修など、あらゆる企業研修に応用可能です。強制ではなく、自然と「やりたい」と思わせる環境作りこそが、研修の真の成功を左右するのです。
あなたの会社の研修にも、効果的な「ナッジ」は設計されているでしょうか?
取材協力
株式会社NTTドコモ マーケティング戦略部
料金戦略担当部長 内山清人様
*内山様の肩書は取材当時(2025年6月末)のものです。
STUDY HACKER 編集部
「STUDY HACKER」は、これからの学びを考える、勉強法のハッキングメディアです。「STUDY SMART」をコンセプトに、2014年のサイトオープン以後、効率的な勉強法 / 記憶に残るノート術 / 脳科学に基づく学習テクニック / 身になる読書術 / 文章術 / 思考法など、勉強・仕事に必要な知識やスキルをより合理的に身につけるためのヒントを、多数紹介しています。運営は、英語パーソナルジム「StudyHacker ENGLISH COMPANY」を手がける株式会社スタディーハッカー。

