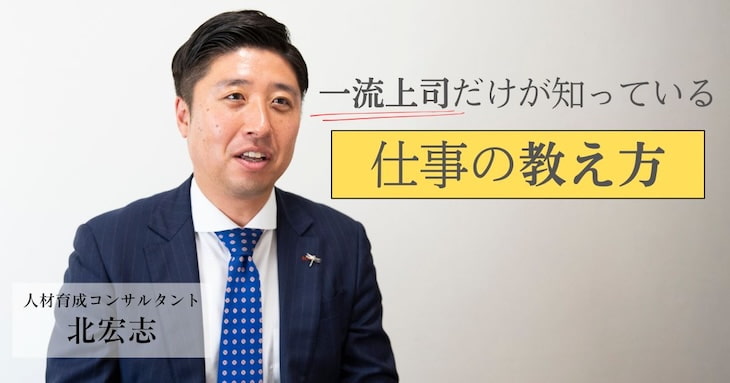
ビジネスシーンに限らず、世代間の価値観や思考などの違いから生じる問題は多いものです。組織内のことで言えば、「若い部下をどのように育てていいかわからない」という上司の悩みなどはその典型ではないでしょうか。そこでお話を聞いたのは、主にZ世代など若手社員の研修に定評がある人材育成コンサルタントの北宏志さん。「いまは若手の育成が難しくなっている」と言う北さんの言葉の真意に迫ります。
構成/岩川悟 取材・文/清家茂樹 写真/石塚雅人(インタビューカットのみ)
【プロフィール】
北宏志(きた・こうじ)
1983年8月9日生まれ、北海道出身。人材育成コンサルタント。株式会社ポールスターコミュニケーションズ代表取締役。大学卒業後、立命館大学に関係する中高一貫校で社会科教諭として6年間勤務。その後、「ララちゃんランドセル」を製造・販売する株式会社羅羅屋に転職。中国での3年間の駐在中は経営幹部として部下80名を束ね、中国国内の売上を3年間で9.7倍に拡大させ黒字化させる。帰国後、日本とアジアの架け橋となって教育をよりよくしていきたいという思いから、人材育成コンサルタントとして独立。Z世代の若手社員の研修を中心に全国35都道府県で1,000回以上の登壇実績をもち、これまでの受講生は2万5,000名を超える。受講者のやる気スイッチを入れる熱血講師として定評があり、「研修業界の松岡修造」の異名ももつ。大手企業や各種団体から依頼される研修・セミナーのリピート率は90%超。著書に『新しい教え方の教科書』(ぱる出版)、『ビビリの人生が変わる 逆転の仕事術』(三才ブックス)がある。
いまという時代だからこそ、「教え方」を学ぶ必要がある
ジェネレーションギャップという言葉を誰もが知っていることからもわかるように、上司の立場にある人間が若い部下を育てる、適切な仕事の進め方を教えることは、時代を問わずこれまでもビジネスにおける大きな課題のひとつでした。ただ、その難しさは以前より増していると思います。
その理由のひとつは、いまの若い世代はいわば「理不尽」を経験していないことにあります。40代の私が子どもの頃もそうでしたが、かつてであれば、家庭でも学校でも、親や先生、怖い先輩などから理不尽に怒られることも珍しくありませんでした。そのなかで、「部活の先輩が怖いから、しっかりあいさつしないといけない」「今日はなぜか先生の機嫌が悪いから、きちんと掃除をしよう」というように、「察する」力を培えたのです。
ところが、いま同じような態度を先輩や先生が見せれば、いじめだとかパワハラだというようにすぐに非難されてしまうでしょう。そのため、若い世代は子どもの頃から理不尽に接する機会が少なく、察することが苦手になっています。
現在、上司の立場にある人の多くはそれこそ理不尽を経験してきたことで、社会人になってからも、「先輩がこういうときは、こうしたほうがいい」と察することができました。そして、「仕事は見て覚えろ」とか「とやかく言わず、言われたとおりにやっておけ」といった無茶な指示にも素直に従ってきたのです。
逆に言うと、現在の上司の大半は、若手の育て方や仕事の教え方をまともに教わることがないまま、上司という立場になってしまったことになります。だからこそ、自分たちとは異なる環境で育ってきた若手に対する仕事の教え方を学ぶ重要性が増していると私は見ているのです。

教え方以前に重要なのは、部下との「関係性構築」
ただし、それ以前に重要なのは、若い世代とのあいだの「関係性の構築」です。マサチューセッツ工科大学のダニエル・キム教授が提唱した「成功循環モデル」が、その裏打ちとなります。
成功循環モデルとは、組織が持続的に成長して成果を挙げるためのフレームワークであり、その好循環は、組織内の人間関係、コミュニケーション、信頼関係など「関係の質」を高めることから始まるとされています。
考えてもみてください。いくらよりよい教え方を学んで、「こうしたほうがいいよ」と若手に伝えたところで、関係性ができていなければその言葉が相手に響くことはないはずです。部下からしても、普段は顔も合わせず名前しか知らないような上司が突然やってきて指示をされても、「誰ですか?」といった印象しかもたないでしょう。
では、その関係性を築くにはどうすればいいでしょうか? 私は、「仕事以外の話をする」のがそのスタートなのだと考えています。いまなら、たとえば「パートナーはいるの?」なんて聞いてしまえばもちろんアウトですが、それでも仕事以外のところでのパーソナリティーを互いに知ることができなければ、心理的距離が縮まることはありません。
私からおすすめするのは、「休み、なにしてたの?」という質問です。「アニメを観ていました」と返ってきたなら、「なんて作品?」「どういうアニメが好きなの?」というように、そこから雑談をさらに発展させていきます。そのなかで趣味などに共通点が見つかればしめたもので、部下との関係は一気に好転していきます。
そうでなくとも、若い部下からすれば、先輩や上司が自分に興味をもって話を聞いてくれたり共感してくれたりしただけでも嬉しくなるものですし、「こんな先輩にだったら」と、自ら積極的に自分のことを話したくもなるはずです。

いつもは放任し、部下の緊急時こそが上司の出番
では、肝心の教え方について解説します。これについて詳しく述べるとそれこそ私の著書のように1冊の本になってしまいますが、なかでも特に重要な考え方についてお伝えしましょう。
まず「これは絶対にNG」という三流のマネジメントは、「自分の思い通りに部下を動かそうとする」ことです。当たり前かもしれませんが、部下を自分の「手下」のように考え、思い通りに動かすためにがちがちに締め上げた指導をする人もいまだにいるのです。もちろん、これは時代錯誤の方法だと言わざるを得ません。
続いて、二流のマネジメントは、「細かく確認する」というもの。業務の漏れやミスを防ぐためには有効だと思えるかもしれませんが、こうしたマイクロマネジメントをされた部下の側は、「信用されていない」「自分の能力を疑われている」と感じてしまいます。つまり、適切に教えるための大前提である関係性構築を妨げることになるのです。
一方、一流が行なっているマネジメントは、「いつもは放任し、緊急時には的確なアドバイスをする」というものです。もちろん全員が全員ではありませんが、終身雇用制や年功序列制が崩壊したと言われるなかでキャリアをスタートした若い世代の多くは、将来的な転職も見越して強い成長意欲をもっています。
だからこそ、まずは部下の「このように仕事を進めたい」という気持ちを尊重してあげましょう。そのうえで、部下が行き詰まってしまったときこそ、上司の出番です。「この仕事、どのように進めたいと思ってる?」と部下の考えを確認したうえで、「だったら、こういうやり方もあるし、こんなやり方もある」「こういう考え方も参考になるかもしれないよ」と、自らの経験や知識から選択肢を示したりアドバイスをしたりするのです。
部下の気持ちや希望を尊重しながら、対話を通じて仕事を教えていく――。そのようなスタイルがいまは求められているのではないでしょうか。

【北宏志さん ほかのインタビュー記事はこちら】
「だったら先に言ってよ……」部下のモチベが急降下する瞬間。伝わる「仕事の頼み方」とは?
「アイデアを出せ」と言う上司、「どうせ却下される」と思う部下。信用されない上司の “あの質問”
「Z世代の部下が何を考えているのかわからない……」と悩む上司が知るといい7つのこと
Z世代の心にはこの言葉が響く。若手部下に問題点を指摘するときは「○○」と言うのが効果的
Z世代が信頼を寄せるのは○○な上司。若手といい関係を築ける上司が大事にしている日常習慣
清家茂樹(せいけ・しげき)
1975年生まれ、愛媛県出身。出版社勤務を経て2012年に独立。ジャンルを問わずさまざまな雑誌・書籍の編集に携わる。


