
「ChatGPT」に代表される「生成AI」の登場により、それらを活用した新しい働き方がビジネスシーンに広まりつつあります。一方で、「ChatGPTは知っているけれど、仕事で使うことがないからよくわからない」という人もいるのではないでしょうか。ChatGPTを活用するための「最初の一歩」について、世界的な総合コンサルティングファームであるアクセンチュアでAI・アナリティクス部門の日本統括を務める保科学世さんにアドバイスをもらいました。
構成/岩川悟 取材・文/清家茂樹 写真/石塚雅人
【プロフィール】
保科学世(ほしな・がくせ)
アクセンチュア株式会社 執行役員。データ&AIグループ日本統括 AIセンター長。アクセンチュア・イノベーション・ハブ東京共同統括。慶應義塾大学大学院理工学研究科博士課程修了。博士(理学)。アクセンチュアにてAI・アナリティクス部門の日本統括、およびデジタル変革の知見や技術を結集した拠点「アクセンチュア・イノベーション・ハブ東京」の共同統括を務める。『AI HUBプラットフォーム』や業務領域ごとに体系化したAIサービス群『AI POWEREDサービス』などの開発を統括するとともに、アナリティクスやAI技術を活用した業務改革を数多く実現。『データドリブン経営改革』(日経BP)、『責任あるAI』(東洋経済新報社)など著書多数。厚生労働省保健医療分野AI開発加速コンソーシアム構成員などを歴任。一般社団法人サーキュラーエコノミー推進機構理事。
生産性向上こそ、生成AI活用の最大のメリット
2022年末に「ChatGPT」が登場し、「生成AI」という言葉が知られるようになると同時に、ビジネスシーンでも生成AIが徐々に活用されるようになってきました。読者のみなさんのなかにも、たとえば外国語の翻訳や議事録作成などに使っている人もいるのではないでしょうか。
しかし、生成AIにできることはそれだけではありません。ビジネスで活用できるシーンで言うと、会社のブログ記事やメールなどの文章作成から校正、長文の要約、プレゼン資料の作成、ウェブサイトやSNSに掲載する画像の作成まで、枚挙にいとまがないほどです。
そういった生成AI活用の最大のメリットは、労働生産性の向上です。日本のビジネスシーンでは、もう何年ものあいだ効率化の必要性が声高に叫ばれてきました。事実、公益財団法人日本生産性本部が2023年末に公表した数字を見ると、2022年における日本の時間あたりの労働生産性はOECD(経済協力開発機構)加盟38カ国中30位、ひとりあたりの労働生産性は31位と低迷しています。しかも、この数字はデータ取得可能な1970年以降で最低位と、改善するどころかむしろ悪化しているのです。
そもそも、日本は深刻な人手不足という大きな社会課題に直面しています。2024年9月に厚労省が公表した『令和6年版労働経済の分析』では、「2023年における求人の充足率はこの半世紀の中で最も低い水準。今後想定される人口減少を踏まえれば、過去の局面よりも人手不足は『長期かつ粘着的』に続く可能性」としています。人手が足りないということは、労働者ひとりひとりがより効率的に働かなければならないことを意味します。
こういった事実を背景として、労働生産性を上げていく必要性はこれまで以上に高まっていくでしょう。そのため、アウトプットまでの時間を大きく短縮しながら質も上げてくれる生成AIが心強い味方になると私は考えます。

「何でもよく知っている友だち」ができたと思って問いかける
生成AIが徐々に活用されるようになってきたと冒頭に述べましたが、実際には「ChatGPTは知っているけれど、使ったことがない」という人もいるでしょう。でも、決して難しく考える必要はありません。
生成AIに限らず新たに登場したツールには共通して言えますが、まずとにかく「使ってみる」ことから始めてみましょう。人づき合いでも、実際に相手とコミュニケーションしてみないことには、なにが得意でなにが苦手な人なのかわかりませんよね? 生成AIだって同じなのです。
特にChatGPTは、膨大なテキストデータと高度なディープラーニング技術を用いて構築された、「LLM(Large Language Models/大規模言語モデル)」と呼ばれる、与えられた文章から自然な文章を生成することを得意としている生成AIですから、なおさらです。
なにか疑問をもったり悩んだりしたときには、「何でもよく知っている友だち」ができたと思って、ChatGPTに問いかけてみましょう。そうするうち、「こういうのが得意なのか」「こういうのは苦手そうだ」といったことが見えてきて、「こんな使い方ができるのでは?」といった新たな発想を得られることもあるはずです。
しかも、「何でもよく知る友だち」は、人間とは違って遠慮がいりません。「こういうことを聞くと変に思われるかな?」「いまは忙しそうだからあとにしよう」などと考える必要もなく、いつどんなときにでもあなたの都合のいいタイミングで気軽に問いかけていいのです。

AI時代により重要な「人の心を動かすスキル」
そうして生成AIを活用できるようになったら、意識してほしいポイントがいくつかあります。ここではそのなかでも「人の心を動かすスキル」を磨いておくことを挙げたいと思います。
たとえば、「ChatGPTがこう言っていた」というのと「〇〇さんがこう言っていた」では、同じことを伝えたとしても相手の受け取り方は異なるはず。なかには「ChatGPTのほうが信じられる」という人もいるかもしれませんが(笑)、できれば「あなたが言うなら信じよう」と言われる人になりたいですよね。
ですから、自分ならではの価値やブランド、あるいは「信用」と言ったほうがいいかもしれませんが、すなわち人間性を高めておくことは、他者との関わり合いが不可欠なビジネスパーソンにとって今後も変わらず大切であり続けると思います。
いかに生成AIを活用しようとも、仕事を進めるうえでは人間関係が必ず存在します。相手が同僚でも外部スタッフでもお客様でも、それぞれ相手に応じたアプローチやコミュニケーションといった、「人の心を動かすスキル」を磨いておきたいですね。
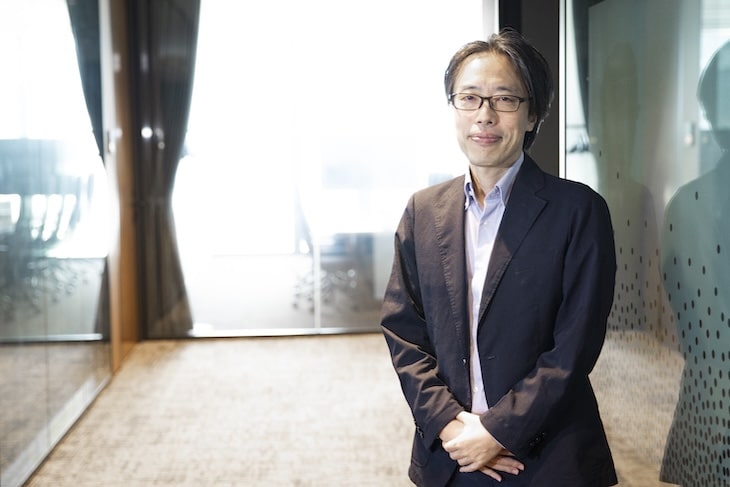
【保科学世さん ほかのインタビュー記事はこちら】
生成AIで「アイデア出し」が変わる。基本テクニック「あなたは○○です」の使い方
AIの影響を受けやすい「2つの職種」と、いますぐ磨くべき「コミュニケーションスキル」
清家茂樹(せいけ・しげき)
1975年生まれ、愛媛県出身。出版社勤務を経て2012年に独立。ジャンルを問わずさまざまな雑誌・書籍の編集に携わる。


