
皆さんは、「自分で考えて処理してください」と「考える力」を求められ、何をどうすれば良いかわからずお困りになったことはありませんか? 「考える力」とは、AI(人工知能)との共生社会を見すえ、ビジネスや教育の場でますます必要とされていく人間独自の能力です。ここではそんな「考える力」について定義し、「考える力」を鍛える方法やトレーニングツールなどをご紹介します。
- 「考える力」とは
- 自分で考える力がない人とは?
- 「考える力」と「書く力」の関係
- 「考える力」をつけるには1:目標を設定する
- 「考える力」をつけるには2:ニュースを利用する
- 「考える力」をつけるには3:能動的に読書する
- 「考える力」をつけるには4:ディベート思考を身につける
- 「考える力」をつけるには5:数字や地図を使って考える
- 「考える力」をつけるには6:ボキャブラリーを増やす
- 「考える力」をつけるには7:「フェルミ推定」に挑戦する
- 「考える力」をつけるには8:手帳を活用する
- 「考える力」を育てるアプリ
- 「考える力」が低下してしまう悪習慣
- これがおすすめ。「考える力」をつける本
「考える力」とは
IoT(Internet of Things)やAIの発展にともない、これからの時代に求められている「考える力」とは、課題を見つけ、解決のためのプロセスを選択し、新しい価値を生み出す能力のこと。言い換えれば深く考える力であり、思考力が類語にあたります。
2006年、経済産業省は長寿化・IoT・ビッグデータ・AIを特徴とする「第四次産業革命」を背景に、社会人として持つべき共通の能力として「社会人基礎力」を発表しました。そして2018年、「社会人基礎力」は時代の流れを反映した「人生100年時代の社会人基礎力」として再定義されました。社会人基礎力の1つに「考え抜く力」があります。
社会人基礎力としての「考え抜く力」は、以下の3つの力で構成されています。
- 課題発見力:問題を発見しソーシャルとビジネスを融合できる。
- 計画力:高い倫理観を持って正しい選択をし、未来を予測できる。
- 創造力:物事の要点をつかみ、価値判断できる。
日本では従来、記憶力ばかりを試すような試験制度などの影響により、処理能力に特化した人材が社会に多数輩出されてきました。結果として、指示待ち人間・マニュアル人間などと揶揄(やゆ)される、考える力の弱い大人が多くなってしまったといわれています。
京都大学デザイン学ユニット特定教授の川上浩司氏は、かつて取り組んでいた研究でAIに自ら考えさせることができなかった経験から、「深く考えること」は、人間の個性であり一番の強みであると痛感したそうです。川上氏は、思考することを、プロセスをたどりながら様々な新しい発見をして自分なりの答えを導き出す認知であると定義し、AI時代に人間が思考することの大切さを次のように語っています。
人間に備わった「考える」という強みを活かしてこそ、これから迎える「AI時代」を生き抜く原動力になっていく(中略)思考のプロセスを意識的に重ねることなく、頭に言葉を浮かべて「わかったつもり」で終わったり、何も考えずアクションを起こしたりするのではなく、「思考」を途中に挟んで自分らしさを強みとして加えてこそ、既存を超える「想定以上の成果」を生むことになるのだ。
(引用元:川上浩司(2017),『京大式DEEP THINKINGー最高の思考力』,サンマーク出版.)
まとめると、「考える力」には以下のような特徴があります。
- 課題を自ら発見できる能力である。
- 人間らしさの象徴である。
- AIが急速に成長していく現代では必須の能力である。

自分で考える力がない人とは?
自分で考える力がない人の特徴と、「考える力」がないと生じるデメリットを4つ挙げてみました。
知的好奇心が薄く、消極的
知的好奇心に欠けていると、そもそも「考える力」を発揮する機会を自力で発見できません。考える力を発揮できなかった結果、他人からもたらされた情報をうのみにしてしまい、誤りに気づかず大きな失敗をしてしまうでしょう。
また、知的好奇心を自分自身に向け自己分析する機会がないと、自分の「軸」となるものが持てずに自己肯定感が弱くなります。自己肯定感が弱くなると、自信がないため人の意見に振り回されてコロコロと言動が変わり、周囲の信用を失いかねません。
考える前に行動してしまう
考える前に行動してしまうと、目標が定まっていないためにやるべきことや道筋がはっきりわからず、時間を無駄に消費してしまうリスクがあります。また、斬新な発想に欠かせない「考えるための時間」を持たないため、既存の知識をまとめただけのありふれたアイディアしか思い浮かばず、時間をかけた割に成果が上がらないという最悪のケースに陥る危険性もあります。
自己中心的
自己中心的な思考しか持たない人は、物事を客観的な視点でとらえることができません。すると、思い込みによる勘違いに気づけず同じミスを繰り返したり、相手の主張が理解できず、誤解によってトラブルを引き起こしてしまったりするかもしれません。
自分の思いを言葉にできない
頭のなかで思いをめぐらせているだけで、日記を書いたり人に話したりなど、考えを整理・アウトプットする習慣がない人も、「考える力」がないといえます。思考を明確な言葉に変換できない人は、会議などの重要な場面で意見を求められたとき、うまく考えをまとめて発言することができません。
また、思考や感情をはっきりと言葉にできない人は、ボキャブラリーが少ないのかもしれません。すると、うまく言葉で表現できないかわりに感情的な振る舞いをしてしまい、冷静な議論を交わすことが不可能な事態を招く可能性があります。
「考える力」がないと、デメリットばかり。ビジネスパーソンでも学生でも、社会で周囲の人とコミュニケーションをとりつつ生きていくには、「考える力」が必要不可欠です。

「考える力」と「書く力」の関係
反対に、「考える力」を持っている人は、「書く力」も優れているという特徴があります。「考える力」は「書く」という行為で養われるからです。書くことで思考や感情を整理して、書いたものを読むことによって自分の感情・思考を客観視することができるのです。
言語化の習慣を身につけると、自分の思考・感情を客観的に見ることができるため冷静になれ、物事を的確に表現できる能力を養えます。考えや気持ちを書き出すことで、仕事や学業、生活などにおいて抱えている問題および解決方法が明確になるばかりでなく、書き留めておいたものから自分独自のアイディアが誕生し、大きな成功につながるかもしれません。
言語化の習慣を続けている1人に、ビジネス書のベストセラー『メモの魔力』の著者にして、ライブ動画ストリーミングプラットフォームを運営するSHOWROOM株式会社代表取締役社長の前田裕二氏がいます。
前田氏は、何かが気になったりアイディアが浮かんだりしたら、すぐに見開きのノートにメモをとるのだそうです。思いつきをメモすることにより、「事実を確認し、本質を抽出し、アイディアを生み出す」ことができるのだそう。自分の考えを書いて言語化するという人間ならではの能力は、AIと共存する時代に最も磨くべきスキルであると前田氏は指摘しています。
世界的に有名なコンサルティングファームのマッキンゼー・アンド・カンパニーで、経営改革に14年間携わった経歴を持つ赤羽雄二氏も、言語化を重視しています。「思考は言葉によってなされるのであり、頭に浮かぶことをメモするだけで深く考える力をつけられる」のだそうです。
書くという行為によって、思考・感情が整理され、アイディアが生み出しやすくなります。前田氏や赤羽氏のように、メモをとって「書く力」を高めれば、「考える力」も向上できますよ。

「考える力」をつけるには1:目標を設定する
「考える力」をつけるために、まず「目標を定める」ことから始めてみてはいかかでしょう。目標がわかれば、目標というゴールから逆算してやるべきことや足りないことが見えてきます。また、意見や判断を求められたとき、目標がはっきりとしていれば、現状ややるべきことについて相手に説明しやすいでしょう。
東京大学に合格するために編み出した独自の読書法を紹介する『「読む力」と「地頭力」がいっきに身につく 東大読書』の著者・西岡壱誠氏は、効率的に「考える力」を身につける方法として、目標を設定することが有効であると指摘しています。
勉強が得意な人や東大生の例を挙げてみましょう。面白いことに、彼らは単位取得に必要なギリギリの点数を取るのがすごく得意。(中略)なぜそういうことができるのかというと、いまの自分の力を把握し、目標の点数までに何点必要で、どんな勉強をすればいいかということがすべて見えているからです。最小限の努力で最大の結果を出す、それこそ超効率的ということですよね。
(引用元:Study Hacker|「自分で考えられない人」に足りない2つのこと。超効率的に『考える力』を身につける習慣とは?)
「考える力」を鍛えるトレーニングとして、自分なりの目標を決めるところから、始めてみませんか?

「考える力」をつけるには2:ニュースを利用する
「考える力」のある人は、ニュースから得た知識をうのみにして「わかったつもり」になることはありません。「考える力」を養うには、テレビやインターネットでニュースを見るだけでなく、知らない単語や背景知識を調べたり、「どうしてこうなったんだろう?」などと考えたりしてみてください。そして、ニュースに関して考え出した自分独自の「仮説」をノートやSNSに書き出してみましょう。
思考のアウトプットを繰り返せば、あなたの「考える力」はぐんぐん育っていきます。ジャーナリストの池上彰氏もニュースを見るとき、取り上げられた出来事の原因・利害関係・情報源に着目して、疑問点を洗い出し、知らないことを調べることにより、「考える力」を深めているそうです。皆さんも、「考える力」をつける方法として、ニュースを利用してはいかがでしょう?

「考える力」をつけるには3:能動的に読書する
「考える力」をつけるには、読書も有効です。けれども、文字面を目で追っているだけの「受け身の読書」では、「考える力」を深めることにはつながりません。
では、どのように読めばよいのでしょう? 独自の読書法で偏差値35から東京大学合格を果たした西岡氏によると、「考える力」を鍛えるには「能動的な読書」が肝心なのだそうです。
そのためにやったのは、「本と徹底的に議論する」ということでした。受動的に本を読むのではなく、能動的に、自分の頭で考えながら、「どうしてこういう風になるのだろうか?」「これは本当にそうなんだろうか?」と、本と会話するつもりで読むようにしたのです。すると、どんどん「本を読みこむ」ということができるようになっていき、同時に得た知識を使う力、(中略)「その知識を運用する力」を得ることができるようになったのです。
(引用元:西岡壱誠(2018),『「読む力」と「地頭力」がいっきに身につく 東大読書』,東洋経済新報社.太字による強調は編集部が施した)
西岡氏も実践する「能動的な読書」のポイントをまとめると、次のとおり。
- 読み始める前に目標を設定する。
- 質問や疑問を持って読書する。
- 本の内容をシンプルな言葉でまとめ、人に説明してみる。
- 同時に複数の本を読む。
西岡氏が実践した「能動的な読書法」を参考に、「考える力」をぜひ鍛えてみてください。
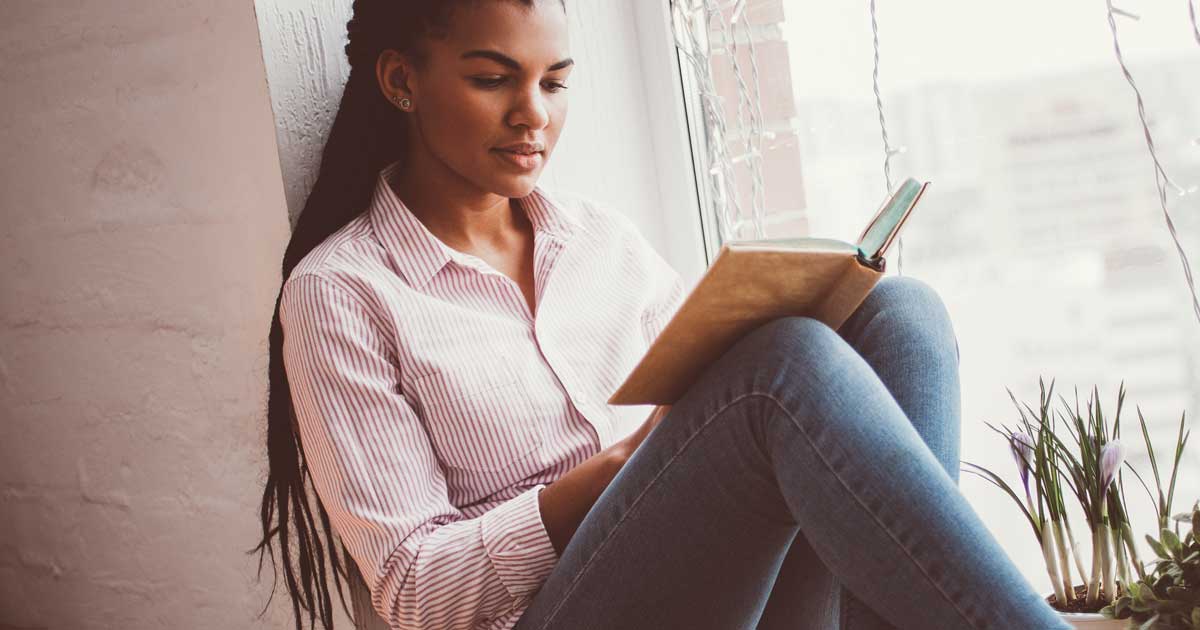
「考える力」をつけるには4:ディベート思考を身につける
「考える力」をつけるには、ディベート思考を身につけましょう。ディベート思考とは、ある課題に対して肯定・否定の両面から分析して問題解決しようとする思考法です。精神科医・樺沢紫苑氏の提唱する、ディベート思考のトレーニング方法をまとめると以下のとおり。
- 会議に備え、自分の賛成意見と反対意見を紙に書いておく。
→ 考えが明確になり、周囲に流されずに意思決定ができるようになる。 - 良かった点・疑問に感じた点を合わせて書評や映画レビューを書いてみる。
→ 多角的な視点から物事を考察する力がつく。 - 意見の異なる本や新聞を読み比べる。
→ 異なる価値観を知り、自分の考えを客観視できる。 - 世間話ができる知人を増やす。
→ 自分とは異なる考えを聞く力、自分の考えを伝える力が身につく。
「考える力」に自信がないのなら、ディベート思考を意識してみませんか。

「考える力」をつけるには5:数字や地図を使って考える
数字を使って考える
「考える力」をつけるには、物事を数字で表すことも有効です。例えば「担当している仕事を2日間で仕上げる」「1週間に3冊、本を読破しよう」など目標を具体的な数字で設定すると、ゴールから逆算して目標達成の道筋を考えることができます。
例えば「3週間で資格試験の過去問を終わらせる」ことを目標に掲げるとします。過去問が110ページあるとすれば、110÷21=5.2380952381。数字で考えたことにより、「1日に6ページやる」という目標達成までのペースが明らかになりましたね。
ビジネス数学の専門家である深沢真太郎氏は、数値化したいテーマを「ヒト」「ジカン」「カネ」に置き換えてみることが大事であるとして、具体的な方法を紹介しています。
たとえば、「うちの会社はホスピタリティ精神がすばらしい」ということを誰かに主張したいとします。(中略)「ホスピタリティ精神がない組織と比べて、人の数はどうなっているのか?」「ホスピタリティ精神向上のためにかけている時間はどれくらいか?」「そこにお金はどれくらいかけているのか?」などですね。すると、自然と数字の情報になっていくはずです。
(引用元:Study Hacker||デキる人は数字を使う! 「数字力」を磨く大切な習慣——“ビジネス数学の専門家” 深沢真太郎さんインタビュー【第2回】)
「ホスピタリティ」のようにあいまいなイメージを数字で表現すれば自分でも「ホスピタリティ」に対する理解が深まりますし、ほかの人への説得力が高まりますよね。「ホスピタリティが高い、とは具体的にどのような状態なのだろう?」と疑問を持ち、数字で表すという工夫をしたことで、「考える力」が強まったのです。
地図を使って考える
「考える力」をつけるには、地図を使ってみるのも一興。地図といっても、町などの様子を図面化したものではありません。東京大学物理学専攻教授の上田正仁氏による「地図メソッド」をご紹介します。
地図メソッドとは、1枚の紙に、「分かっていること」「分かっていないこと」を書き出し目に見える形にすることで、問題の本質をとらえ、問題を解く道筋を見出す方法です。上田氏の著書『東大物理学者が教える「考える力」の鍛え方』を参考に、地図メソッドの手順をまとめると以下の通りです。
- テーマに関連した情報を徹底的に収集する。
- 問題の核心につながるキーワードや周辺知識を、自分の言葉でメモする。1と2の作業を習慣化する。
- メモした情報をもとに「情報地図」を作成する。1枚の大きな紙に、「分かっていること」「分かっていないこと」をリストアップする。
- 情報地図を見ながら、その問題において何が重要なのかを検討する。
- 「分かっていないこと」のなかから、「分かりたいこと」を選び出す。
- 「分かりたいこと」の解決に全力を傾ける。
例えば、「ある企業主催のイベントに1,000人集客する方法」をテーマに地図メソッドを実践してみると、次のような情報地図ができあがります。

(画像引用元:Study Hacker|東大の物理学者が教える! 問題の本質を浮かび上がらせる「地図メソッド」がすごい)
地図メソッドを実践するにあたっては、「自分の力を最大限発揮すれば解決できるオリジナルな問題」を選ぶのが重要なのだそう。簡単すぎず難しすぎず、しかもありきたりでないテーマを選ぶことが大事なのですね。
地図メソッドを用いて「分かっていること」「分かっていないこと」を整理し可視化することで、解決するべき課題が見えてきます。「深く考える」ことにある程度慣れた人向けの方法ではありますが、地図メソッドに挑戦することで、あなたの「考える力」は飛躍的な向上を遂げることでしょう。

「考える力」をつけるには6:ボキャブラリーを増やす
「考える力」を高めるには、ボキャブラリーを増やすことが欠かせません。自分の気持ちや考えを表現するには、それぞれの感情・思考に対応する最も適切な言葉を知っている必要があるからです。
ボキャブラリーを増やすには、以下の方法をおすすめします。
- 書店へ行き、自分の業界や興味のある分野で参考になりそうな本を5、6冊買う。
- 買った本のうち、基礎的な内容の2、3冊を読み込む。
- 知らない単語や意味のわからない言葉を見つけたらすぐに調べ、メモする。
ひと通り基本を押さえたら、自分の業界や普段の興味とは異なる本にも手を伸ばし、上記の方法を繰り返してみてください。自分の業界関連の本から始めて、普段は見ない棚に置かれている興味のない分野の本にもチャレンジしていくことで、語彙の幅を広めることができると、伝える力【話す・書く】研究所所長の山口拓朗氏は推奨しています。
上記の方法をとらなくても、ボキャブラリーを増やす方法として読書が最適なのは言うまでもありません。新聞と異なり、本には「常用漢字しか使わない」「難解な表現は避ける」という制限がないため、読書は表現の幅を広げることができると池上氏は述べています。
池上氏は、A4サイズの「裏紙」を四つ折りにしたものを本に挟んでメモ用紙にしており、気になった部分や思いついたアイディアを書いておくのだとか。また、分からない言葉に出会ったときは、5歳ほどの子どもに対して説明できるくらいに詳しく意味を調べ、理解を深めるのだそうです。
就学前の子どもは、大人が「そういうものだ」となんとなく受け入れている常識も、抽象的な概念を表す言葉も知りません。大人ですら知らなかった言葉を子どもに説明するには、複雑な物事をシンプルに言い換えたり、例え話を考えたりする必要があります。「どうしたら5歳の子どもでも分かってくれるだろうか」と試行錯誤することで「考える力」が大幅に向上するのは間違いありません。
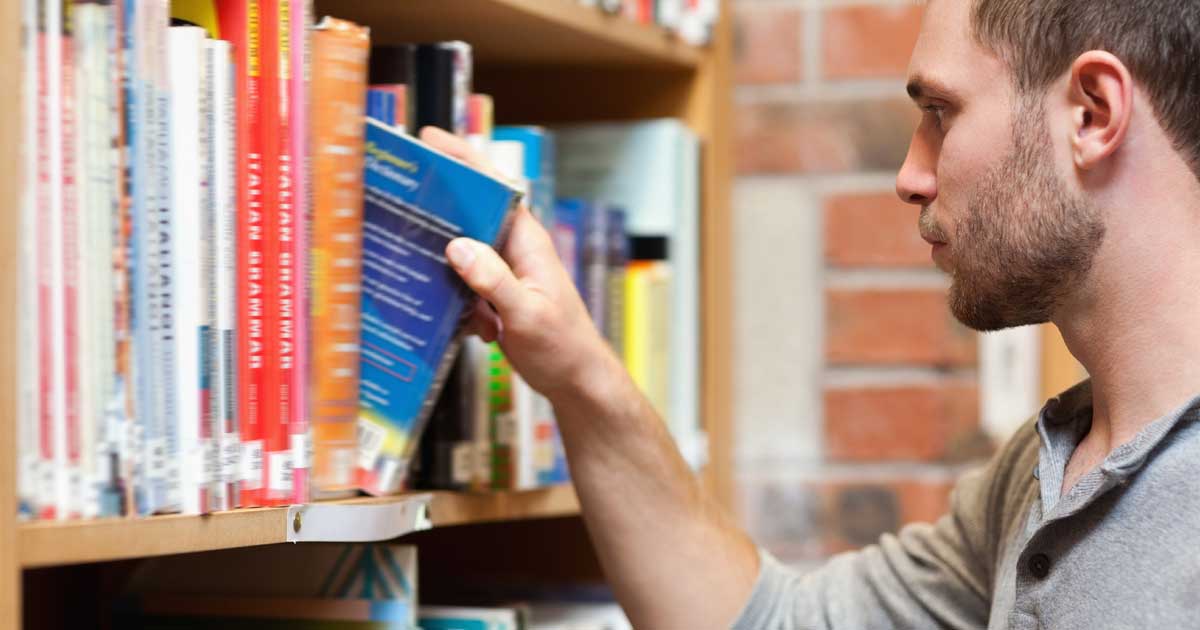
「考える力」をつけるには7:「フェルミ推定」に挑戦する
「考える力」をつけるには、「フェルミ推定」にチャレンジするのもよいですね。フェルミ推定とは、正確な答えを出しにくい問題に対して、今持っている情報から仮説を構築し、前提条件を設定して、短時間で結論を出す手法です。論理的な思考力を測る問題として、外資系のコンサルタント会社やIT企業の採用面接などで使われてきたことでも知られています。
ビジネスコンサルタントの細谷功氏は、フェルミ推定の特徴を次のようにまとめています。
フェルミ推定の最大の特徴は、問題を解くことで、「結論から」「全体から」「単純に」考えるプロセスを訓練できることにあります。いわば「問題解決の縮図」でもあるわけです。
(引用元:茂木健一郎他(2010),『考える力をつくるノート―強く生きるヒント9 すぐに実行できるのに誰も教えてくれなかった』,講談社.)
フェルミ推定という名前は、「原子力の父」と呼ばれるノーベル賞物理学者、エンリコ・フェルミ(1901~1954)が、シカゴ大学の講義で学生に対し「シカゴにピアノの調律師は何人いるか?」と問いかけたことに由来しています。東京大学大学院の鳥井寿夫・准教授によると、「未知の問題に出会ったら、仮説を立てて見当をつけ、物事を数量化して考える」ことの必要性を伝える意図がフェルミにはあったそう。
フェルミ推定は、以下のような場合に使われます。ハーバード大学の物理学者、エリック・マズール氏の実体験です。
土曜日の午後、商店街近くの駐車場に車を止めようとしたが、あいにく満車だった。そこで駐車場の入り口近くで駐車場が空くのを待つことにした。駐車場には20台の車が止まっている。駐車場が空くまでに、どのくらいの時間待たねばならないか。
(引用元:鳥井寿夫|フェルミ問題のすすめ)
マズール氏は、駐車場に着いた時刻・駐車場に止められる台数・車が出入りする時間の平均・自らの経験から、買い物の平均時間を2時間と仮定したそう。そして待ち時間を3分と見積もり、実際に駐車場は3分ほどで空いたとのことです。
皆さんも、「日本全国に電柱は何本あるか?」など、身近なものでフェルミ推定にチャレンジし、「考える力」を養ってみてはいかがでしょう。

「考える力」をつけるには8:手帳を活用する
「考える力」をつけるには、頭の中に浮かんだことを紙に書くことが有効です。考えを書き出すツールとして手帳を利用してみてはいかがでしょう? 手帳をうまく使うコツを2つご紹介します。
予習に利用する
手帳を用意し、3週間~ひと月先までの予定を書き込んでおきます。もし会議があるなら、取り上げられるであろう問題や、自分が提案したいことなどを手帳にメモしておきましょう。事前に考えをまとめておけば、本番で落ち着いて自分の意見を伝えることができます。
上記のように、手帳を「予習」のためのツールとして利用することで、せっかく会議に集まったのに意見が出ず、何も解決しない……という惨事が避けられます。時間が無駄にならず、生産性が上がるというわけです。
ToDoリストに利用する
手帳には、月ごと・日ごとのスケジュールを書くカレンダー式のページだけでなく、自由に使える白紙のページもありますよね。白紙の使い方は人それぞれですが、タスクを書き出してToDoリストにするのはいかがでしょう。
解決できたタスクには線を引いて消しましょう。線を引くごとに達成感が味わえますし、何が未達成なのか一目瞭然です。もし、ToDoリストからずっと消えないタスクがあるなら、それは解決が困難で後回しにしがちなタスクなのでしょう。なかなか消せない困難なタスクこそ、本当に重大な問題なのではないでしょうか。本腰を入れ、解決策を練りましょう。
以上、手帳をうまく使うコツを2つ紹介しました。ツールを使いこなし、あなたの「考える力」を成長させましょう。

「考える力」を育てるアプリ
「考える力」の育成につながるアプリをご紹介します。株式会社花まるラボの制作した「Think!Think!(シンクシンク)」(iOS/Android)です。
「Think!Think!」は、空間認識・平面図形などの問題を通し思考センスを育む教材アプリケーションとして、2016年にリリースされました。「Google Play」で最も権威ある賞「Google Play Awards」のファイナリストに日本の教育アプリとして初めて選出されたほか、世界最大のEdTech(教育×テクノロジー)スタートアップコンペ「Global EdTech Startup Awards」で日本予選の最優秀賞を受賞するという、高い評価を受けています。
「Think!Think!」の開発者は、算数オリンピック・世界最大のオンライン算数大会「世界算数」の問題作成を担当した、株式会社花まるラボ代表の川島慶氏。川島氏を中心とする東京大学出身の精鋭チームが作成した10,000題以上の問題が収録されています。
「Think!Think!」の画面は見やすくカラフル。答え合わせは自動で行われ、結果がすぐにわかるため、成功体験を楽しく積み重ねることができます。また、プレイは1日10分までという制限時間がついているので、スキマ時間を利用して遊ぶにはピッタリ。熱中し過ぎを防ぎ、毎日少しずつ継続しやすい仕組みなので、「Think!Think!」は忙しいビジネスパーソン・学生にぜひおすすめしたいアプリです。
筆者も思考力のトレーニングとして実際に「Think!Think!」を利用しています。対象年齢が5~10歳とはいえ、難易度が上がると油断はできません。1日10分という限られた時間のなかで、ミスをせずにどこまでレベルアップできるかという「自分との競争」に集中していると、確かに「考えている」という実感がわくほど脳が働いているのがわかります。
「Think!Think!」をプレイして楽しくなってきたら、定期的に開催されている「シンクシンクWorldCup」に挑戦してみては? 空間認識・平面図形・試行錯誤・論理・数的処理という「思考の5分野」を包括的に測定する検定です。あなたの思考能力を測ってみませんか?
「Think!Think!」は無料でも利用できますが、「スタンダードコース」(月額300円)や「プレミアムコース」(月額980円)に登録すれば、アプリケーションを使えるユーザーの数や挑戦できる問題を増やせます。毎日10分間、思考力の限界にチャレンジして、「考える力」を楽しく育ててみませんか?

「考える力」が低下してしまう悪習慣
「考える力」を鍛えるのと平行して、「考える力」を低下させてしまう悪い習慣を遠ざけましょう。「気分が落ち着かない」「集中して考えられない」と悩むことがある人は、今から紹介する悪習慣が身についてしまっているのかもしれません。
睡眠不足である
睡眠不足は「考える力」にとって大敵です。脳と脊髄を循環している「脳脊髄液」というものがあるのですが、脳脊髄液は「脳のゴミ」と呼ばれる認知症の原因物質「βアミロイド」などの老廃物を回収し、脳外へと排出する役割を持っています。特に睡眠中は、脳内の「グリア細胞」が縮んで大きな隙間が生じるため、脳脊髄液が効率よく老廃物を脳外へ運び出せるのだそうです。
つまり、睡眠時間が短いと、老廃物が脳から排出されず、記憶力の低下をはじめとした悪影響を引き起こしてしまいます。「考える力」を保つには、充分な睡眠をとる必要があるのです。 快眠セラピストで快眠環境プランナーの三橋美穂氏によると、睡眠時間には年齢別の目安があります。理想的な睡眠時間に、入眠直前~目覚め直後の時間として30分ほど加えた時間は、以下のとおり。
- 25歳:7時間(+30分)
- 45歳:6時間30分(+30分)
- 65歳:6時間(+30分)
(引用元:Study Hacker|脳に「ゴミ」が溜まる3つの最悪習慣。今すぐ改善すべきは就寝前の “あの行動” だった。)
上記の時間を睡眠のために確保することは、「考える力」を保つのに必須だといえるでしょう。
朝食を食べない
脳が活動するためには、エネルギーと十分な酸素が必要です。もし朝食を食べなければ、脳の血流が悪くなり、頭がぼんやりとして仕事や学業に集中できません。農林水産省は、朝ごはんを食べないことが引き起こすデメリットについて、次のように警鐘を鳴らしています。
脳の活動エネルギーは主にブドウ糖の働きによるものですが、ブドウ糖は体内に大量に貯蔵しておくことができず、すぐに不足してしまいます。つまり、空腹な状態で起きた朝の脳は、エネルギー欠乏状態。朝にしっかりごはんを食べないと、脳のエネルギーが不足し、 集中力や記憶力も低下してしまいます。
(引用元:農林水産省|朝ごはんを食べないと?)
アデレード大学のプロジェクトリーダー、ロジャー・S・シーモア名誉教授は、「脳が非常に知的になるためには、血液から酸素と栄養素を絶えず摂取することが必要である」と指摘しています。また、アテネ大学の心臓病専門医であるソティリオス・ サラマンドリス博士は、動脈を健康的に保つために、1日の総カロリー摂取量の20%以上を占める「高エネルギーな食事」を朝食としてとることを勧めています。
動脈が健康になって脳の血流がよくなれば、脳が活性化して「考える力」が高まります。朝食には、鮭のおにぎり・バナナ・牛乳・ヨーグルト・ナッツ類などがおすすめですよ。
長時間座りっぱなし
オフィスワークがメインの人は、出勤してから退勤時間までほとんど座りっぱなしの状態になっていませんか? 長時間座りつづけることも、「考える力」が低下する原因。股関節が圧迫されることで血液やリンパ液の流れが滞り、疲労物質が脳や自律神経にたまるためです。
東京疲労・睡眠クリニック院長の梶本修身氏によると、デスクワークで感じる疲労感は、脳が疲れきっているサイン。そのまま無理を続けると、脳神経の働きが落ち、注意力が低下してしまうそう。
座り仕事や勉強をしていて、疲れた・だるいと感じたら、いったん「座りっぱなし」の状態をやめましょう。1時間ごとに休憩を入れ、少し歩いたりストレッチをしたりなど、血流を改善しまょう。「考える力」が戻ってきますよ。

これがおすすめ。「考える力」をつける本
「考える力」をつけるのにおすすめの本を2冊紹介します。
『東大物理学者が教える「考える力」の鍛え方』
東京大学物理学専攻教授の上田正仁氏による、「思考のトレーニング方法」をまとめた1冊です。「考える」とはどういうことなのか思索を重ね、上田氏が大学の講義で実践し試行錯誤の末編みだした「考える力」を鍛える方法が、誰でもできるよう分かりやすく解説されています。
- 不要になった情報を捨てるテクニック
- 地図メソッド
- キュリオシティ・ドリヴン:回り道をすることで、当初の目的に縛られず自由な発想を得られる方法
上田氏が「自ら考え創造する力」の要素として挙げているのは以下の3つです。本記事の冒頭で挙げた「社会人基礎力」のひとつ「考え抜く力」と共通する点がありますね。
- 問題を見つける力:常識だと考えられているところに課題を見い出す
- 解く力:自分で見つけた課題に取り組み、問題点を整理・分析することで答えを出す
- 諦めない人間力:成果の出にくい問題を粘り強く考えつづける
『東大物理学者が教える「考える力」の鍛え方』では、アインシュタインや益川敏英氏といったノーベル物理学賞受賞者から、ピカソ、グレン・グールドなどの芸術家まで、各界で偉業を成し遂げた人々の「思考」にまつわるエピソードが多数語られます。「考える力」を高めようという目的がなくとも、読み物として非常に面白いですよ。人類の思索の歴史に思いをはせつつ、『東大物理学者が教える「考える力」の鍛え方』を読んでみませんか?
『考える力がつく本』
池上氏が自らの経験をもとに、「考える力」をつける実践的な方法をまとめた1冊です。本・新聞・インターネットといったメディアのうち、情報収集に最も役立つのは本だとして、特に本の選び方・読み方・使い方が詳しく解説されています。
例えば、小説は「楽しんで読んでいるうちにいつの間にか業界の知識が得られるツール」なのだそう。真山仁『ハゲタカ』、幸田真音『日本国債』など、ビジネスパーソン向けの具体的な「おすすめ本」が挙げられています。池上氏も、NHKの記者時代に警察回りを始めたとき、先輩記者からの勧めで松本清張の小説を読んでいたそうです。
また、海外のビジネスパーソンの多くは「リベラルアーツ」を身につけています。リベラルアーツとは「人を自由にする学問」という意味ですが、「教養」と言い換えてもよいでしょう。
池上氏によると、海外のビジネスパーソンたちと円滑にビジネスを進めるには、世界のニュースを把握したり教養を身につけておいたりする必要があるのだそう。経済の原則を知るにはアダム・スミスの『富国論』、近現代史を学ぶには教科書でおなじみの『世界史A』など、現代人に必要な教養を学べる本が紹介されています。
「リーダーたちは何を読んできたか」という最終章では、株式会社ユニクロ代表取締役会長兼社長の柳井正氏など、8人の「リーダー」たちが愛読している本が3冊ずつ紹介されています。また、池上氏と「リーダー」たちとの対談が掲載されており、企業のトップに上り詰めた人々の思索の軌跡がうかがい知れます。
『考える力がつく本』は、「考える力」をつけるのに有効なメディアの使い方や、「考える力」を鍛える本の選び方をすぐ知りたい人におすすめの1冊です。
***
「考える力」を深めるには、ふと頭に浮かんだことをそのままにせず、書き留めて整理・分析し、知識を関連づけて本質を抽出、自分なりのアイディアを生み出していく、という過程が必要です。AIをツールとして使いこなし、想定外の問題を柔軟な思考で乗り越え、未来を軽やかに生きるため、今から人間独自の能力である「考える力」を磨いてみませんか?
川上浩司(2017),『京大式DEEP THINKINGー最高の思考力』,サンマーク出版.
池上彰(2016),『考える力がつく本』,プレジデント社.
前田裕二(2018),『メモの魔力』,幻冬舎.
茂木健一郎他(2010),『考える力をつくるノート―強く生きるヒント9 すぐに実行できるのに誰も教えてくれなかった』,講談社.
西岡壱誠(2018),『「読む力」と「地頭力」がいっきに身につく 東大読書』,東洋経済新報社.
上田正仁(2013),『東大物理学者が教える「考える力」の鍛え方』,ブックマン社.
赤羽雄二(2013),『ゼロ秒思考―頭がよくなる世界一シンプルなトレーニング』,ダイヤモンド社.
Study Hacker|“紙1枚” から始められる言語化トレーニング。「言葉にできない」解消のための4ステップ。
Study Hacker|言えないのは、考えていないから。「言葉にできない」に逃げない、言語化トレーニング
東洋経済オンライン|忙しすぎる日本人が知らない深く考え抜く力ーたくさんの解き方を意識して重ねよう
Study Hacker|「自分で考えられない人」に足りない2つのこと。超効率的に『考える力』を身につける習慣とは?
Study Hacker|考える力は鍛えられる! 一目おかれる "賢い人" になるための、3つの『思考力トレーニング』
Study Hacker|「東大読書」と「京大読書」を比べてみたら、本の “読み方” と “選び方” が真逆だった。
Study Hacker|「人の意見に流されやすい人」がするべき4つの簡単トレーニング。“本の選び方” で意思決定力が高まる!
プレジデントオンライン|だまされない人間になるための6つのコツ
Study Hacker|仕事がデキる人の3つの特徴。仕事がデキる人は「○○○○」と言わない
Study Hacker|デキる人は数字を使う! 「数字力」を磨く大切な習慣——“ビジネス数学の専門家” 深沢真太郎さんインタビュー【第2回】
Study Hacker|東大の物理学者が教える! 問題の本質を浮かび上がらせる「地図メソッド」がすごい
Study Hacker|「言葉を知らない」では深い思考ができぬ。語彙力を伸ばす大切な習慣――“文章術のプロ” 山口拓朗さんインタビュー【第4回】
Study Hacker|地頭力が鍛えられる『フェルミ推定』。日本の電柱の数、あなたは推定できますか?
鳥井寿夫|フェルミ問題のすすめ
Study Hacker|一冊の手帳で身につける「考えるクセ」
Study Hacker|知らず知らずのうちに脳を疲れさせている3つの最悪行動。“効率を重視しすぎ” はかえってキケン。
Study Hacker|脳をダメにする最悪習慣、賢い脳をつくる最高習慣。
Study Hacker|脳に「ゴミ」が溜まる3つの最悪習慣。今すぐ改善すべきは就寝前の “あの行動” だった。
東洋経済オンライン|グーグルが認めた「花まる学習会」アプリの力ー子ども向け教育アプリで世界トップ5に選出
エドテックジン|子どもの学習意欲を引き出す思考センス育成教材「Think!Think!」~開発者・川島慶さんが語る「意欲格差と教材の可能性」
Think!Think!
農林水産省|朝ごはんを食べないと?
上川万葉
法学部を卒業後、大学院でヨーロッパ近現代史を研究。ドイツ語・チェコ語の学習経験がある。司書と学芸員の資格をもち、大学図書館で10年以上勤務した。特にリサーチや書籍紹介を得意としており、勉強法や働き方にまつわる記事を多く執筆している。



