
仕事で売り上げ1位になろう、資格を取ろう、読書の習慣をつけよう……とさまざまな目標を立てつつも、結局どれも中途半端になり達成することができない。努力を継続できない。そんな悩みを抱えている方は多いかと思います。
なぜいつも計画がグダグダに終わってしまうのか? 目標を達成するためには何に気をつけるべきなのか? 本稿で詳しく解説していきます。
- 目標達成できない理由
- 目標の達成方法
- 目標達成までのプロセス
- 便利ツール「目標達成シート」
- 目標達成を支援するアプリ
- 目標達成のための手帳術
- 目標達成率の出し方
- 目標達成に効く名言・四字熟語
- 目標達成に役立つ本
- 目標を達成した後は……
目標達成できない理由
なぜ、いつも目標を達成できずに終わってしまうのでしょうか? 目標を達成できない理由としては、以下の9つが考えられます。
工程を細分化していない
まず1つ目の理由は、目標を達成するために何をやるべきか細かく決めていないことです。心理学者の岩井俊憲氏によれば、目標が曖昧だったり高すぎたりすると、私たちのやる気は損なわれてしまうのだそうです。
たとえば「今年中に10キロダイエットする」を目標とするなら、「毎朝5分だけ走る」「朝ごはんはサラダだけにする」というように細かな工程に分けることで、何をすべきか明確になりますよね。しかも、各工程はやり遂げられそうだと思える程度の、能力に見合った難易度でなければいけません。いきなり朝1時間走る、ご飯をまったく食べない、というような無茶な計画を立ててしまうのは、努力が続かない典型例です。
戦略を考えていない
目標達成までのステップを明確にしたとしても、そのステップをどう攻略するか考えていないのであれば、目標を達成するのは難しいでしょう。
たとえば英単語を1日30語覚えるという目標を立てたとしたら、「通勤時間は往復2時間もあるので、電車の中では必ず英単語を覚えるルールにしよう」というような戦略を考えることで、勉強時間を確保しやすくなります。
どうすれば自分が抵抗を感じずに努力を続けることができるか、どうすれば時間を取りやすいか、といったことを事前に想像しておかないと、目標達成は困難です。
「やらないこと」を決めていない
目標を達成するには、一定の時間を努力に割く必要があります。ただし、「やるべきこと」だけではなく「やらないこと」も決めておかないと、「やるべきこと」に使える時間が足りなくなってしまいますよ。
たとえば、グロービス経営大学院学長の堀義人氏の場合、ノンフィクション以外の本を読まず、会食や接待、ゴルフなどもやらないことに決めているそうです。やるべきことを “断捨離” することで、本当に成すべきことに注力することができるのです。
家に帰ったらついダラダラとテレビを見てしまう、通勤電車の中でもスマートフォンをいじってしまう、自分のキャパシティではこなせないほど多くのノルマをこなそうとしている、という方は、ぜひ一度自分の時間の使い方を見直し「本当にやるべきことはどれか?」と問い直してみてください。
計画の進行状況を把握していない
目標に向かって努力を継続するためには、進捗状況をしっかり把握しておくことも大切です。
いくら良い計画を立てても、予定通りに進んでいないのでは意味がありません。また、計画どおりのノルマはこなせているけれど、思ったよりも成果が現れなかった、というパターンもありますよね。
週に一度など、定期的に自分の成果を振り返り、「予定が遅れていないか?」「今のままの計画で大丈夫か?」と確認するようにしましょう。
失敗の理由を真剣に考察しない
目標を達成できなかったとき、「できなかった、残念」で終わっていては、次回も目標達成は厳しそうです。なぜ失敗したのか真剣に考え、次に活かせる教訓を学び取れていないからです。
たとえば、失敗の理由を考察し、「時間が思うように取れなかったこと」が原因だと判明したとします。ではどうすれば時間を捻出できたのか、無駄な時間の使い方をしていなかったか、とさらに問いを進めれば、次こそは同じ失敗をしないように対策を練ることができますね。
目標を達成するには、達成できなかったときの対応が大事なのです。
できない理由ばかり探す
目標の達成が難しそうなとき、「どうすれば達成できるか」ではなく「達成を困難にしている理由」ばかりに目が向いている場合、要注意です。
「忙しい」というのを、目標を達成できない理由として使っていませんか? たしかに時間は有限ですが、少ない時間をうまくやりくりしている人も存在するのもまた事実。「忙しいから、できない」と諦めるか、「忙しいなら、どうすればよいか」と対策を考えるかが、目標を達成できる人とできない人の違いなのです。
目標を達成できない理由を思いついたとしても、達成できない理由を言い訳にして目標を諦めるのではなく、「きっと乗り越える方法があるはず」と、次に成すべきことを考えるようにしましょう。
自分ひとりでやろうとしている
なにもかも自力でやり遂げようとするのも、ときには失敗の原因になります。
たしかに、自分ひとりの力だけで目標を成し遂げられたら、達成感はひとしおかもしれません。しかし、他人の力を頼るのも、決して逃げではないはず。ぜひ上司や同僚に力を借りてください。家族や友だちを巻き込むことも、努力へのモチベーションが高まったり、張り合いが出ることでより速く成長できたりといったメリットを生みます。
心理学の研究でも、単独で何かを行なうより、複数人のグループで行なうほうが能率が上がったり、意欲や満足感を得られやすかったりするということがわかっています。自分と同じように目標を持っている仲間と達成具合を報告し合ったり、集まって一緒に勉強する時間を設けたりなど、適度に他者からの刺激も受けるようにしてみましょう。
楽観視しすぎている
計画の設計がそもそも甘い、というパターンもありがちです。手元にある限られた情報だけを見ていると、私たちはつい楽観的すぎる計画を立ててしまうことがあるのです。
たとえば「自分は1日30個英単語を覚えられる。だから、100日後までに3,000単語覚えよう」という計画を立てたとします。しかし、実際には覚えた30単語は時間とともに忘れていきますし、ほかの用事が入って勉強できない日もあるでしょう。
したがって「3,000単語暗記したことがあるほかの人は、いったいどれくらいの時間がかかったのか」「自分は1か月あたり何日、英単語の暗記に充てることができるのか」など、まずは情報を集め、なるべく客観的な視点で計画を立てることが大切です。
必要なリソースをそろえていない
目標を達成するには、時間・人手・予算・機材などのリソースが必要です。リソースがないのに目標を達成することはできません。目標を達成するために必要なものがきちんとそろっているか、今一度確認してみましょう。
資格試験の勉強を始めるのなら、まずは自分に合った参考書を買い、自宅の中の学習環境も整えなければなりません。趣味のフットサルに時間を割いているなら、やめるか、頻度を減らす必要があります。気合を入れるため、新しい文房具を買いそろえてもいいでしょう。
どうしてもリソースが用意できないというのであれば、目標そのものを見直す必要があります。たとえば「起業したいけれど資金が用意できない」というのであれば、起業の計画を立てる前にまずはお金を工面する方法を考える必要があります。
以上、目標を達成できない原因のパターンを9つご紹介しました。

目標の達成方法
では、目標を達成するための方法にはどのようなものがあるのでしょうか? この章では、目標の種類や場面に応じて使える7個の方法をご紹介します。
SMARTの法則
まず紹介するのは「SMARTの法則」。SMARTとは、以下の5つの英単語の頭文字を取ったもので、正しい計画を立てるために必要な5要件を表しています。
- Specific(具体的な):具体的かつ明確な言葉で表現されている。
- Measurable(測定可能な):目標の達成度合いが数値的に評価できる。
- Achievable(達成可能な) :現実的に達成可能である。
- Related(目標に関連している):達成したい目標や成果に沿っている。
- Time-bound(時間制約がある) :達成するべき期限が設定されている。
このSMART理論を用いることで、計画を現実的かつ合理的なものにブラッシュアップできるのです。たとえば「運動習慣を身につける」という目標を立てるとしたら、以下のような具合になります。
- Specific(具体的な):毎朝、腕立て伏せ、腹筋、スクワットを行なう。
- Measurable(測定可能な):回数はそれぞれ50回とする。
- Achievable(達成可能な):すべてのメニューをこなしても10分とかからないため、十分達成できる。
- Related(目標に関連している):「運動習慣を身につける」という目標に合っている。
- Time-bound(時間制約がある):まずは1か月間、継続する。
できれば「1週間続けられたら焼肉を食べる」などのご褒美も、計画の中にルールとして取り入れておきましょう。ご褒美があることで、なんだかやる気が出ない日などにもモチベーションを確保することができます。
こうした自分の外部の要因によるモチベーション(いわば不純な動機)を、心理学では「外発的動機づけ」と言います。意欲や自信をつけるためのキッカケとして有効です。
仮説思考
仮説思考は、どうやったらうまく目標を達成できるかを考えるときに役立つ思考法です。モデルとなる前例がないことに取り組むときや、参考にできる情報が少ないとき、目標の達成方法がわからないときなどに使えます。
仮説思考の基本的な考え方は「ザックリと当たりをつけて、とにかく手を動かしてみる。そして失敗しながら修正し、答えに近づいていく」というものです。仮説思考は以下の4ステップからなります。
- 事実を集める・整理する
- 仮説を立てる
- 仮説を実行・検証する
- 仮説を修正する
日常でも、私たちは自然にこの仮説思考を使っています。たとえば「なくした財布を探す」場合。まずは「さっきまで飲み屋にいた」「会社にいた時点ではまだ財布はあった」などの事実を集め(1)、「飲み屋に忘れたんだろう」という仮説を立て(2)、実際に飲み屋に足を運んで財布がないか訊き(3)、なければ「帰り道で落としたんだろう」という新たな仮説を立てる(4)というプロセスを繰り返すうち、財布の本当の在りかに近づくことができますよね。
同様に、仕事や勉強などの目標に取り組むときにも「こうすればうまくいくだろう→ダメだった→ならばこうしよう」というプロセスを繰り返していくことで、効率的な方法にたどり着くことができるのです。
では、英単語を覚えるという例で「どうすれば効果的に暗記できるか」という問題を考えてみましょう。
1. 事実を集める・整理する:立った姿勢で覚えると、記憶効率が上がるらしい。
2. 仮説を立てる:通勤電車の中で英単語を覚えると、効率的なのではないか。
3. 仮説を実行・検証する:満員で苦しく、全然集中できなかった。
4. 仮説を修正する:1本早い電車なら、少し空いているのではないか。
↓
3. 仮説を実行・検証する:空いていたが、やはり電車の中では集中できなかった。
4. 仮説を修正する:電車を待っている時間を暗記に充てよう。
↓
3. 仮説を実行・検証する:集中できたが、時間が短いのが難点だ。
4. 仮説を修正する:電車の待ち時間に加え、ランチを店で注文してから出てくるまでの時間も活用しよう。
このようにトライ&エラーを繰り返していくことで、最も自分にフィットするスタイルやコツをしだいに確立できるはずです。
A4用紙でタスクの洗い出し
3つめの方法は、ベストセラーとなった『ゼロ秒思考 頭がよくなる世界一シンプルなトレーニング』(ダイヤモンド社、2013年)の著者・赤羽雄二氏が紹介するメモ術です。
メモ術と言ってもやり方は簡単。考えていること、頭の中にあることをA4用紙にひたすら書きまくるだけです。目標を立てるなら、その目標を達成したい理由や、目標達成に必要なことなどを書き出すとよいでしょう。
赤羽氏流のメモ術には下記のルールがあります。
- A4用紙は横向きで使う。
- 1つのテーマにつき1枚を使う。
- 1つのテーマについて5、6項目に分け、全部で20字~30字程度にまとめる。
- 1枚につき1分以内で書く。
つまり、短い時間で直感的にバーッと書き出す、というイメージになります。赤羽氏によると、このメモ術を1日10枚のペースで続けると、思考が整理され頭の回転が劇的に速くなるのだそうです。
ちなみに、フィギュアスケート金メダリストの羽生結弦選手も、練習中にうまくできなかったことや気になること、疑問点、こうすればうまくいくのではないかという仮説などを、「発明ノート」と名づけたノートに記しているのだそうです。
発明ノートという名称は、日々の練習の中でひらめいたことや気づいたことを書くことにちなんでいます。大きな目標を達成するためには、思考を記録することで自分の現状を分析したり、トライ&エラーの過程を把握したりしながら今後に活かしていくことが不可欠のようです。
クエスチョン・マトリクス
4つめに紹介するのは、クエスチョン・マトリクスです。
クエスチョン・マトリクスとは、自分が今どんな問題を抱えているのか把握することができるフレームワーク。クエスチョン・マトリクスを行なうことによって、隠れた問題や疑問点に気づくことができ、思考をより深めていくことができます。
以下は、「どうすれば運動習慣をつけることができるか?」という問題を解決するために行なったクエスチョン・マトリクスの例です。
| 物 what | 環境 when/where | 選択 which | 人 who | 方法 how | |
|---|---|---|---|---|---|
| 現在 is/does | 今、どんな運動をしているか? | 今、どこで運動をしているか? | 有酸素運動と無酸素運動ならどちらがいいか? | 今、誰と運動しているか? | 今、どうやって運動しているか? |
| 過去 was/did | 過去にはどんな運動をしていたか? | 過去にはどこで運動をしていたか? | 有酸素運動と無酸素運動のどちらが好きだったか? | 過去には誰と運動していたか? | 過去にはどうやって運動していたか? |
| 可能 can | どんな運動が可能か? | 他にはどこで運動することが可能か? | 有酸素運動と無酸素運動、どちらが続けやすいだろうか? | 誰と運動することができるか? | どうやって運動することが可能か? |
| 推量 should/would | 健康のためにはどんな運動をすべきだろうか? | どこで運動すべきだろうか? | 有酸素運動と無酸素運動のどちらをやるべきだろうか? | 誰と運動すべきだろうか? | どうやって運動するべきだろうか? |
| 未来 will | どんな運動をしてみたいか? | どこで運動したいか? | 今後の健康のためには、有酸素運動と無酸素運動のどちらがいいか? | 誰と運動したいか? | どうやって運動したいか? |
| 想像 might | どんな運動が面白そうか? | どこで運動できそうか? | 有酸素運動と無酸素運動、どちらかがデメリットを及ぼすことはないか? | 一緒に運動してくれる人を探す方法はないか? | 良い運動のやり方を教わるにはどうしたらいいか? |
1つの問題から派生して、30個(5×6)のテーマが導かれました。「有酸素運動と無酸素運動ならどちらがいいか?」「誰と運動すべきだろうか?」など、クエスチョン・マトリクスを使わなかったら思いつかなかったであろうテーマを得られたことで、より多角的なアプローチから解決策を考えられるようになった、と言えるでしょう。
タスクをスモール・ステップに分解
タスクが大きすぎる場合、具体的に何をやるべきかわからず、モチベーションが下がってしまうことがあります。
たとえば「びっくりするほどおいしいカレーを作ってください」と言われたとしたら、誰でも途方に暮れてしまうでしょう。「びっくりするほどおいしいカレー」とはどんなものなのか想像もつかないし、そもそもプロの料理人ではないのだから作れるわけがない、と諦めてしまうかもしれません。
そこで、タスクを小さなステップに細分化してみましょう。「1. びっくりするほどおいしいカレー屋さんがないか調べる」「2. その店のレシピを教えてもらう」「3. 材料をそろえる」「4. レシピ通りに作る」という4段階にしてみれば、これならできそうな気がする、と思えるのではないでしょうか。
大きな目標を掲げるのは良いことですが、全体像が把握できないかぎり行動に移すことはできません。まずはタスクを手ごろな大きさにカットし、完成までの工程を具体的にイメージできるようにすることが大切なのです。
別の例として、「売上金額を300万円に増やす」という目標について考えてみましょう。
- 価格単価を3倍にする。
- アプローチする顧客数を3倍にする。
- SNSによる宣伝を強化する 。
という3つのタスクに分解すると、漠然としていた目標が明確になり、やるべきことが具体化されたことがわかるかと思います。
時間管理マトリクス
次に紹介するのは、ビジネス本の名著『7つの習慣』(原題:The 7 Habits of Highly Effective People、1996年)の著者として有名なスティーブン・コヴィー氏が提唱する「時間マトリクス」という方法です。
時間マトリクスでは、タスクを「緊急/非緊急」「重要/非重要」の観点から4つに分類します。表に示すと、以下のようになります。
| 緊急 | 非緊急 | |
| 重要 | 領域1:取引先とのアポなど | 領域2:仕事のための勉強など |
| 非重要 | 領域3:メールの返信など | 領域4:趣味など |
領域1、2、3、4の順番に優先順位が高くなっていることがわかるかと思います。 目標を達成するために行なう努力は、領域2にあたります。とても重要なものではありますが、1年後などへ向けて長期的に積み重ねていくタスクなので、緊急を要するわけではないからです。そしてこの領域2にあたるものこそ、将来大きな成果を出すためには最も重視すべき項目になります。
まずは時間管理マトリクスにしたがって、自分の日々の行動を全て分類してみてください(遊びなども含めて)。タスクが持つ意味や重要性を確認でき、どのタスクに時間を取られすぎているか、どのタスクにもっと時間をかけるべきか見えてくるはずです。目標を達成するには、領域1、3、4にかける時間を極力減らし、領域2に割く時間を増やせるよう、タスクの断捨離や効率化を図りましょう。
KPT法
KPT法は、振り返りや反省のときに役立つフレームワークです。KTPとは、以下3つの単語の頭文字から取られています。
- Keep:良かった点(続けるべき点)
- Problem:反省点や問題点
- Try:次からチャレンジすべきこと、改善策
KTPの3項目にしたがって振り返りを行なうことで、「何が良く、何がダメで、どう変えるべきなのか?」を漏れなく洗い出すことができます。たとえば、英単語の暗記というタスクに対してKTPを適用してみましょう。
- Keep:計画通り、1日30個覚えることができた。
- Problem:暗記の確認テストをしてみたら、半分以上忘れていた。
- Try:復習の時間を設けて何度も覚え直すことにする。
KTPを用いた振り返りによって復習の重要性を認識し、勉強の方法を改善することができましたね。仕事でも、うまくいかなかったことがあれば、ぜひKPT法を実践してみてください。
以上、目標を達成するための方法を7つご紹介しました。

目標達成までのプロセス
上で紹介した「目標の達成方法」を踏まえ、目標達成までのプロセスの一例をご紹介します。
1. 目標を設定する
まずは、これから達成したい目標を具体的に設定します。“どうなれば達成なのか” という基準は、必ず明確にしておきましょう。より詳細な目標設定をするには、前章の1で紹介した「SMARTの法則」が役立ちます。
(例)TOEICで800点以上とる。
2. 方法・戦略を考え出す
前章2の「仮説思考」に基づき、まずは思いつく限り達成の方法を挙げましょう。戦略を考えるには、前章3の「A4用紙メモ術」や、4の「クエスチョン・マトリクス」が助けになります。
(例)英単語を1日30個、半年で5,000個覚える。
3. 方法の詳細を考える
計画に着手しはじめてから悩まないよう、具体的な手順や想定される障害、障害への対処法などをイメージし、あらかじめ決めておきましょう。 前章5の「タスクをスモール・ステップに分解」にしたがい、各タスクはなるべく小さく切り分けます。タスクの優先順位を決めるには、前章6の「時間管理マトリクス」の表が便利です。
(例)行き帰りの通勤電車の中で覚えることにする。
4. スケジュールを実行しながら、振り返り・改善を重ねる
前章7の「KPT法」を使い、計画通り進んでいるか、思ったような成果が出ているか、想定外の問題はないか振り返り、改善していきましょう。
(例)いちど覚えた単語を、想定以上に多く忘れてしまうので、復習の時間をもっと長くとる。
以上のような4つのステップを踏むことにより、効率よく努力を重ねることができます。個人だけでなく、営業の売上など組織単位での目標達成にも役立つので、ぜひ活用してみてください。

便利ツール「目標達成シート」
続いて、目標達成に便利なツールをご紹介します。目標達成シート(マンダラート)は、目標を達成する方法を洗い出すためのフレームワークで、正方形が9×9マス集まった表です。ルールにしたがって書き込んでいくことで、自分に必要なものを把握し、目標達成の条件を明確化することができます。
まずは実物を見てみましょう。以下は、メジャーリーガーとして大活躍している大谷翔平選手が、高校1年生のときに書いたシートです。

(画像引用元:News Picks|大谷を怪物にした花巻東高校の「目標達成用紙」)
中央にある「ドラ1、8球団(ドラフト1位で8球団以上から指名される)」がメインとなる大目標で、その目標を実現するための具体的方法が「体づくり」「コントロール」「キレ」「スピード160km/h以上」「変化球」「運」「人間性」「メンタル」の8つ。それらの条件を達成するためのさらなる手段が、周りのマスに書かれています。
「ドラフト1位で8球団以上から指名される」という大きな目標から出発して、「スライダーのキレ」「礼儀」などの具体的な要素に落とし込まれているのがわかると思います。漠然とした目標はあるけれど達成するために何をしたらいいのかわからない、という方に目標達成シートはオススメです。
もう少し、私たちに身近な例を見てみましょう。以下は、同じ目標達成シートを「TOEICで800点以上とる」という目標に対して適用したものです。

(画像引用元:STUDY HACKER|勉強にも仕事にも! 大谷翔平も使う『目標達成マンダラート』がすごい)
TOEIC以外の資格試験の勉強を始めたい方にも、テンプレートとして役立つはずです。目標の達成を目指す際には、まず最初にこの目標達成シートを活用してみてください。

目標達成を支援するアプリ
目標の達成に役立つツールとして、「Lifebear」(iOS/Android)という手帳アプリをご紹介します。
「Lifebear」は、紙の手帳と同じような見た目の画面にスケジュールを入力することができ、しかも予定の種類ごとに色を分けることができます。「LifeBear」はiPhone、Android両方に対応しているのみならず、デスクトップで使うこともできます。
「Lifebear」には、予定管理を支援してくれる様々な機能がついています。
予定の詳細メモ機能
カレンダーに表示する短文だけでなく、詳細情報をワンタッチでメモすることができます。たとえば、カレンダーに「A商事との取引日」と短文で表示しておき、その予定と紐づけて、詳細欄に取引先の情報や戦略など長い文章を入力しておけるのです。
アカウント機能
「Lifebear」では自分のアカウントを複数のデバイスで使用できるため、スマートフォンで作成したスケジュールをタブレットやPCから確認できます。もしスマートフォンが壊れたりしても、作成した予定が失われることがないので安心です。
休日設定機能
デフォルトでは土日が休日となっていますが、仕事に合わせて、土日以外の曜日を休日として設定することができます。
ノート・日記機能
カレンダーとは別に、長文の文章を記録しておけるノート機能があるので、目標をメモしておいたり、気づいたことや改善点などを書き留めておいたりするのに使えます。
スタンプショップ
「Lifebear」独自のスタンプショップからスタンプを購入し、ワンタッチでカレンダーに張りつけることができます。特に目立たせたい予定などがあるときなどに便利です。
目標達成までのスケジュールを立てる際にはとても役立つので、ぜひ「Lifebear」を使ってみてください。

目標達成のための手帳術
目標を達成するために欠かせないのが「手帳」によるスケジュール管理。あなたは正しく使いこなせているでしょうか? この章では、意外と知られていない手帳の使い方の基礎をご紹介します。
終了予定時刻を書く
スケジュールには、タスクの終了予定日だけではなく、終了予定時刻も記しておきましょう。終了予定時刻まで書いておくことで効率への意識が高まりますし、どれくらいの時間かかったのか分単位で把握することで、次回以降、同様のタスクにかかる時間を予想できるようになります。
目標や振り返りを書く
手帳はスケジュール管理だけでなく、自分を見つめ直すためのメモ帳としても活用できます。今何を目標としているか、今日のノルマの達成度合はどうなのかなどを書き込み、日々振り返りを行ないましょう。振り返りの方法については、前述した「KTP法」を参考にしてください。
心に残った言葉や出来事など、何でも書いておく
自分の目標に関することだけでなく、本で読んで心に刺さった言葉や、仕事で起きた出来事、仕事の中での気づきなど、とにかく何でもメモしておくようにしましょう。
こうした日々の気付きをメモしておくことで、手帳は将来役立つ資産になります。過去と同じような問題に遭遇したときや部下の指導をする立場になったとき、社内で研修やスピーチを頼まれたとき、具体的なエピソードや言葉が残っていれば大いに役立つことになります。
以上、目標達成に使える手帳術をご紹介しました。

目標達成率の出し方
目標の達成具合は、なるべく数字を使って把握するようにしましょう。数字を使うことで、進捗具合はどれほどなのか、計画通り進んでいるのか遅れているのかを客観的に測ることができます。
たとえば、TOEICの過去問1冊を3週間で終わらせる、と決めたとします。参考書が150ページあるとすると、150÷30=5。1日に5ページ進めればいい、ということがわかります。「1日5ページ」というノルマを数値として把握できていると、「昨日は4ページしかできなかったから、今は1ページ遅れているんだな」というように、計画の進み具合を細かく評価することができるのです。
数値目標を定めたら、次は目標達成率を計算してみましょう。目標達成率とは「作業が90%完了した」「売上が前年比125%になった」というような、百分率(%)による書き方のことです。
進捗度合や仕事の成果などをよりわかりやすく表現できることが、目標達成率を用いるメリットです。 目標達成率の出し方は以下のとおり。
実績÷目標
たとえば150ページの参考書が95ページ終わったとしたら、目標達成率は、
95(実績)÷150(目標)=0.6333……
つまり、タスクが63%完了している、ということがわかります。「150ページのうち95ぺージが終わった」と聞くより「63%終わった」と聞くほうが、進捗度合のイメージをつかみやすいですよね。
複数のタスクを同時に進めている方は、達成度合をエクセルに入力し、グラフ化することによって、よりタスク管理がしやすくなります。目標達成度は、上司などに自分の成果をわかりやすく伝えるためにも使えるので、ぜひ覚えておきましょう。

目標達成に効く名言・四字熟語
目標達成のモチベーションが欲しいという方のために、意識を高めてくれる言葉を2つご紹介します。
人間の最大の悪は、 「鈍感」である
野球評論家・野村克也氏の格言です。野村氏は、ものを考えたり自分の欠点を改善するためには、まず前提として、自分で問題に気がつく必要があると言います。したがって、鈍感な人や自分勝手な人は自分に何が欠けているのか認識できず、成長が遅れてしまうのです。監督として最多勝を成し遂げた野村氏らしい、示唆に富んだ名言ですね。
鈍感にならないためには、前述したKTP法などを使って定期的に振り返りを行ない、何か問題点はないか、もっと良くする方法はないか、常に自分を客観視するように心がけましょう。
一陽来復
一陽来復とは、中国から伝わった占いである「易」の考え方が表れた四字熟語です。
易では、万物を陰と陽に分けて考えます。1年を陰と陽に分けたとき、冬至(夜の長さが1年で最も長い日)に陰が最も強くなり、夏至(昼の長さが1年で最も長い日)に向けてしだいに陽が増していくそう。つまり1年は、夏至を境に弱まっていった陽が、冬至を超えるとまた回復し始め、次の夏至にまた最大になる、という円環運動をしているのです。 一度弱まった陽が1年後にまた回復するという意味で、これを「一陽来復」と言います
転じて、一陽来復には「悪いことが続いても、必ずそのうち良いことがあるものだ」という意味もあります。もし思い通りに成果が出なくても「陰の後には必ず陽が来るんだ、一陽来復なんだ」と思えば、少し気が楽になるのではないでしょうか。
気持ちが折れそうなときは、先人たちが残した言葉に刺激を受けることで目標達成の糧にしましょう。
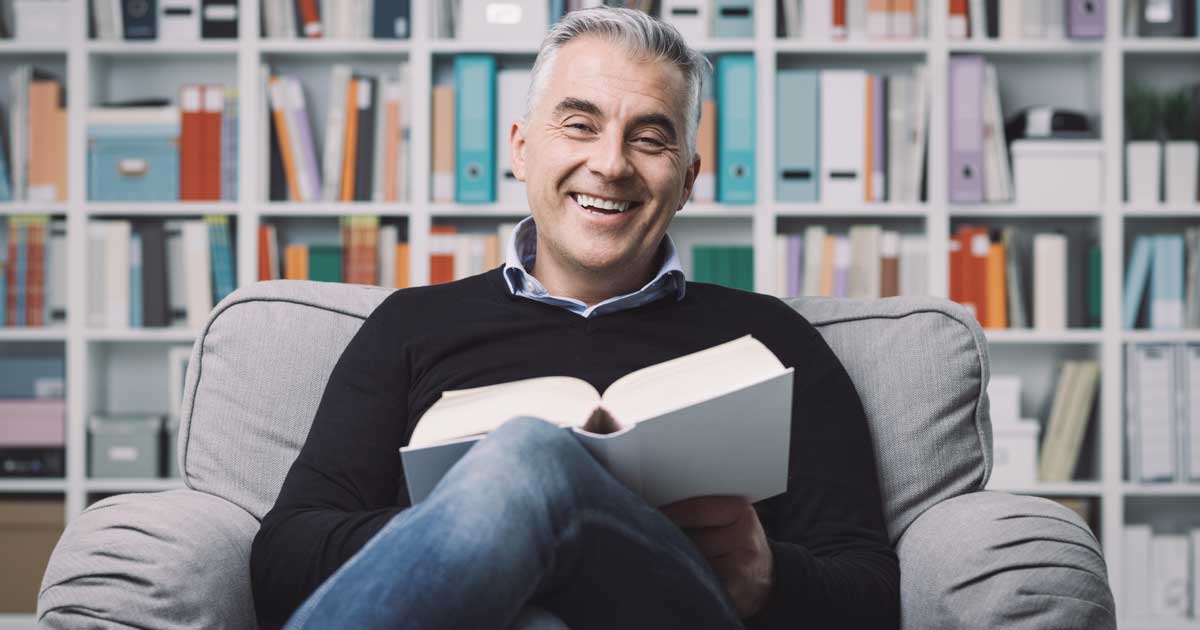
目標達成に役立つ本
目標達成のノウハウをさらに深く学びたい方向けに、2冊の本をご紹介します。
まず1冊めは、株式会社原田教育研究所代表、原田隆史氏が監修した『目標達成ノート STAR PLANNER』(ディスカヴァー・トゥエンティワン、2017年)です。本書は、原田氏が教員時代、陸上競技部を7年間に13回も日本一に導いた経験などをもとに書かれたもので、実践から得られた具体的なノウハウが詰まっています。
先ほど紹介した「目標達成シート」をはじめ、モチベーションを高める「目標・目的設定用紙(スターシート)」など、すぐに使える4つのツールが収録されています。
2冊めは、ベストセラーとなったビジネス本、スティーブン・ガイズ『小さな習慣』(ダイヤモンド社、2017年)です。『小さな習慣』では、タイトル通り、ほんの小さな習慣を始める大切さとコツを明快に論じています。
本書が提唱する習慣とは、例えば「腕立て伏せを1日1回」など、本当にごく小さなものです。たった1回の腕立て伏せから始まり、著者は本格的な筋力トレーニングを習慣づけることに成功したそう。なぜそんなことが可能なのか、という理由も、心理学や脳科学の観点からわかりやすく解説しています。
目標を達成する技術を究めたい方に、入門書としてオススメの2冊です。
目標を達成した後は……
最後に、努力が実って目標を達成できた後、何をすべきか考えてみましょう。達成後にすべきことには、以下の3つがあります。
勝因を分析
1つの目標を達成したら、「なぜ達成できたのか?」と振り返りを行ない、自分の強みと呼べるものを3つ発見してみましょう。一度得た “勝ちパターン” は、多くの場合、ほかの分野にチャレンジするときにも応用することができます。1回の成功で終わらせず次につなげるために、勝因の分析は大切です。
TOEICで800点以上とるという目標を達成したなら、ほかの資格試験や営業成績などの別の目標にも、同じようなプロセスを適用できるはずです。また、せっかく得た目標達成のノウハウは、ほかの人にも説明できるように言語化してみましょう。ノウハウを部下に伝授したりチームで共有したりすることで、組織全体の目標達成力を底上げすることができます。
次の目標を立てる
多くの場合、目標には次のステップがあります。1つの目標を達成して満足するのではなく、そこからさらに上のレベルを目指せないか、と考えてみましょう。例えば、
- TOEICで800点とれた→900点を目指そう
- 資格に合格した→その資格を活かして昇進を目指そう/より年収の高い会社に転職しよう
- 営業部門でトップになれた→2期連続トップを目指そう
このように、常に次の目標を設定しておくことで、「燃え尽き症候群」に陥らずに努力を続けられるはずです。
自分にご褒美をあげる
1つの目標を成し遂げたら、一息ついて自分にご褒美をあげましょう。どんなご褒美を用意するか、なるべく計画段階で決めておくことで、モチベーションを高められます。達成の喜びをしっかり味わい「頑張れば良いことがある」と自分に学習させることで、次の目標に向かうときの力にすることができるのです。
目標を達成するまでのプロセスだけでなく、達成したら次はどうするか、ということも計画の中に組み込んでおきましょう。
***
何か成し遂げたいことがある方や、漠然と何か打ち込めるものが欲しいと考えている方は、ぜひ本稿でご紹介した目標達成ノウハウを参考にしてみてください。
STUDY HACKER|日本の会社員の94%は「やる気がない」!? その原因は “4つの悪習慣” にあった。
STUDY HACKER|長期目標はなぜ達成できないのか。達成に必要な「4つの能力」、あなたは持ってる?
STUDY HACKER|二流は「やらないこと」を決められない。“コトの断捨離” で時間はいくらでも生み出せる。
STUDY HACKER|目標がいつも “机上の空論” になる人に欠けている2つの視点。
STUDY HACKER|「去年から1ミリも成長できない人」がやりがちな4つの悪習慣
STUDY HACKER|目標達成のために継続できる人は1万人に1人!? 「続かない人」ができていない3つのこと。
STUDY HACKER|「何をやっても続かない人」が陥っている “3つの大いなる誤解”
STUDY HACKER|“計画通りに行かない” は普通!? ノーベル経済学賞受賞者が教える「正しい計画の立て方」
STUDY HACKER|「できないこと」に時間をかけすぎるな! すぐできる「できること」「できないこと」の見分け方。
STUDY HACKER|あいまいな目標なんて意味がない! “具体化主義” の目標設定メソッド『SMART』を実践してみた。
STUDY HACKER|なぜか勉強したくなる!? 「やる気が出ない」が解消される『アメ』と『アメなし』の合わせ技
STUDY HACKER|成長速度を爆上げする「6×5のマトリクス」がすごい。課題ポイントを一気に発見できる!
STUDY HACKER|海外大学が証明。たった3つの「事前準備」で目標達成率が大きく上がるワケ。
STUDY HACKER|“見える化”でデキるビジネスパーソンに! メリットたくさんの「数字化」の技術。
STUDY HACKER|気づきを成長に変えるために。羽生結弦選手を支え続けた『発明ノート』の偉大なチカラ。
STUDY HACKER|売上げ600%アップを達成した私の秘術を大公開。1日5分の習慣で「本質的な仕事」を見極めろ!
STUDY HACKER|海外の著名学習コンサルタントに学ぶ! 絶対に「先延ばし」をしないための30の方法。
STUDY HACKER|忙しいときこそ振り返ろう。手軽に続けられる『KPT』という方法。
STUDY HACKER|いつまでも目標達成できない人が知らない「20%の法則」。最小の労力で最大の成果を生む方法とは?
STUDY HACKER|認知行動療法から考える。「問題解決」と「目標達成」のための7つのステップ
STUDY HACKER|ソフトバンク孫社長に学べ! 目標達成のためのすごいメソッド『高速PDCA』
STUDY HACKER|紙一枚でまとめる「トヨタ式」ドキュメント。無駄をなくして本質を伝える。
STUDY HACKER|仕事の効率は「手帳」が決める!? デキるビジネスパーソンになるための『手帳活用術』
STUDY HACKER|なぜ一流は “手帳の質” にまでこだわるのか? 倍以上の予算をかける深すぎる理由。
STUDY HACKER|「考える力」をつける8つの方法
STUDY HACKER|人は正しく考えるからこそ、正しく行動できる。 そして、考える前にもやるべきことがある【野村克也『カリスマの言葉』第5回】
コトバンク|一陽来復
ダイヤモンド・オンライン|脳をだまして、いつの間にか目標を達成する!
STUDY HACKER|「昨日から1ミリも成長できない人」には “この3つ” が欠けている。
News Picks|大谷を怪物にした花巻東高校の「目標達成用紙」
STUDY HACKER|勉強にも仕事にも! 大谷翔平も使う『目標達成マンダラート』がすごい
佐藤舜
大学で哲学を専攻し、人文科学系の読書経験が豊富。特に心理学や脳科学分野での執筆を得意としており、200本以上の執筆実績をもつ。幅広いリサーチ経験から記憶術・文章術のノウハウを獲得。「読者の知的好奇心を刺激できるライター」をモットーに、教養を広げるよう努めている。



